こんにちは!ようやく2025年夏のジョージア旅を開始した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)
一週間に渡って旅した、ジョージア西部の小コーカサス山脈エリア。
あの夢のような日々を総まとめするときがやって来ました…!
それが、今回の記事テーマであるバフマロ~ゴミスムタ間の2日間トレッキングです。

舞台となるのは、黒海と小コーカサスの山々に挟まれたグリア地方と、イスラムのエッセンス香るアジャラ地方。
このジョージア西部2エリアの境界を成す山々を縫うように歩く、アドベンチャー感あふれるトレッキングです。
トレッキングの拠点となるバフマロやゴミスムタの村のファンタジー感いっぱいの山村風景や、人の手の及ばない小コーカサスの圧倒的な大自然、厳しい自然環境の中で生きる人々との温かな出会い…
とにかく、ジョージアの山岳地域が有する魅力がぎゅっと詰まったエリアで、自分の足で歩いた人だけが見られる風景の数々は感動ものです。


「2日間のトレッキング」と聞くと、多くの日本人は二の足を踏んでしまうもの。
確かに初心者向けのルートではありませんし、インフラ面や宿泊施設の乏しさなど、ジョージア他エリアに比べてもかなり不便さが感じられます。
しかし…!実際に歩いて旅したのぶよ的には、本当に本当に本当におすすめ。
山が好きな人にはもちろんですし、「観光客だらけの定番山岳リゾートではない場所を旅したい!」という人にも心からおすすめです。

そんなわけで今回の記事は、バフマロ~ゴミスムタ間の2日間トレッキングの情報を総まとめしたもの。
基本となる2日間のコース詳細はもちろん、さらに先へと進みたい人向けのオプショナルルートや、実際に歩いたからこそ分かる注意点やアドバイスなど、大ボリュームの記事となっています。
ネット上には情報はほとんどなく、知名度も完全にゼロなエリアではあるものの、この場所の「ジョージアの山岳地域ならではの魅力」はまさに本物。
決して万人向けのルートではありませんが、日程や体力が許すならぜひとも挑戦してほしいです。
いっぽう「やっぱり歩くのは無理…」という人でも、この記事でのぶよの冒険を追体験できるはず。
さあ、誰も知らない小コーカサスの雲海の上へと旅立ちましょう!
バフマロ~ゴミスムタ2日間トレッキング基本情報

今回紹介するバフマロ~ゴミスムタ間の2日間トレックは、その名の通りグリア地方の山岳避暑地として知られるバフマロと、ダイナミックな雲海の風景が有名なゴミスムタの二つの村を結ぶコース。
歩く距離の合計は30kmほどでアップダウンもあるため、1日で歩ききることは不可能です。
まずは、トレッキングのイメージをつかむために、このルートの基本情報を解説していきます。
トレッキングのルート&マップ
青:2日目のコースとポイント
オレンジ:3日目&4日目のコースとポイント
黄色:マルシュルートカ発着ポイント
バフマロ~ゴミスムタ間2日間トレックの基本となるのは、1日目のバフマロ~メリア・ケリ村間(15km)と2日目のメリア・ケリ~ゴミスムタ間(17km)。
標高はコース全域が2000m~2500mの間に位置しており、高地ならではの美しい自然風景が最大の魅力です。
バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も、夏季限定でマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が下界とを結んでいるので、この2日間トレックだけを楽しんで下界へと戻ることが可能です。
いっぽう、日程や体力、天候が許すのであれば、ゴミスムタから南へと山を下り、アジャラ地方のハベラシュヴィレビ村まで+2日間かけて歩くオプショナルコース(13km+13km)もおすすめ。
このオプショナルコースは未舗装道路に沿って延々と歩くだけのものでトレッキング的な醍醐味は少な目ではあるものの、周囲の風景の美しさや絶景コテージでの宿泊体験が味わえます。
トレッキングコース上の主な見どころ

バフマロ~ゴミスムタ間2日間トレックの最大の見どころとなるのは、スタート/ゴール地点となる二つの村。
グリア地方最奥部に位置する「雲の上の村」・バフマロと、雲海発生率の高さで知られる「雲の王国」・ゴミスムタです。


バフマロ/ゴミスムタのいずれも、夏場の間だけ住人が戻ってくる避暑地としての性格が強い村。
いずれもグリア地方山間部伝統の木造建築が緑の丘陵地帯に点在する風景がとにかく美しく、トレッキングの拠点としてだけでなく観光目的での滞在も充実したものとなるでしょう。
バフマロ/ゴミスムタ以外にも、トレッキングコース上には小コーカサスの大自然と山岳地域ならではの伝統が織りなす美しい風景がたくさん。
コース全体を通して雲海が見られる確率がとても高いため、下界とは隔絶された地らしい非現実的な風景を24時間堪能することができます。


また、ゴミスムタから南のアジャラ地方方面へと歩を進めるオプショナルコースもおすすめ。
雲海を見渡すポイントに整備されたジュワリミンドリの無料コテージでの宿泊体験や、中世の姿をそのままに残すハベラシュヴィレビの木橋など、小コーカサスの山々ならではの穴場スポットも点在しています。
トレッキングの必要日数

「2日間トレック」と題している通り、バフマロ~ゴミスムタ間のトレッキング自体に必要な日数は2日間。
しかし2日間だけの日程だと、1日目の朝に下界からバフマロ入りしてすぐに歩く→2日目の夕方にゴミスムタに到着してすぐに下界へ戻るという行程となるため、ハイライトとなるバフマロ&ゴミスムタの村を楽しむ時間はほぼありません。
というわけで、この2日間というトレッキング自体の必要日数に加え、前後に1日ずつバフマロ/ゴミスムタを観光する日を設けて4日間確保するのが理想的です。
ゴミスムタからオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へと抜ける場合は、ゴミスムタ~ジュワリミンドリ間に1日/ジュワリミンドリ~ハベラシュヴィレビ間に1日の、計2日間追加が必要。
つまり、オプショナルコースを含めて制覇したい場合、合計で6日間の日程が必要です。
ちなみに、のぶよの実際の行程は以下の通り。
悪天候に備えて予備日を1日確保して、合計7日間かけて旅しました。▼
・1日目:オズルゲティからバフマロへ移動
・2日目:バフマロでのんびり
・3日目:バフマロ~メリア・ケリ間トレック
・4日目:メリア・ケリ~ゴミスムタ間トレック
・5日目:ゴミスムタでのんびり
・6日目:ゴミスムタ~ジュワリミンドリ間トレック
・7日目:ジュワリミンドリ~ハベラシュヴィレビ間トレック
トレッキングの難易度

バフマロ~ゴミスムタ間のトレッキングの難易度は、中級レベルといったところ。
コース自体は多くが未舗装の道に沿って歩いていくだけの簡単なもので、山道を歩く区間や岩場を登る区間はほぼありません。
ではなぜこのトレッキングの難易度が初級ではないのかと言うと、高低差が結構あるのと、時期によっては残雪の上を通る危険な箇所もいくつかあるため。
コースの高低差は500mくらいと一見大したことなさそうですが、登ったと思ったら下ってまた登って…を繰り返すので(特に2日目)、体力的にも精神的にも少しハードに感じられます。
また、のぶよが歩いた7月中旬であってもコースが残雪でブロックされている箇所があり、傾斜のある滑りやすい雪の上を歩く場面(バランス崩したら谷底へさようなら)もいくつかあり、結構危険だと思いました。
というわけで、全く山を歩いた経験のない初心者には、このトレッキングは不向き。
ある程度山歩きをしたことがある人であれば、まあ問題なく歩けるはずです。
トレッキングの歩く方向

バフマロ~ゴミスムタ間の2日間トレッキングは、バフマロスタート/ゴミスムタスタートのいずれで歩くことも可能。
バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も標高は2000mほどと同じような高さの場所に位置しており、いずれの方向で歩いても最終的な高低差はほぼ変わりません。
しかしのぶよ的には、本記事で紹介している通りの順番でバフマロ→ゴミスムタの方向で歩くのが断然おすすめ。
理由はいくつかあるのですが、ゴミスムタをゴール地点にした方がその後のプランの選択肢が増える(マルシュルートカでそのまま下界へ下りるorオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へ抜けるorキントリシ国立公園方面へ抜ける…)のが最大のポイント。
小コーカサスのどん詰まりのような場所にあるバフマロをゴールにしてしまうと、到着後はマルシュルートカで下界に下る一択となってしまいます。
また、バフマロの方がゴミスムタよりも村として発展している点も重要。
バフマロであれば、軽食類やパン類などトレッキング中に必要なものが入手しやすいですが、ゴミスムタではそうした手段がかなり限られている(電気すらない)ので、トレッキング前に必要なものを準備できるという意味でもバフマロスタートの方が何かと安心だと思います。
トレッキングの装備

すでに触れた通り、バフマロ~ゴミスムタ間の2日間トレッキングコース上には本当に何もありません。
拠点となるバフマロとゴミスムタであれば、商店や飲食店、宿泊施設もいちおうあるので何とかなりますが、1日目の宿泊ポイントとなるメリア・ケリ村には商店も宿泊施設も何も存在しないのです。
そのため、このトレッキングに挑戦する場合に絶対に必要なのは、テントや寝袋などのキャンプ装備。
これらを担いだ状態で歩くことになる点も、このトレッキングが初心者には難しい理由かもしれません。
また、コース上で食料を入手することは不可能であるため、日持ちする食べ物or簡易コンロなどの自炊器具も欠かせません。
飲料水に関しては、各宿泊ポイントやコース上に飲用可能な湧き水が多くあるため、心配はないでしょう。
また、残雪の上を渡る場面が多くあるため、トレッキングシューズなどの装備も不可欠。
橋の架かっていない川を渡る場面も無数にあるので、サンダルを持参するのがおすすめです(のぶよは気合で裸足で渡ったけど、絶対サンダルがあった方が安心)。
1日目:バフマロ~メリア・ケリ

トレッキング1日目は、バフマロからメリア・ケリまでの峠越えを含むコース。
距離も高低差もコースで最大となり、初日にして結構な難関となります。
・距離:15km
・所要時間:5時間~6時間
・高低差:▲694m
・難易度:★★★★☆
トレッキングのスタート地点となるバフマロ【マップ 緑①】は、ジョージア人が憧れる山岳避暑地としての性格が強い村で見どころもあるため、トレッキングとは別に1泊はするのがベスト。
標高1900m~2100mほどの地点に可愛らしい木造コテージや民家が散らばる風景は、まるでおとぎ話の世界のような美しさです。


バフマロから最高標高地点となるサコルディア峠まで延々と登り坂が続き、峠を越えるとメリア・ケリまで緩やかな坂道を下っていくようなコース。
1日目のゴールとなるメリア・ケリ村の素朴な風景も楽しみです。
バフマロ~グリア側最後の集落

絵画のような風景が広がるバフマロの村に別れを告げたら、村の中心部に架かる唯一の橋を渡ってトレッキングコースへと入ります。
しばらくは川沿いに延々と未舗装道路を歩いていくだけのシンプルなルートで、だんだんと建物は少なくなり、最終的には森の中を抜けていくコースに。


渓谷沿いを抜けると、本格的な上り坂のはじまり。
ここからサコルディア峠まではずっとこんな感じで上り坂が続いていきます。▼

どんどん小さくなってゆくバフマロの村を背にひたすらに登っていくと、傾斜は徐々に急なものに。
この辺りまではまだ木々も生えていますが、さらに登ると森林限界を超えて一面の草原が広がる風景になっていきます。


バフマロを出発して5km/2時間ほどの地点で、サコルディア峠のグリア地方側最後の集落【マップ 緑②】に到着。
一面の緑を背景に伝統の木造民家が散らばるだけの小さな集落ですが、いちおう住人の姿はありました。▼

グリア側最後の集落~サコルニア峠

グリア地方側最後の集落には特に名前などはないのですが、ここがサコルディア峠前で水を補給できる最後のポイント。
集落には湧き水もありますが、住人に頼んで水を補給してもらうのもアリです。


集落を出て南へと続く未舗装道路を登っていくと、そこは完全に無人の小コーカサスの山々。
サコルディア峠までの道は傾斜がきつめで、地図で見る以上に時間がかかります。

…と、こんな感じで順調に歩いていたのですが、何やら空が急に雲で覆われはじめ、ものすごい雷鳴がどんどん近づいてくるおどろおどろしい雰囲気に。
そう、嵐がやって来たのです。
はじめこそぽつりぽつりと降り始めた雨はいつの間にか大降りとなり、とうとう雹が大量にどわぁ~っと降りだす始末。
さすがにこの状態で歩くことはできないのですが、周囲には民家どころか木の一本さえなく、雷のことを考えるとかなり危険です。
ヒイヒイ言いながらも前に進んでいると、なんと目の前に小さな掘っ立て小屋が。
あまりの大量の雹で視界真っ白の中、小屋まで無我夢中で走ると、そこにはすでに先客がひとりいました。

それが、こちらのおじさん。
なんでも峠の向こうにある自宅(夏場だけ住んでいるらしい)に戻る途中で嵐に遭い、この小屋で雨宿りしていたのだそうです。
ペチカ(ソ連式の暖炉)に薪で火を灯し、びしょびしょになった服や靴を少しでも乾かし、つかの間の暖を取る幸せ…
外では嵐が想像以上に長く続いており、ものすごい轟音とともに粗末な小屋の屋根を雨粒が叩きます。
「もしもこの小屋を見つけていなかったら…もし小屋の鍵が閉まっていて無人だったら…」と考えるとなんとも恐ろしくなりますが、それもこれもコーカサスの山の神の思し召しだったのかもしれません。
2時間以上雨宿りしてようやく嵐が去ると、外では太陽の淡い光が差し、鳥たちのさえずりが聞こえるように。
地獄から一転しての天国のような風景を前に、おじさんはこう言います。
「馬、乗れるか?」と。

なんとおじさん、バフマロから馬を連れて自宅へ戻る途中だったようで、小屋の外には滑らかな毛並みの馬が留めてありました。しかもなぜか二頭。
そういうわけで、空いている一頭に乗ってこのまま峠を越えようということだそう。
しかしながら、のぶよは乗馬経験がいっさいありません。
とはいえ、雨宿りでかなり時間をロスしてしまったため、このまま歩いて峠越えをするのはかなりハード。
「まあメリーゴーランドは乗ったことあるしな…」と謎の理論で自分を勇気づけて、いざ人生初の乗馬…!

まさか人生初の乗馬が、こんなジョージアのコーカサスの山奥で、しかも観光乗馬体験ではなく純粋な移動手段として、しかも無料ですることになるとは夢にも思っていませんでしたが、いざ馬にの乗ってみると意外となんとかなるもの(運動神経良いタイプ)。
手綱の引き方など全く知らないままに見よう見まねで、必死にスイスイと進むおじさんの後をついていきます。

はじめこそ振り落とされないように必死だったのですが、徐々に慣れてきて周囲の風景を楽しむ余裕も。
よくよく考えてみると、コーカサスの一面の緑の山々を馬に乗って移動するなんて、旅の浪漫が詰まりまくった体験に他なりません。
言葉を失うような非現実的な情景に感動しっぱなしで到着したのが、この日の最高標高地点であるサコルニア峠【マップ 緑③】。▼

標高2500mを越える高地に位置する峠付近は、まだ雪が多く残っている初夏の風情。
これまで辿ってきたグリア地方側の山々と、これから目指していくアジャラ地方側の山々の両方を見渡すことができ、開放感にあふれる風景に癒されます。
サコルニア峠~メリア・ケリ

おじさんの家があるのはサコルニア峠を越えて少し下った先だということで、引き続き馬に乗っての移動が続きます。
峠を越えると道は緩やかな下り坂となり、高山植物も多く見られる楽園のような雰囲気に…
もはや見るものすべてが夢の中の光景のように美しく幻想的で、このままずっと馬に乗っていたいなんて思ってしまったほどです。


こうしてようやく辿りついたのが、おじさんの家があるポイントとメリア・ケリ村までの道が分岐する地点。
おじさんは「うちに泊まっていけ」と何度も提案してくれたのですが、それはあまりに申し訳ない&翌日のルート的に不便になるためお断りし、ここからは自分の足で歩いていきます。
この地点からメリア・ケリ村まではあと3kmほどで、遥か彼方に集落の遠景が望めるほど。
緩やかなアップダウンの道をひたすらに歩いていきます。


メリア・ケリ村の北側には川が流れており、いったん川まで下って再び村まで登るというルート。
この川がグリア地方とアジャラ地方の境界となっているようで、川の向こうのメリア・ケリ村はアジャラ地方となります。

そんなこんなで、ようやく到着したメリア・ケリ村【マップ 緑④】。
ここも夏場だけ住人が戻ってくる山村で、7月前半はまだ村人の姿はあまりなくとても静かな雰囲気でした。
メリア・ケリ村の宿泊

メリア・ケリ村には宿泊施設は一つも存在しないため、基本的にはキャンプすることになります(冬場だけオープンするドイツ人経営のマウンテン・ハットがあるけど、夏場は閉鎖されている)。
キャンプは村の全域で自由にできますが、野生動物などのことを考えるとできるだけ民家が見える範囲の場所を探すのが◎
のぶよはメリア・ケリ入口にある空き地にテントを張りましたが、ここからの夕景がとにかく素晴らしくて大満足でした。


これまで馬&自分の足で歩いてきた山々に沈んでいく夕日は、感動的なほどの美しさ。
日が沈んだ後の村は完全なる静寂と深い闇だけに支配され、頭上に広がる一面の星空がとにかく綺麗でした。
2日目:メリア・ケリ~ゴミスムタ

2日目のコースは、メリア・ケリ村からゴミスムタまでの標高が高い地点を歩いていくコース。
コース前半だけガッツリと登り、あとは基本的に下りとなりますが、登ったり下りたりのアップダウンが結構激しいので意外と疲れるかもしれません。
・距離:17km
・所要時間:5時間半~6時間半
・高低差:▼580m
・難易度:★★☆☆☆
のぶよが一晩を明かしたメリア・ケリの村はずれから中心部方面へと坂を登っていくと、徐々に建物が増えていきます。▼


多くの家屋にはまだ住民が戻って来ていないようでしたが、生活の香りが漂う建物もいくつか。
メリア・ケリより先にはゴミスムタまで水を補給できる場所は一つもない(チンチャオ湖の湖水はあるけど飲めるか微妙)ので、住民に頼むなどして必ず飲料水の確保をしておきましょう。
メリア・ケリ~チンチャオ湖

緩やかな山の斜面にひらけたメリア・ケリ村を中心部へと登っていくと、T字路に突き当たります。
ここを左(南)に曲がるとそのままアジャラ地方方面へと下りる山道に、右(西)に曲がるとゴミスムタ方面へと続く未舗装道路になります。
今回はゴミスムタ方面へ向かうのでT字路を右に曲がりるルート。
住人たちに笑顔で手を振られながら、小さくも美しい村を背にひたすら歩いていきます。


傾斜はそこまできつくはなく、見通しの良い丘陵地帯を歩くだけなので、この辺りは余裕。
だんだんと小さくなってゆくメリア・ケリ村を望みながら、さらに標高の高い地点へと登っていきます。

マップを見ると延々と登りが続くのかと思いきや、意外とアップダウンがあるのが2日目の前半。
登ってはまた下って…を数回繰り返すことになるので、「また登るの…?」と感じながらも、前に進むしかありません。
メリア・ケリ村を出発して約30分くらい、標高2300mを越えるあたりでは、7月前半だというのにまだ残雪が多く残る箇所がいくつもあります。
未舗装道路が雪で覆われていて進路がわからない&シャーベット状になった雪が滑りやすいというわけで、かなり危険を感じました。


残雪を避けることができればベストなのでしょうが、基本的に迂回ルートはなくすぐ横は谷底。
山の斜面を覆うように残っている雪の上を歩くしかないのですが、とにかく危ないので要注意です。
こんな感じの残雪を越えること数回、ようやく本日の最高標高地点となる峠に到着しました。【マップ 青①】

▲峠付近には、かつてこの道を歩いた冒険者たちが積み上げた石の山が。
近くにある石をひとつ上にのせ、自分も確かにこの場所に到達したという証を刻みます。

峠を越えた後はアップダウンは少なめとなり、基本的に緩やかな下り坂が続くので、体力的にはかなり楽。
次のポイントであるチンチャオ湖まで、開放感あふれる風景の中を快適に歩いていきます。
チンチャオ湖~ゴミスムタ

メリア・ケリ村を出て1時間半ほど。
トレッキング2日目の休憩ポイントにぴったりなチンチャオ湖に到着しました。【マップ 青②】。
チンチャオ湖は標高2500m付近にあるアルピンレイクで、湖水は全て湖の底に湧く水で占められているそう。
湖に流れ込む川はなく、そのためなのか湖水の透明度がとても素晴らしいです。


夏のハイシーズンになると、ゴミスムタからオフロード車でやって来るジョージア人観光客で大いに賑わうらしいチンチャオ湖。
しかしこのときはまだシーズン前だからなのか、人影はいっさいありませんでした。
人里離れた山の中にぽつりとある湖を、たった一人ぼんやりと眺めながらの極上のランチ休憩。
十分にエネルギーをチャージして、再び歩きはじめます。

チンチャオ湖~ゴミスムタ間は10kmほどの道のりで、ほとんどは下り坂なのでかなり楽。
だんだんと近づいてくるゴミスムタの村の風景を前に、ひたすら歩いていきます。


ゴミスムタに至る道はいくつかあるのですが、のぶよは村の東側をぐるりと周って中心部に至るルートを歩きました。
一面の緑に包まれた村の美しい風景は、ここまで歩いた人だけが見られるものです。

こうして到着したのが、2日間トレッキングのゴール地点となるゴミスムタ。【マップ 青③】
「雲の王国」と称されるこの小さな村は雲海発生率の高さで知られ、まるで村を呑み込まんばかりに迫る雲が織りなす圧巻の風景が見られます。

ゴミスムタの美しさは期待以上のもので、「頑張って歩いて良かった…」と感動を覚えるはず。
点在する木造コテージや民家のたたずまいも含め、おとぎ話の世界観を具現化したような風景が見られます。
ゴミスムタの宿泊

ゴミスムタはバフマロと同様に、住人の多くが夏場だけこの地に戻ってくる村。
村には旅行者向けにコテージを一棟貸ししているところもいくつかありますが、ゲストハウスのような手頃な宿は基本的にないのがネックです。
のぶよの場合、ゴミツムタ到着日はそのまま村はずれでテントを張りましたが、ゴミスムタ2日目は村中心部の民家兼ゲストハウスに泊まれることに。
スマホを充電させてもらおうと道端にいたおばちゃんに声をかけたところ、「電気通ってないけど無料で泊まって良い」とのことで、またもやミラクルが起きました。
おばちゃんの民家は一階が住居/二階が旅行者向けの宿泊スペースとなっており、昨年二階部分を改装したばかりだそう。
木の温もりが感じられる明るい空間で、正直こんな良いところで寝られるとは思っていなかったのでびっくりです。


そんなわけで、電気もインターネットもお湯もないながらも快適な宿泊ができたゴミスムタ。
ムツヴァディ(豚肉BBQ)をお裾分けしてもらったり、宿泊先の向かいにある絶景カフェで数日ぶりの生ビール(しかも3GEL=¥150と激安)に感動したりと、トレッキングの疲れを存分に癒すことができました。

ゴミスムタをトレッキングのゴール地点とする場合、ここから下界方面へのマルシュルートカを利用することも可能。
のぶよはさらに2日間追加して、アジャラ地方側へと歩いていくオプショナルプランへと進みました。
3日目&4日目(オプション):ゴミスムタ~ジュワリミンドリ~ハベラシュシュヴィレビ

ゴミスムタからさらにトレッキングを続ける場合、南のアジャラ地方方面へと下るのがおすすめ。
ゴミスムタから、マルシュルートカ便がある最初の村であるハベラシュヴィレビまで、約25kmほどの道のりです。
最初の13kmほどは緩やかな上りとなりますが、道のりの大半は下り坂であり、距離的にも1日で歩ききることは可能。
しかし、のぶよ的には2日間かけて歩くのが断然おすすめです。


▲2日間の日程を勧める最大の理由が、ジュワリミンドリというポイントにある無料コテージの存在。
この場所に宿泊して、一面の雲海を前にのんびりと滞在することこそが、このオプショナルコースを歩く最大のハイライトとなるためです。
ゴミスムタ~ジュワリミンドリ

ゴミスムタ~3日目の宿泊地となるジュワリミンドリまでは、南へとのびる未舗装道路をずっと歩いていくだけ。
全体的に上り坂とはなっているものの、アップダウンは少ないので、かなり快適に歩くことができます。
・距離:13km
・所要時間:4時間~5時間
・高低差:▲259m
・難易度:★☆☆☆☆
ゴミスムタを出発して歩いていくと、途中にはいくつも名もなき集落の風景が。
おそらく人が住んでいるような感じでしたが、この山奥での暮らしはかなり不便なのではないかと思います。


未舗装道路は車両の通行も可能ではあるのですが、この道を通る車はほとんどなし。
ごくごくたまに車が通ると、ほぼ100%の確率で「乗るか?」と向こうから提案してくれます。
せっかくなので自分の足で歩きたい派ののぶよは、この好意を丁重にお断りしてひたすら歩き続けるのみ。
ゴミスムタを出て約3時間半ほどで、アジャラ地方側の山々を望むちょっとした平地のようなポイントに到着しました。▼

ここがジュワリミンドリ(Jvarimindori)と呼ばれるポイント。【マップ オレンジ①】
村ではなく基本的に無人の場所であるため、マップアプリには地名の記載はないものの、地元の人に「ジュワリミンドリ」と言えば100%通用します。
ジュワリミンドリは、下界の人々の日帰りピクニックスポットとして機能しているような場所。
敷地内には炭火BBQをするためのスペースやピクニックエリアが整備されており、土日の昼間であれば仲間内でワイワイ楽しむジョージア人たちの姿が見られるかもしれません。
ジュワリミンドリの宿泊

のぶよはジュワリミンドリでテントを張って泊まろうと考えていたのですが、いざ実際に到着してみるとそこには4基の木造コテージのような建物が。
コテージの扉は開け放たれており、内部に自由に立ち入ることができます。


「え…?なにこれ…?」と戸惑っていると、ちょうどすぐそばでBBQをしていたジョージア人のおじさんが「ああ、ここ無料で泊まって良いんだぞ」との神情報をくれました。
どうやら、アジャラ地方の政府観光局(※アジャラ地方は自治権を有しており、ジョージア政府から半独立している)が山間部の観光インフラ整備の一環として、これらのコテージを旅行者向けに無料開放しているのだそう。
いやもう…まじですか…太っ腹がすぎるのでは…
正直この3日目のキャンプ泊は野生動物との遭遇リスクが最も高いだろうと考えて怯えていたのぶよにとって、コテージに泊まれるなんてまさにコーカサスの山の神からの贈り物に他なりません。


そんなわけで、アジャラ地方の太っ腹観光局に心の中で感謝しまくりながらも荷物を下ろし、コテージ周辺のピクニックエリアからの絶景を堪能。
すぐ目の前にはアジャラ地方の深い山々が広がり、それらを覆うように一面の雲海が広がります。
ピクニックエリアでは、先ほど話したジョージア人おじさん二人組が連れて来たというロシア人日帰りピクニック観光客グループの姿が。
おじさんたちはバトゥミでミニバスの運転手をしているそうで、こうして下界から少人数グループを山間部に連れて来るツアーでお小遣い稼ぎをしているのだそうです。

ロシア人観光客グループはちょうどこの場所で腹ごしらえをする行程のようで、ジョージア人おじさんたちはムツヴァディ(炭火豚肉BBQ)をひたすらに焼いていました。
辺りには肉を焼くあの良い香りが漂い、なんとも食欲が刺激されます…
といったところで、おじさんが近づいてきては「ほれ!」と手渡してきたのが巨大な肉塊とパン。
なんというか、ここまで来ると「あ、ぜったいこれお裾分けしてくれるパターンだわ」と半ば予想できていたのですが(卑しい)、やっぱりジョージア人にとってシェアしないという選択肢はないようです。

自分のコテージと、その先に広がる一面の雲海を眺めながら食べるBBQは、言うまでもなく絶品のひとこと。
なんだか毎日誰かに餌付けしてもらっているような気もしますが、旅の恥はかき捨て。ありがたくいただいておくことにします。
こんな感じでお腹は満たされ、おじさんたちはロシア人観光客を連れてミニバスで去っていき、ようやくジュワリミンドリのコテージ広場にも夕方の静寂が…訪れませんでした。

日没まであと1時間ほど…といったタイミングでやって来たのが、ジョージア人五人組。
さらに山奥で道路工事の仕事をした帰りにこの場所で飲んでいこうと立ち寄ったのだそうですが、もうすでにべろんべろんに酔っぱらっています。
ジョージア地方部をある程度旅している外国人なら、この状況はもはや確実に巻き込まれて飲まされるパターンだと即座に察知できるものですが、やはり予想通りの流れに。
「一杯だけ」と言われて注がれたチャチャ(度数60%の蒸留酒)を飲み干すと、さらにグラスが満たされ、さあ飲めさあ食えの大合唱となります。
…ジョージアでは「一杯だけ」なんていう概念はやはり存在しないのかも。

そんなわけで、謎の外国人に散々飲み食いさせて満足したらしいジョージア人五人組はボロボロのソ連ワゴン車で颯爽と去っていき(どう考えても飲酒運転すぎるけど法律だいじょぶそ?)、とうとうジュワリミンドリにも静寂が訪れます。
周辺には民家の一つもない山奥であり、ジュワリミンドリ自体にも電気は通っていないので、光の一つもない闇空には一面の星空が広がります。
先ほどまでは常に誰かがいて、わいわいと楽しんでいたのが嘘だったかのように、今この場所にいるのは自分だけという極上の孤独感。
驚くほどに温かいコテージの中から闇夜を眺めながら、いつの間にか眠りについていました。


ジュワリミンドリには、飲用可能な湧き水を引いた水道と、簡易トイレ(もちろん水洗ではない)が設置されています。
今後さらに整備を進める計画もあるそうですが、個人的にはこれくらいの規模で十分なのではないかと思います。
ジュワリミンドリ~キントリシ国立公園方面へのルート
本記事ではジュワリミンドリから南へと続く未舗装道路を下っていくコースを掲載していますが、実はジュワリミンドリからはもう一つ別のルートが存在します。
それが、西に位置するキントリシ国立公園方面へと抜けるルート。

ジュワリミンドリのコテージ広場には分岐点(標識あり)があり、ここを西へと進めばキントリシ国立公園。
必要な日数は+2日間で、途中のヒノ(Khino)という村に一軒のゲストハウスが、ゴールのチャハティ(Chakhati)という村からはマルシュルートカ便が運行されています。
のぶよは元々こちらのルートへと進む予定だったのですが、あいにく天気予報は下り坂。
今回はキントリシ国立公園は諦めて、素直にハベラシュヴィレビ方面へと下ることにしました。
ジュワリミンドリ~ハベラシュヴィレビ

ジュワリミンドリからオプショナルコースのゴール地点となるハベラシュヴィレビ村までは、未舗装道路を延々と下っていくだけ。
最初の数kmは雲海を眺めながら歩くことができますが、後半は雲海の中~下へと入ってただひたすらに九十九折りの山道を下っていくだけなので、正直退屈だと思います。
・距離:13km
・所要時間:4時間~5時間
・高低差:▼1440m
・難易度:★☆☆☆☆
13kmの距離で1440mの標高差を下ることとなるので、コース後半は結構な下り坂が延々と続き、体力的には楽でも肉体的には結構ハード。
また、下れば下るほどに湿度が上がってくるため、一歩進むごとに一つ暑さが増していくような、かなりの不快感を感じながら歩くことになるでしょう。


というわけで、4日目のコース(特に後半)はヒッチハイクで移動してしまうのもアリ。
車の量は相変わらず絶望的に少なくはあるものの、通る車はほぼ100%停まってくれます。
のぶよの場合は頑固なので(みんな知ってる)、せっかく停まってくれたおじさんの車を「最初から最後まで歩きたいから」と断ったのですが、結局はおじさんの車に乗せてもらうことに。
というのも、歩き続けていたら天気が急に下り坂になってきて「おうちかえりたいいいい」と半泣きで歩いていたところで、偶然先ほどのおじさんの車がエンストして止まっていたのです。▼

ミラクルだったのが、のぶよがおじさんと再会するやいなや、なぜか車のエンジンがかかって動きはじめたこと。
おじさんは車が直ってハッピー、のぶよは雨の中歩かずに済んでハッピー…世界ってうまいことできていますね(どういうこと?)。
というわけで、最後は車にがったんごっとん揺られて目的地のハベラシュヴィレビ村に到着しました。

ハベラシュヴィレビ村は想像以上に小規模で、山の斜面に民家が十数軒点在しているだけ。
村の中心部には二軒の商店があるものの、この日は日曜日で休業していました(ゴール地点でビールをプシューっとやりたかったのぶよ、涙目)。
どうしてわざわざこの小さな村をゴール地点にしたのかというと、ハベラシュヴィレビ村からバトゥミ方面へと抜けるマルシュルートカ便があるため。
それに加えて、ジョージアの国指定重要文化財であるハベラシュヴィレビの木橋に立ち寄りたかったためです。
ハベラシュヴィレビの木橋

商店があるハベラシュヴィレビ村の中心部から村の南側を流れる渓流へと下る道を500mほど歩くと、ハベラシュヴィレビの木橋が姿を現します。【マップ オレンジ②】
深い緑の渓流地帯に凛とたたずむ風景は、まるで絵画のよう。
湿度の高い空気も相まってか、どこか日本の山間部にありそうな風景をほうふつとさせます。
この場所にこの橋が架けられたのは約300年前のこと。
村に住む一人の男性が周辺で採れた木を加工し、長さ26mに及ぶ総木造の屋根付き橋を完成させたのです。


ハベラシュヴィレビの木橋に使用されているのは、樫やヘーゼルナッツ、ライムなどの樹木。
アジャラ地方山間部にはかつてこうした木橋が多くありましたが、多発する増水でその大半は流されてしまい、オリジナルがそのまま残っているのはなんとここだけなのだそうです。
その文化的・歴史的価値が高く評価され、ジョージアの国指定重要文化財にも指定されているハベラシュヴィレビの木橋。
これまで見てきた山のダイナミックな風景の数々の後だと少し地味に映ってしまう点は否めませんが、貴重な文化財として一見の価値があります。

木橋の見学を終えたらふたたびハベラシュヴィレビ村の中心部へと戻りましょう。
毎日15時頃にバトゥミ方面へと向かうマルシュルートカがこの場所を通過するので、時間に合わせて待機していればOKです。
こんな感じで、グリア地方とアジャラ地方をまたいで旅したトレッキングも終了。
数日ぶりの下界の空気はなんだかとても新鮮で、「好きな時に好きな物が手に入る」とぃう当たり前のことにさえ感動を覚えるはずです。
バフマロ~ゴミスムタ間トレッキングの拠点へのアクセス

バフマロ~ゴミスムタ間トレックの拠点となるのは、バフマロとゴミスムタのいずれかの村。
どちらの村へも、同じグリア地方のオズルゲティから夏季限定でマルシュルートカが運行されており、個人で安く移動することが可能です。
もし3日目&4日目のオプショナルルートを歩く場合は、アジャラ地方山間部のハベラシュヴィレビ村やキントリシ国立公園の入口となるチャハティ村が交通の拠点。
この場合でもマルシュルートカ便が運行されているので、個人での移動も可能です。
タクシーでサクッと移動するのもアリではありますが、注意したいのはトレック拠点となるいずれの村にも客待ちのタクシーは存在しない&配車アプリは使えない点。
行きはバトゥミやオズルゲティなどの大きな町からタクシーで移動することが可能ですが、トレックを終えた帰りに各村からタクシーを利用することは不可能だと考えておきましょう。
バフマロへのアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、最も便利なのが同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。▼
もしくは、バトゥミ~バフマロを直接移動することも可能。
バトゥミ~バフマロ間には、夏季限定で直行のマルシュルートカが1日1往復しています。
バトゥミ側の発着ポイントは、中心街東側のオールド・バスステーション。
バスステーションの建物南側の一角からの出発です。▼
ゴミスムタへのアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合に最も便利なのが、同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。▼
このマルシュルートカ便の最大のネックが、運行スケジュールが2日に1本と不確定要素が大きい点。
ゴミスムタに到着してマルシュで下界に下ろうと考えていても、その日は運悪くマルシュの運行がない…なんてケースも考えられます。
ゴミスムタ→オズルゲティへマルシュで移動する場合、ドライバーに直接電話してスケジュールを確認しておくのが良いでしょう。
ハベラシュヴィレビのアクセス

オプションとなる3日目&4日目のルートを経由した場合、ゴール地点となるのはハベラシュヴィレビ村。
ハベラシュヴィレビ~バトゥミ間は1日1往復のマルシュルートカが運行しているので、簡単に移動することができます。
この便はハベラシュヴィレビ始発ではなく、さらに山奥の村からバトゥミまでを結ぶルート。
バトゥミ行きの便がハベラシュヴィレビを通過するのは、平日&土日のいずれも15:00過ぎです(のぶよが乗ったときは15:10分くらいにマルシュが来ました)。
もし1日1本というスケジュールが不便な場合は、ハベラシュヴィレビからさらに10kmほど山道を下り、メインの幹線道路沿いにあるヒチャウリ(Khichauri)という村まで下りるのも一つの手。▼
バトゥミ~フロを結ぶこの幹線道路沿いには、バトゥミ方面/フロ方面のいずれにもマルシュルートカが頻発しているので途中乗車しやすいです。
直接バトゥミに戻っても良いですし、幹線道路沿いにあるアジャラワイン街道やフロなど、アジャラ地方山間部エリアへと足をのばしても良いでしょう。
チャハティへのアクセス
ジュワリミンドリからキントリシ国立方面へと抜けるルートを歩く場合、他都市とを結ぶ公共交通機関がある最初の村がチャハティ(Chakhati/ჭახათი)。
この小さな村から黒海沿いのコブレティとを結ぶマルシュルートカが1日4往復運行しています。
バフマロ~ゴミスムタ間トレッキングの注意点・アドバイス

バフマロ~ゴミスムタ間のトレッキングに挑戦する際は、「ここは大自然が支配する地」ということを理解しておかなければなりません。
いくら綿密に計画しても山の天気は読めませんし、すべてが計画通りに行くわけではないことも承知の上で訪問することになります。
とはいえ、あらかじめ知っておけばどんな状況にも対応ができるというもの。
ここでは、実際にこのコースを歩く人向けに、プランニングに役立つ注意点やアドバイスを解説していきます。
ベストシーズン

一般的にジョージア山岳部のベストシーズンとされるのは、6月~9月の3ヶ月間。
天候が比較的安定している夏場の時期にあたり、美しい風景が見られます。
バフマロ~ゴミスムタのトレッキングに関してはベストシーズンはさらに短く、7月半ば~9月半ばの2か月間ほど。
6月はまだ雪が多く残っていてリスクが大幅に増しますし、9月後半になると夜間はかなり冷え込むためキャンプが難しくなる点が理由です。
のぶよが旅したのは7月前半~半ばにかけてでしたが、残雪の感じなどを見るに「あと1~2週間後くらいがベストかな」といった感想。
気温に関しては特に問題なく、最低気温12℃ほどだったので、テント泊でも寒い思いをすることはありませんでした。
総合的に、残雪リスクが最小限&天候が安定している&夜間でもそこまで冷えないというベストofベストの時期はズバリ8月だと思います。
インフラ

プランニングの際に大切なのが、トレッキングに必要なインフラ面をしっかりと理解しておくこと。
どこで何ができるのかできないのかを知っておくことで、準備を完璧にすることができます。
バフマロ~ゴミスムタ間における各種インフラをまとめると、以下の通りです。▼
・電気:バフマロは問題なし。ゴミスムタは基本的に不通。それ以外のエリアは一切電気なし
・ガス:全域で不通。ガスボンベか薪が使用されている
・水道:問題なし&飲用可。コース上に湧き水多々あり
・ネット:バフマロ/ゴミスムタ共にスマホ回線の電波はかなり貧弱。コース上は基本電波なし
・買い物:バフマロに数軒/ゴミスムタに3軒。それ以外はなし
・飲食店:バフマロに3軒/ゴミスムタに1軒。それ以外はなし
・宿泊:バフマロ/ゴミスムタに宿あり。それ以外にはなし
・ATM:バフマロに1台あるのみ
・カード払い:バフマロとゴミスムタでは意外と対応しているところが多い
こんな感じで、このエリアのインフラの不便さは下界とは比べ物にならないほど。
バフマロやゴミスムタでは最低限のものならまあ購入できますが、それ以外のエリアでは本当に何一つ手に入らないので、準備はぬかりなく!
ネット環境

旅行者にとって最も不便なのが、バフマロ~ゴミスムタ間のトレッキングコース上ではネットの接続ができない場面が多いこと。
ジョージアのスマホ会社最大手のMagtiであれば、バフマロやゴミスムタの村内でネットにつながりますが、それ以外の会社の回線は電波が超絶弱いorまったくつながらないことがほとんどです。
また、バフマロ以外ではそもそも電気が通っていない場合がほとんどである点も要注意。
ある程度の集落であるゴミスムタでさえ基本的に電気は不通なので、電子機器の充電ができないという状況も考えられます。
各民家では夜間の数時間のみラジエーターで自家発電したりしてしのいでいるのですが、発電量にはかなり限りがあるため、大容量のモバイルバッテリーなどを持参するのが安心です。
服装・持ち物

トレッキングの服装に関しては、一般的な山歩きにふさわしいものを用意すればOK。
藪の中などを歩く場面はほぼないので半ズボンでも問題ないですが、メリア・ケリ村やハベラシュヴィレビ村などアジャラ地方に属する山村は住人の大半がイスラム教徒であるため、半ズボンやタンクトップなど露出の多い服装が厭われる点にも注意しましょう。
持ち物に関しても一般的な山歩きを想定して準備すればOKなのですが、キャンプ泊があるため自炊できる環境が作れれば便利。
コース上にはゴミ箱等はないため、自分の出したゴミを持ち帰るためのビニール袋などもお忘れなく。
野生動物

今回紹介しているコースに限らず、山岳地域旅で気になるのが野生動物。
小コーカサス山脈には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、トレッキングコース上には多くの区間が標高2000m以上で森林限界を超えていることもあり、トレッキング中に熊に遭遇するというケースはほぼ考えられません。
野生動物との遭遇リスクが上がるのは夜間となりますが、バフマロやゴミスムタ、メリア・ケリ村など人が住んでいる場所周辺であればリスクは限りなくゼロに近いです。
ジュワリミンドリなど基本的に無人のエリアに関してが怖いですが、昼間にわざわざ野生動物側から出てくるリスクは低い&夜間はコテージ内に泊まれるということで、そこまで恐れることもないでしょう。
また、ジョージア他地域では注意が必要な牧羊犬ですが、このエリアでは基本的に牛の群れを人が放牧しているため、心配は不要。
まれに無人の家畜の群れを犬が率いている場合もありますが、他のコーカサス山岳地域の攻撃的な牧羊犬とは異なり、ハイカーを敵とはみなしていないようです。
おわりに
のぶよの5年間に渡るジョージア滞在の中でも、トップレベルに印象的で素敵な思い出となった、バフマロ~ゴミスムタ間のトレッキング。
正直とっっっても不便ですし、途中でギブアップしようかと思う瞬間もありましたが、それらも含めて良い思い出です。
今回紹介したトレッキングは複数日に渡って山を歩く&キャンプ必須とあって、多くの日本人にとってはハードルが高く感じられるもの。
しかし、実際に歩いた人だけが体験できる極上の風景の数々や、スレていない山の人々の温かさは、きっとジョージアという国に対する感覚を大きく変えてくれるものだと思います。
「歩くのは無理だけど、バフマロやゴミスムタには行きたい!」という人でも楽しめるのがこのエリアの魅力。
プランニングの選択肢は無限大なので、ぜひ自分に合ったスタイルで小コーカサスの隠れた桃源郷を満喫してみてはいかがでしょうか。



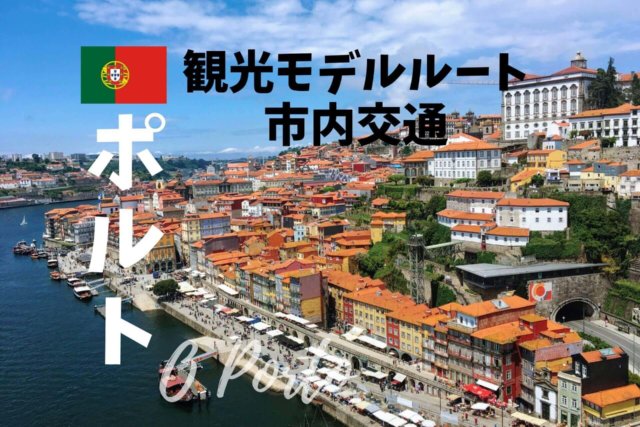










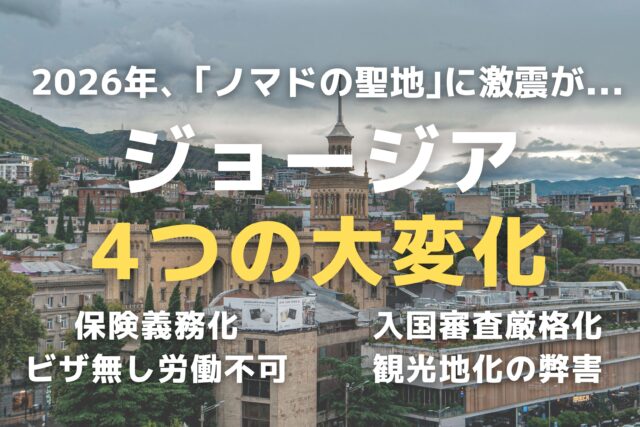



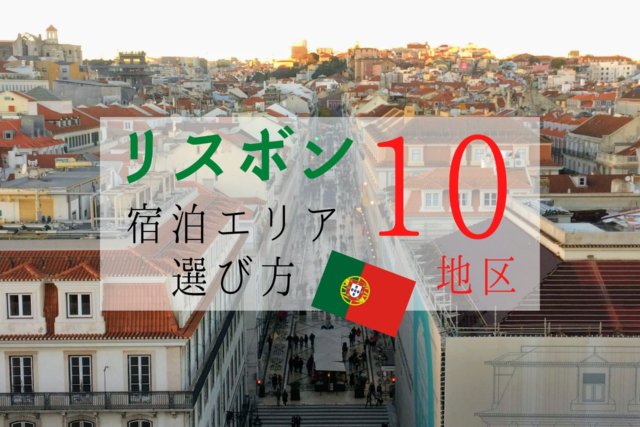

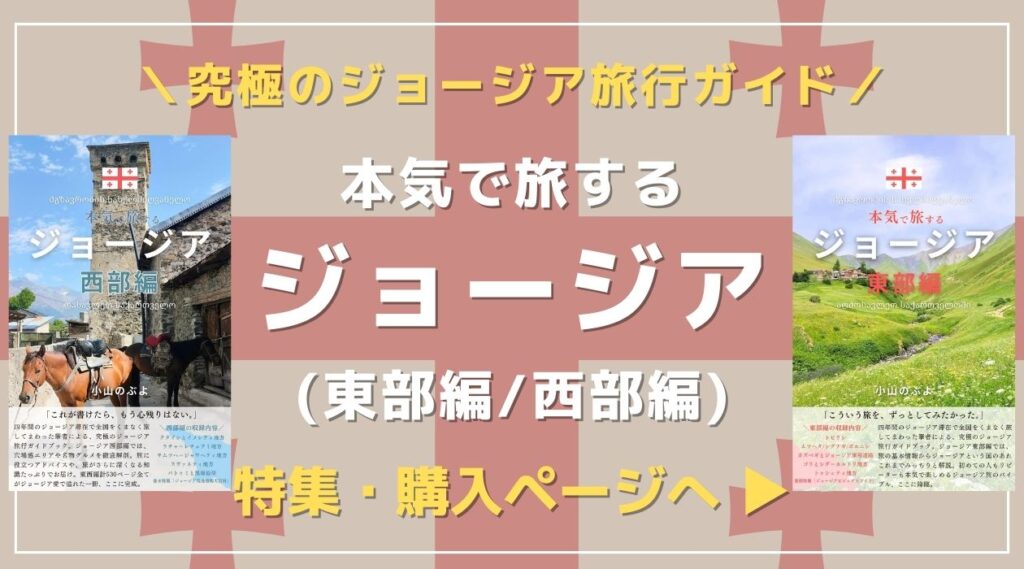


















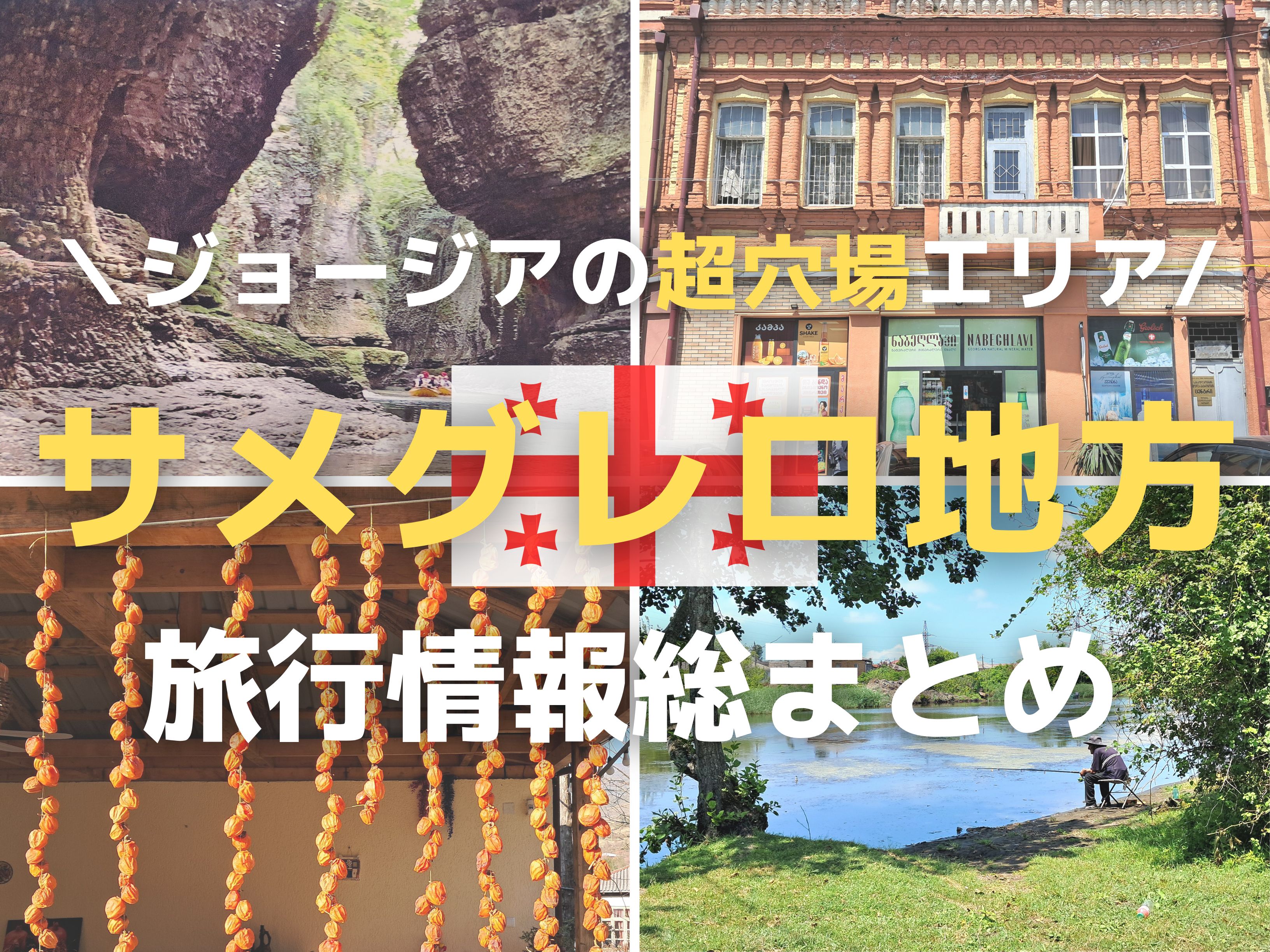




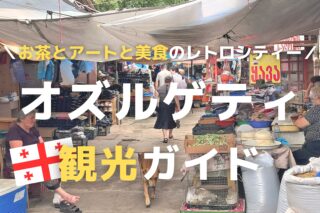

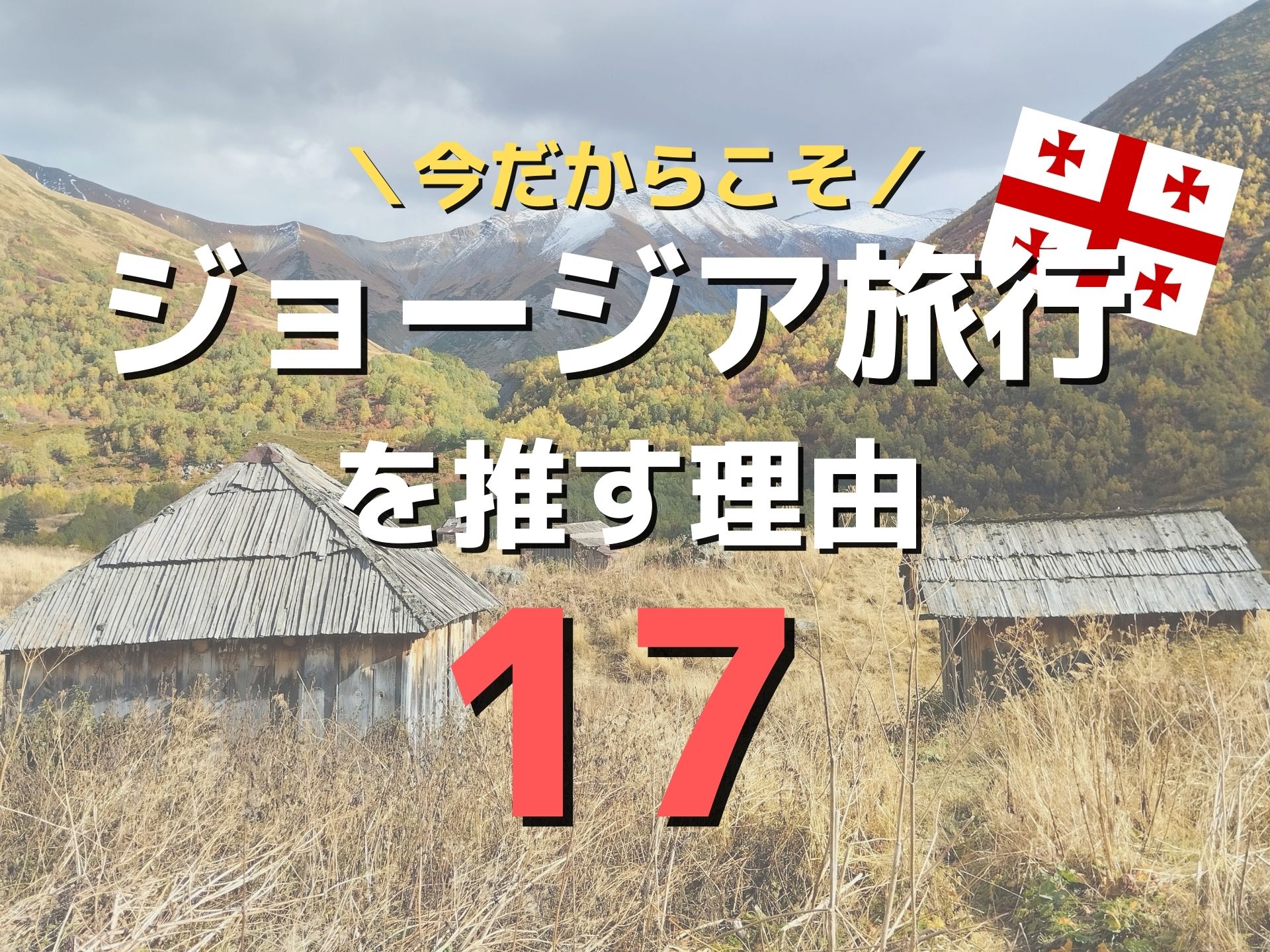
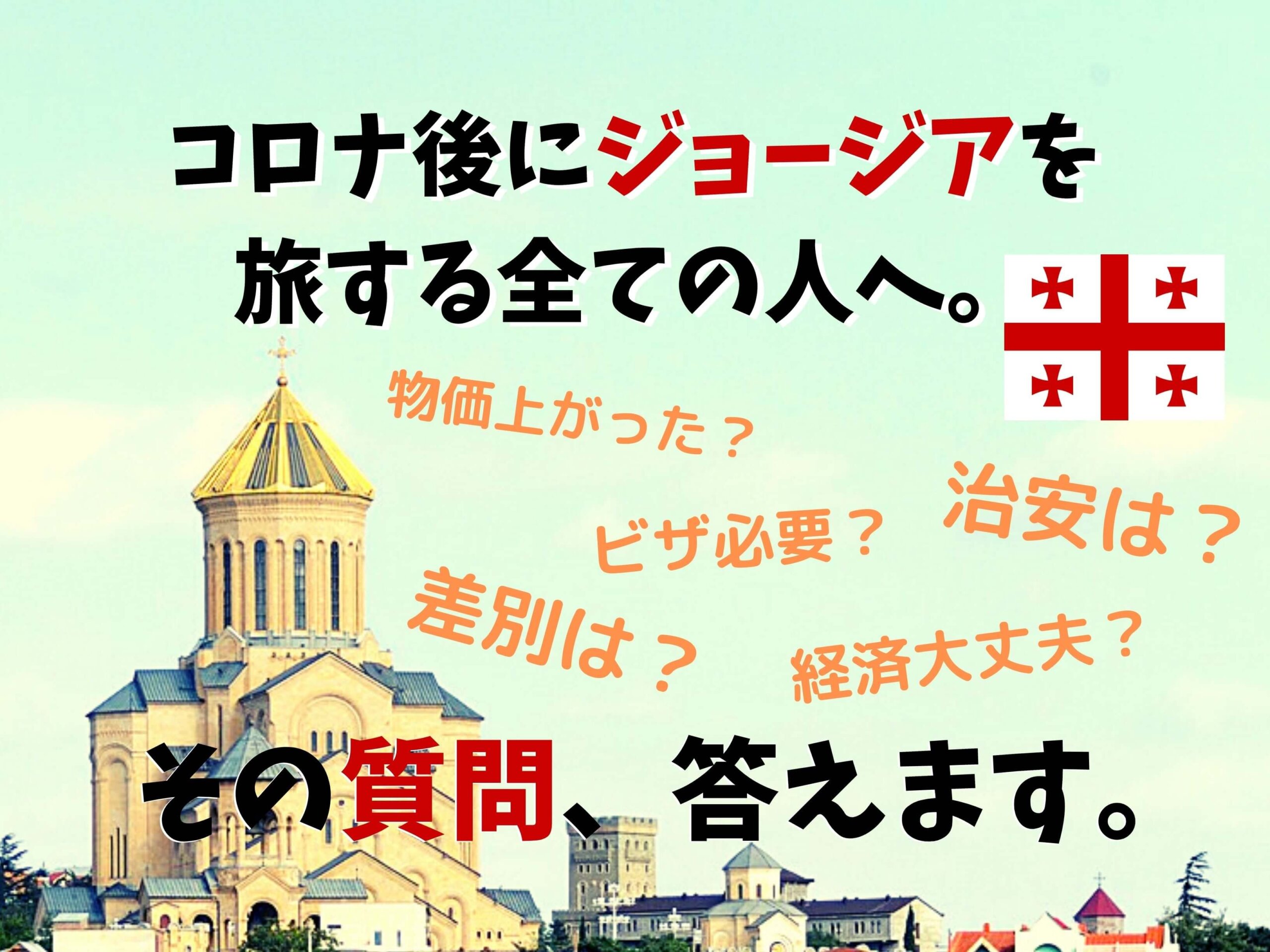

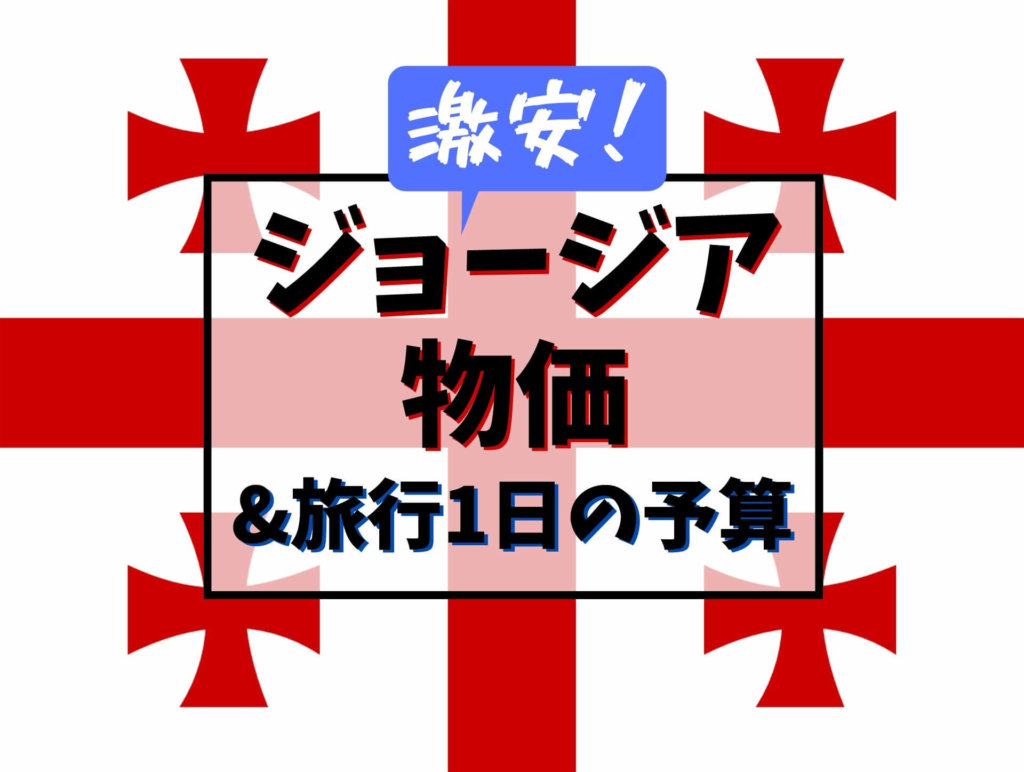




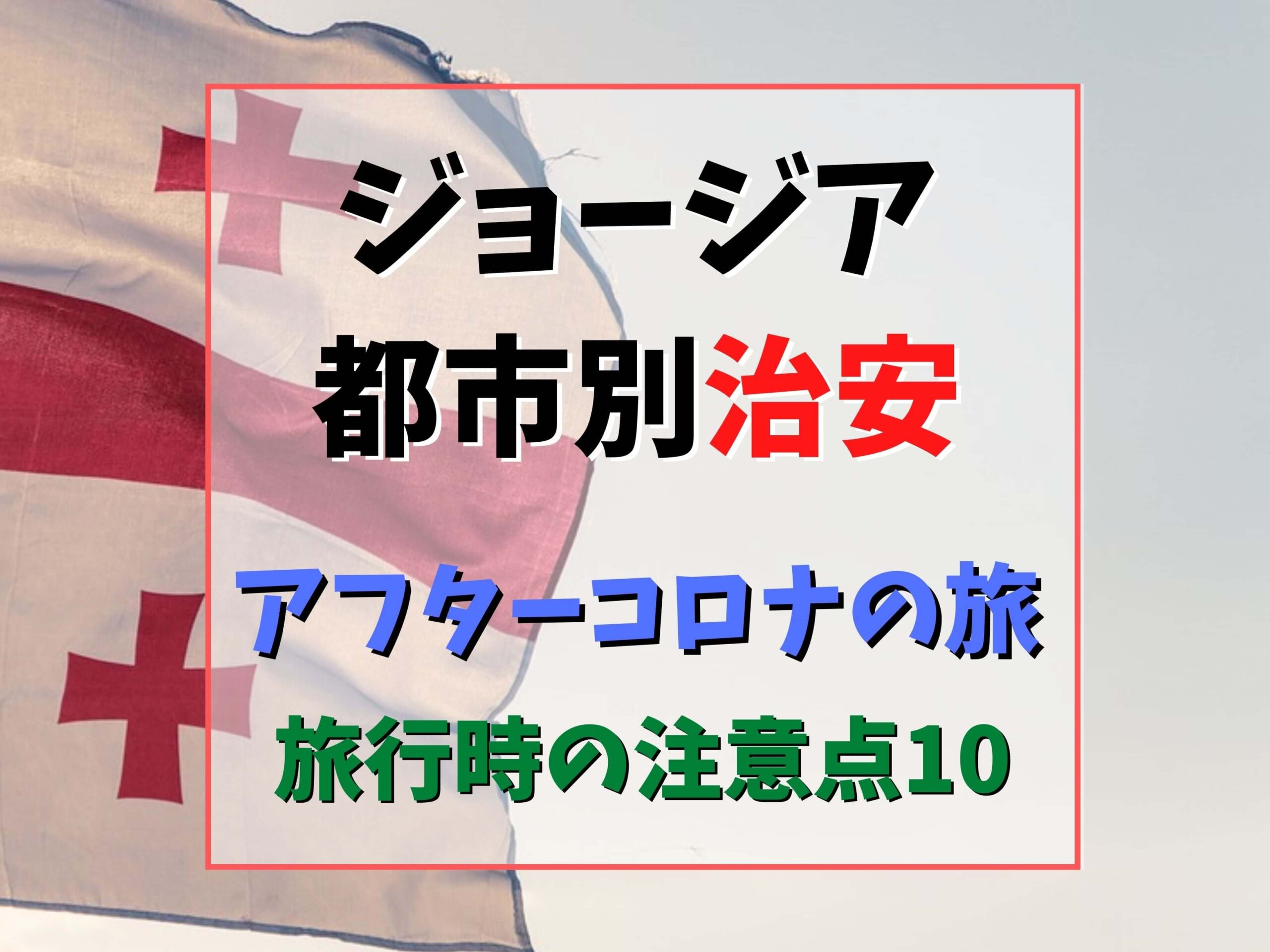
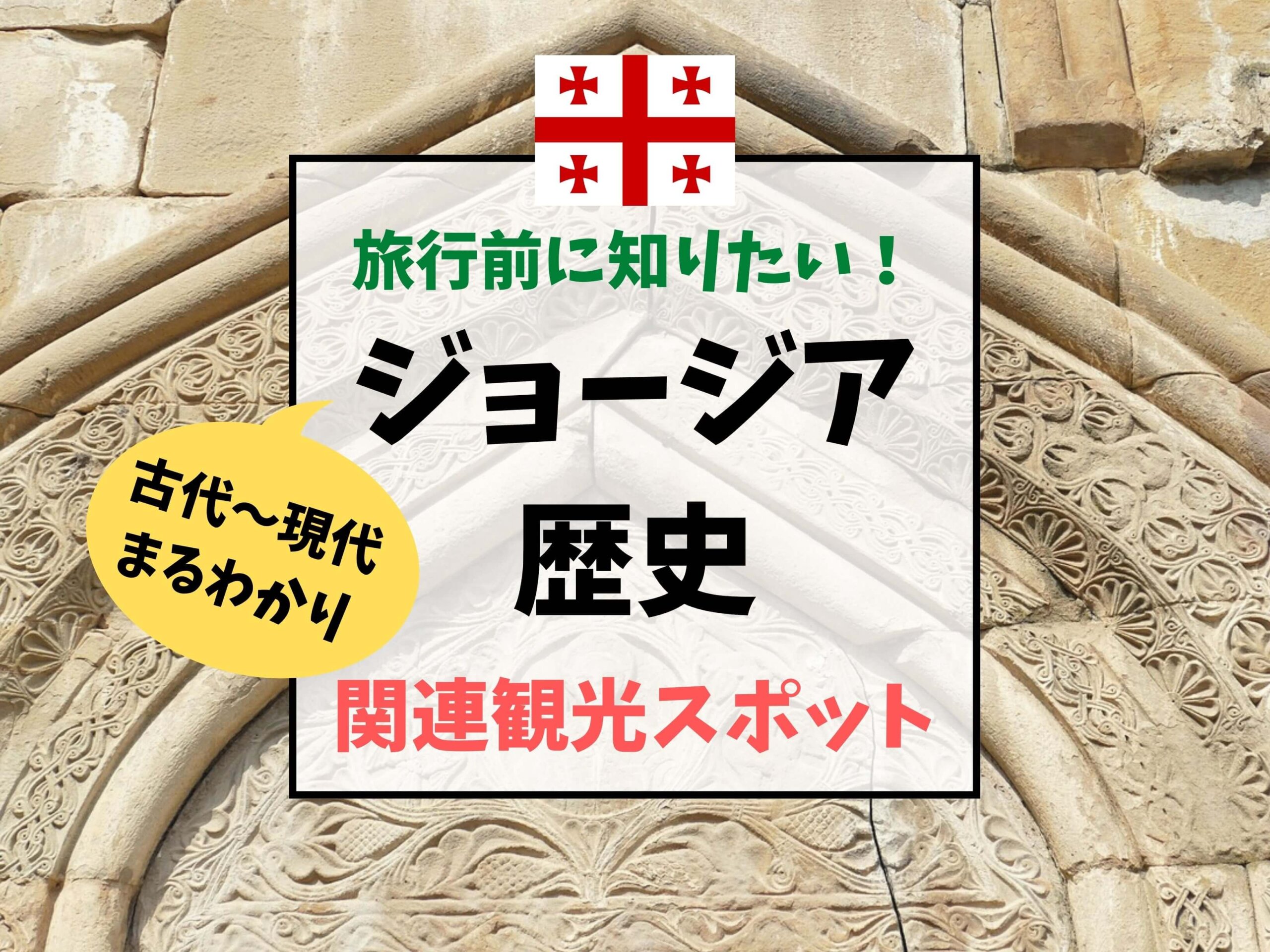


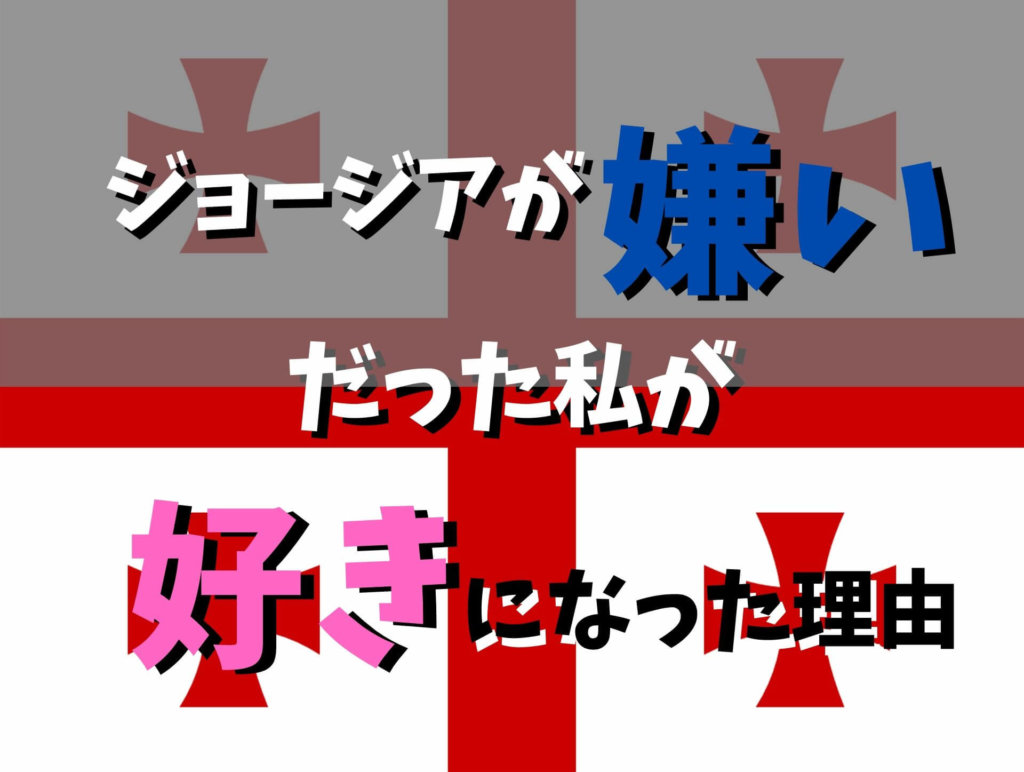



コメント