普段は旅行情報や海外情報を主に発信している当ブログですが、これまでの旅を通して感じたことをフォトエッセイ形式でお届けする新企画が「世界半周エッセイ」。
各国で体験した出来事や、出会った人たちとの思い出がテーマとなっています。

思えばずっと、考えていた。
「どうして今、ジョージアに居るのだろう」
「世界がこんな状況で、これからどうすれば良いのだろう」
元々先のことを色々と計画立てることが苦手で、むしろ、計画に縛られるように生きる人たちを内心蔑んでさえいた。
時は2020年。
世界中に広がったコロナウイルスの猛威は留まることを知らず、滞在中のジョージアも厳しい都市封鎖が2か月ほど続いた。
買い物以外にはほとんど外出しない生活。
それまで1年以上に渡って「行きたいところに行く」スタイルの旅をしてきたこともあって、「どこかに行きたくても行けない」というのは全く新しい経験だったし、そもそも、そうならないような人生を自分で選択してきた。
トビリシの自宅のバルコニーを通した先に広がる青空はあまりに澄み渡っていて、まるで人類を嘲笑っているように思えた。
冬から春になり、初夏のような陽気が続く季節になっても、一度落ち着けてしまった腰を上げるのは簡単ではない。
初夏の段階ではかなり感染が抑えられていたジョージア。
せっかくなので国内を旅しようと思い立つまでには、ロックダウンが明けてから実に2か月ほどの時間を要した。
再び旅に出ようと思い立ってから出発するまでは、さほど時間はかからなかった。
人間、「スイッチ」のようなものがどこかにあって、それをONにすれば良いだけなのだ。
そのスイッチに指がたどり着き、ほんの少しの力を入れてONにするまでが、真っ暗闇の中でスイッチの場所を手探りするようで案外難しいのかもしれない。

とうとうやって来た、旅の再開の日。
これまで散々利用してきた、埃をかぶったミニバス車内の匂いも、狂ったようにスピードを上げる運転手も、車窓を流れていく風景も…なんだか新鮮に感じる。
とはいえ、再び旅ができていることへの感動はない。
むしろ、地方部で差別に遭ったり、店や宿の閉鎖によって旅がしにくくなっているのではないか、という不安の方がこの時は大きかった気がする。

トビリシからおよそ3時間でカズベキという山岳エリアの町に到着する。
近年ブームとなりつつあるジョージアの中でも最も有名な山岳リゾートの一つで、アクセスが容易なわりに、コーカサス山脈のダイナミックな景観が見られることで人気が高い。
事前に予約しておいたホステルを探して、山がちなカズベキの町を歩く。
ホステル(他の旅行者と相部屋)も、ゲストハウス(個室)もほとんど料金が変わらないにもかかわらず、あえてホステルの宿泊を選んだのは、自分と同じ境遇の旅行者に出会えることを期待していたからかもしれない。
いや、ロックダウンが始まって数か月間、ほとんど他人と顔を合わせたり会話を交わすことがなかった孤独な日々への反動だったのだろう。

到着したホステルは、普通の民家そのものな佇まい。
老夫婦とその娘が3人で生活している家の2階部分を宿泊客に開放している、ジョージアではよくあるスタイルの宿だ。
他の旅行者に出会えることを期待すると同時に、心のどこかではもう分かっていたのかもしれない。
「他に宿泊客はいない」と、”ナナ”と名乗った娘に告げられたとき、何も驚くことはなかった。
そう言いながらも、(自分では全く意識していなかったが)きっと残念そうな顔をしていたのだろう。
いや、もしかしたらこの娘も家族以外の誰かと交流したかったのかもしれない。
彼女はたった一人のゲストをやけに気遣ってくれ、一緒に食事をしたり、ことあるごとに話しかけてくれたりした。

カズベキにやって来て、3日目の夜。
それまでのはっきりしない天気が嘘のように雲が割れ、満天の星空が広がった。
7月とは言え、標高2000m近いカズベキの夜はかなり冷える。
お互いに頭から毛布をかぶって、ナナと一緒にビールを飲みながら、零れ落ちんばかりに爛々と輝く星空を眺めた。
そして、色々なことを話した。
おすすめの見どころやカズベキ地域の伝統文化についてだったり、去年の夏に他の旅行者と一緒にハイキングしたナナの思い出話だったり、彼女の弟の子供がすごく可愛いという自慢話だったり…
気付けば、「これからどこで何をしていけばいいのか分からない」と、この場所に来る前に自分が抱いていた悶々とした気持ちを彼女に打ち明けていた。
いったいどうして友達でもない、むしろ、出会ってまだ3日ほどしか経っておらず、英語も微妙にしか通じない彼女にこの話をしようと思ったのかはもう覚えていない。
星空があまりに綺麗だったためか。ビールがまわってきたのか。もしくは、そもそもこの話がしたかったから、雪国で寒さに耐える子供のような恰好でずっと外にいたのか。
こちらが投げかけた言葉の意味を反芻していたのか、それともどう返答すべきか逡巡していたのか。しばし沈黙にひたったあと、彼女はこう言った。
「カズベキの人々は自然の中にいる神の存在を信じているの。あなたが今ここに来ることができたのは、きっと神にあなたの運の良さが認められたから。ほら、世界は今こんな状況だけど、あなたは偶然ジョージアに居たから、今ここに居られてこうして私と話せている。これはきっとあなたが持っている運に違いないの。神が認めた運を持っている人は、何をしようともどこに居ようとも、うまくいかないことなど絶対にありえないのよ。」
正直驚いた。彼女がこんなに長いこと自分の意見を投げかける場面に初めて居合わせたからだ。
それと同時に、「そうか。自分は運が良かったのか。」と、すっと納得できた。
カズベキの人々が信じる「神」とは、町を見下ろすようにそびえたつ国内最高峰のカズベキ山、それ自体なのだそう。

先人たちは、この山を間近に望む最高のロケーションに小さな教会を建てた。
それが、「天国に一番近い教会」なんてキャッチフレーズがつけられた「ゲルゲティの三位一体教会」。
住人達は毎朝、町から教会とその背後に鎮座するカズベキ山を見上げて祈りを捧げるのだという。
こうした情報をたっぷりと与えてくれたあと、ナナは「もう寒いからお先に」と言い残して自室に戻っていった。
一人になり、まるで命あるものの鼓動のように煌めき続ける星たちを見上げながら、「明日、晴れますように」とそっと願って、炭酸が抜けかけた残りのビールを一気に喉に流し込んだ。
翌朝。
いつもは10時くらいまで寝ている、絵に描いたような駄目な旅行者なのに、6時に目が覚める。
夜が明けきっていない薄紫色の町を背に、ひたすらに歩く。
そう、ゲルゲティの教会に向かうのだ。

朝食も食べずに出てきてしまったため、約1時間半ほどの山道は体力的につらい。
登山道からは角度的に目的地の教会は見えないので、どこまで歩いても坂が続くような錯覚にとらわれる。
しかし、丘の上の教会がようやく目に入った瞬間に、それまで考えていたこと全てが吹き飛んだ。

早朝の誰もいない教会は、静寂のみが支配する、まさしく神の住処たるべき姿。
「天国に一番近い」のかどうかは分からないが、こんな感じなら天国だってそんなに悪いもんじゃないのではないか。
しかし、町を出た時にははっきりと見えていたカズベキ山は、たった1時間ちょっとの間に厚い雲に覆われてしまい、その姿は確認できない。

どうやらこの地の神様は、運の良さこそ認めてくれたとは言え、まだ「天国」の素晴らしさをこんな若造に見せる気はさらさらないらしい。
ならいいや。もう少し下界で頑張ってみるから。
ひょっとすると、昨晩この教会の話を出したナナは、何かに迷っている様子の旅行者をこの場所に向かわせて、何かを感じさせたかったのかもしれない。
だとしたら、それも運なのだろうか。

教会から山を下って宿に戻ると、それまで意識すら及んでいなかった空腹に気が付く。
時間はもう正午過ぎ。
キッチンで昼食の準備をしていたナナの「おかえり」と無言で語るような意味ありげな笑顔で迎えられる。
どこに行っていたのか。どうして朝ごはんを食べなかったのか。
彼女は何一つ尋ねてこなかったし、こちらも早朝からの山登りで疲れていたので何も言わなかった。
温かいスープと煮込み料理のお昼ご飯をいただき、いつものように他愛もない話をする。
そう、彼女は知っているのだ。
宗教や文化は違えど、あの教会を訪れた者は、山の神様がくれる何かを心で感じる運命にあることを。
そして気づかぬうちに、自身の幸運を信じられる強さを手にすることを。





















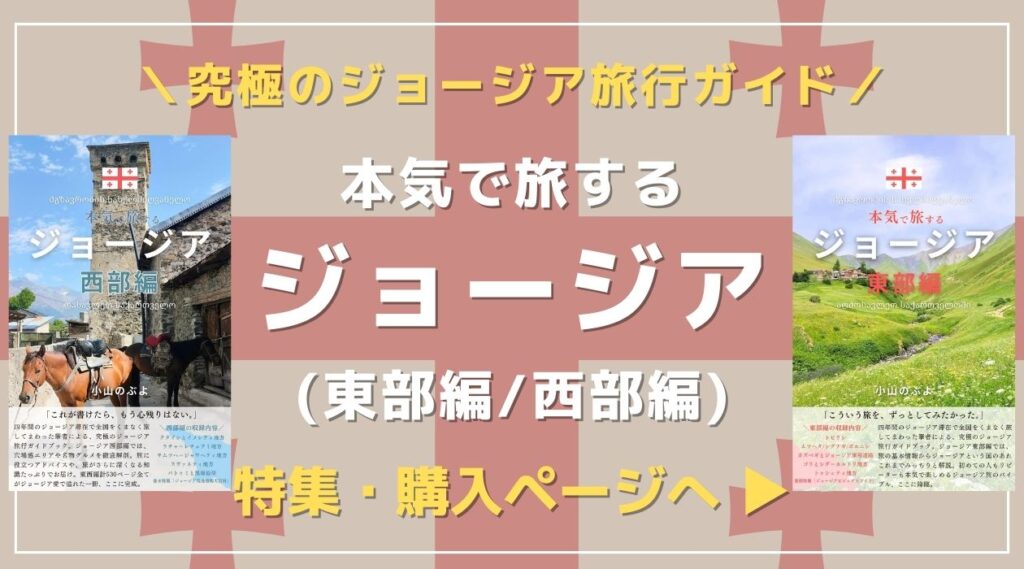



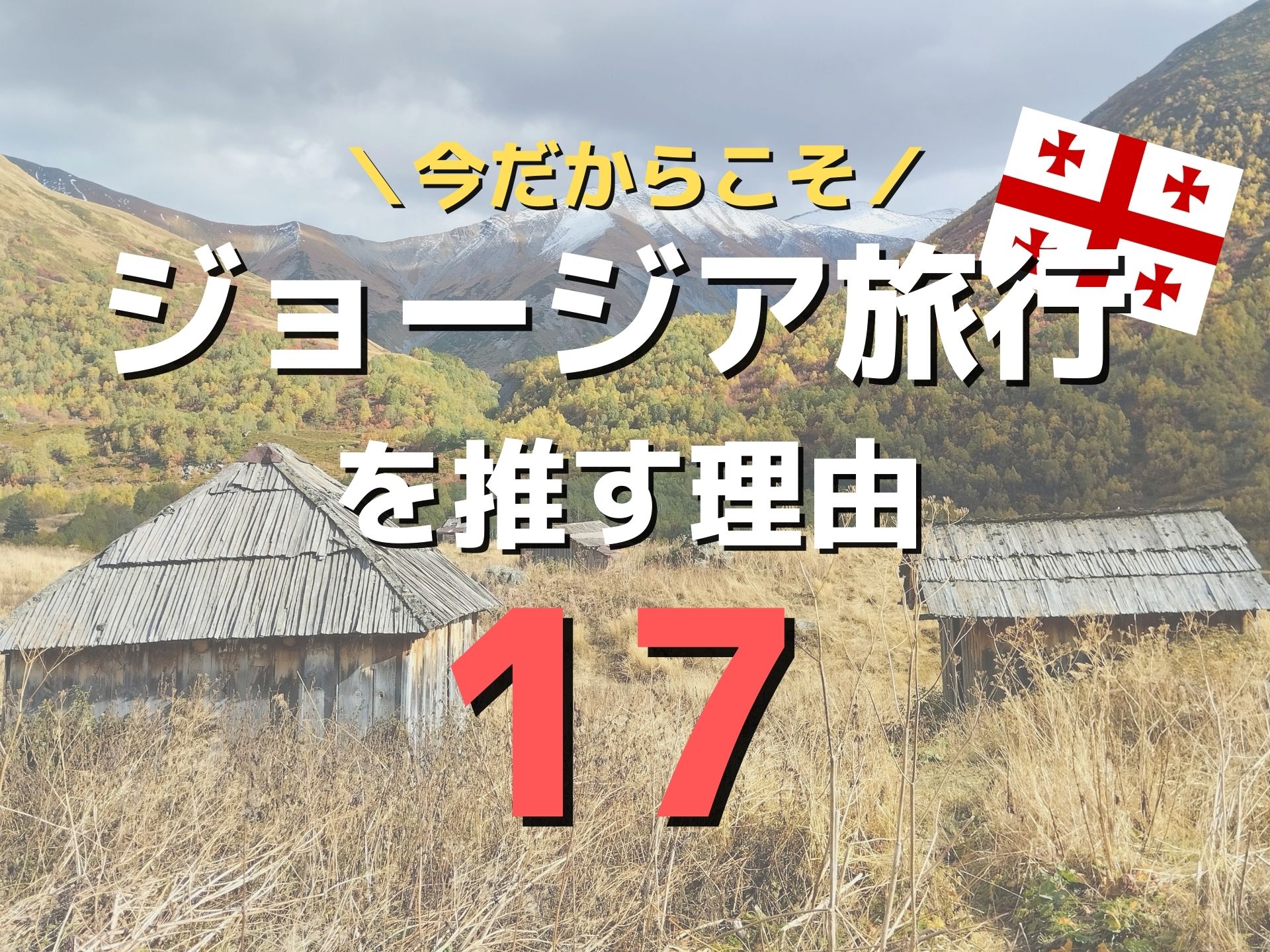







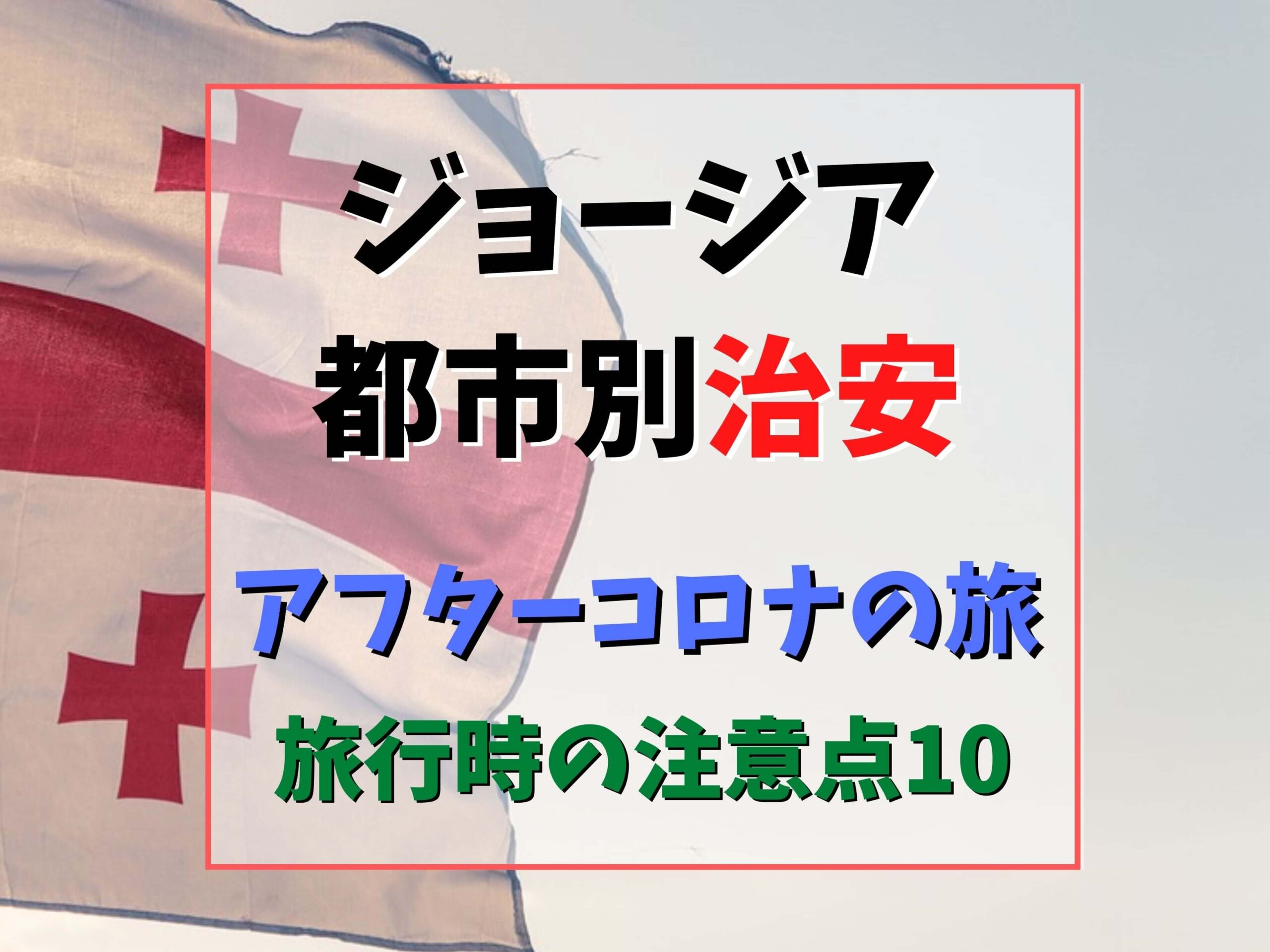







コメント