普段は旅行情報や海外情報を主に発信している当ブログですが、これまでの旅を通して感じたことをフォトエッセイ形式でお届けする新企画が「世界半周エッセイ」。
各国で体験した出来事や出会った人々との思い出がテーマとなっています。

「アジャラ地方の山間部を旅したい。」
ふとそう思ったのは、毎日うだるような暑さの中、何かに憑りつかれたようにビーチに繰り出していたバトゥミでの滞在も、すでに2週間ほど経ったころだった。
ジョージアの南西に位置するアジャラ地方と言えば、青く輝く黒海。
海岸線に面した地域が限られているジョージアという国においては、7月にもなれば海水浴目的の観光客がどっと押し寄せる「夏の首都」のようなエリアだ。
いっぽうで、内陸部には「グリーン・アジャラ」なんて呼ばれるほどに、緑深い山々が連なる山間部が広がり、実はこちらの方がエリア面積の大部分を占める。
しかし、夏はみんな海沿いの開放感に酔いたいのは世界共通。内陸部まで足をのばす旅行者はそう多くはない。
「旅行者が来ない穴場のエリア」と聞くと、自分の足で旅したくなる衝動に駆られる性。
緑の山々とターコイズブルーの清流が織りなすコントラストが美しいミルヴェティ村にわざわざやって来たのは、こうした理由だった。

人口数十人のミルヴェティ村には、この地域の伝統である木造の家々が建ち並ぶ。
一年を通して温暖で湿度が高いため、食料の保存に悩まされたアジャラ地方の先人たちは、風通しが良い木造の高床式倉庫を庭に作った。それが今でも現役で使用されており、この村の風景の一部となっている。
端から端まで歩いても20分ほどで一周できるほどの小さな村。
昔ながらの家々を眺めたり、澄んだ空気を味わいながら散策していると、村で最も立派な高床式倉庫がある家を見つけた。

時間は午後2時頃だっただろうか。
ジリジリと照り付ける夏の太陽光でなかなか上手な写真が撮れず四苦八苦していると、家から女性が出てきて何かを言っている。
ジョージア語なのでほとんどわかるわけもないのだが、「モディ!(おいで)」という単語だけは知っていた。(女性の笑顔で手招きする動作のおかげで理解できたのもあるが)
ジョージア、特に地方部を外国人が訪れると、知らない人の家に招かれることはよくある。
招かれるままに席につくやいなや、自家製のワインや前菜、ケーキなどが次から次へとテーブルに並び、もはやこちらが来ることを予知していたのではないかと勘繰ってしまうことも、よくある。
それはまさに、魔法だ。
ミルヴェティ村のこの家でも、魔法は例外なく発揮され、ワインやチャチャ(蒸留酒)を勧められたと思ったら、ケーキやバトリジャーニ(ナスとくるみの前菜)が姿を現す。
宴が繰り広げられるのは、青々とした木々に囲まれた広い庭の一角にある気持ちの良いテラス。
そこには、赤ん坊を抱いたおじさんが座っていた。
「おじさんの子にしてはちょっと歳が離れすぎているような…」と感じて拙いロシア語で尋ねてみると、やはり子供ではなく孫らしい。
まるでビー玉のようにクリッとした青い目が可愛らしい男の子で、なんと今日がたまたま1歳の誕生日だという。

初めこそ、「ジョージアは好きか?」「ジョージア語は話せるのか」といったお決まりの会話ばかりだったものの、次々に注ぎ足されるワインのおかげもあってか、だんだんと自分たち家族の話やこれまでの人生の話をしてくれる。
コロナウイルスの影響で、おじさんはバトゥミでの仕事を解雇されてこの家に戻ってきたこと。
赤ちゃんのお父さん(おじさんの義理の息子)は、バトゥミでの仕事を休むことができず、子供の誕生日に帰って来られないこと。
この家は、先祖代々受け継がれてきた大切な宝物だということ。
先が見えない状況だからこそ、赤ちゃんの誕生日は大切に祝ってあげたいということ。
ジョージアのこんな山奥の村にまで、コロナウイルスは大きな影響を及ぼしている。
しかし、「どうしようもないことを、どうにかしようとしても仕方がない」と笑い飛ばすおじさんと家族みんなは、客人がいるから明るく振舞っているだけなのかもしれないが、あくまでも前向きに日々を暮らしているように見えた。
ちょっと高床式倉庫を近くで見ようと立ち寄っただけのつもりが、気づけば2時間以上も滞在していた。
そんな午後の柔らかな日差しに包まれながらの宴も終盤にさしかかったころ。
「この子の初めての誕生日にお前がここに来たのは、偶然ではない。きっと神がそうさせたのだ。」
とやや怪しい呂律で二度、三度繰り返しながら、ペットボトルに詰めた自家製ワインとおばさん手作りの焼きたてハチャプリ(チーズ入りパン)をお土産にくれる。
もちろん後からお金を請求してくることなどないし、好意をお金で返そうとするのもこの国では無粋であることは知っているから、素直に受け取って礼を言い、家を後にすることにした。

帰りのバスの中、だんだんと遠ざかっていく村の美しい風景を埃をかぶったバスの車窓越しに眺めながら、お土産にもらったハチャプリを食べる。
人間、感傷的な気持ちになろうとも味覚は変わらないようで、いつも通りしょっぱくて、ずっしりと腹にたまる。いわば、どこの家庭でも食べられる、なんの変哲も飾り気もない至って普通のハチャプリ。
でも、あの家の窯で焼かれていたときの熱がまだ少し残っていて、なぜか心がふんわりと温かくなった。
同時に、人生初の誕生日という節目に、変な外国人がふらりとやって来ては飲むだけ飲んで、発音もめちゃくちゃなジョージア語で「誕生日おめでとう」とだけ言って去っていったことを、彼が大きくなってから笑い話にでもして伝えてあげてほしいな。と、静かに願った。


















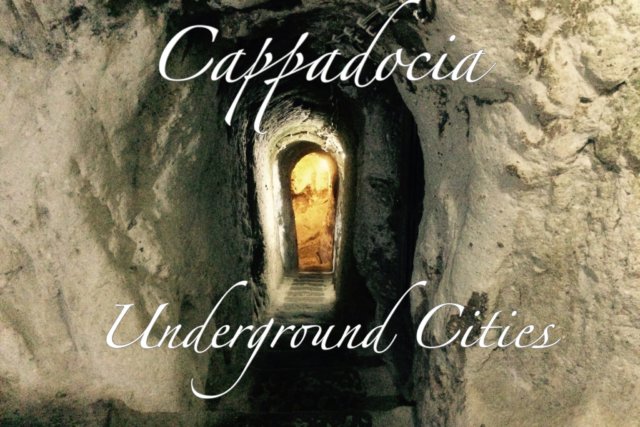






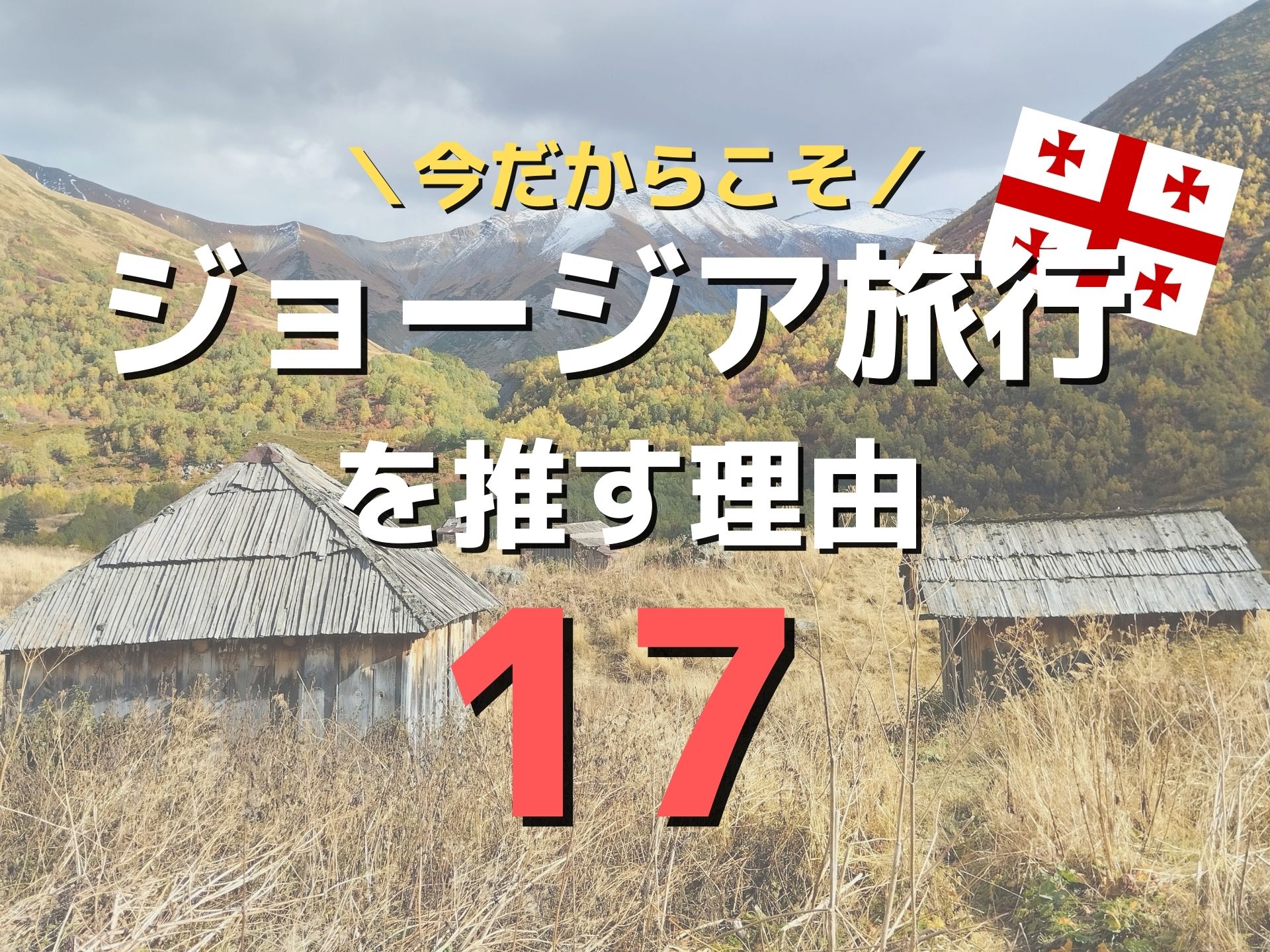







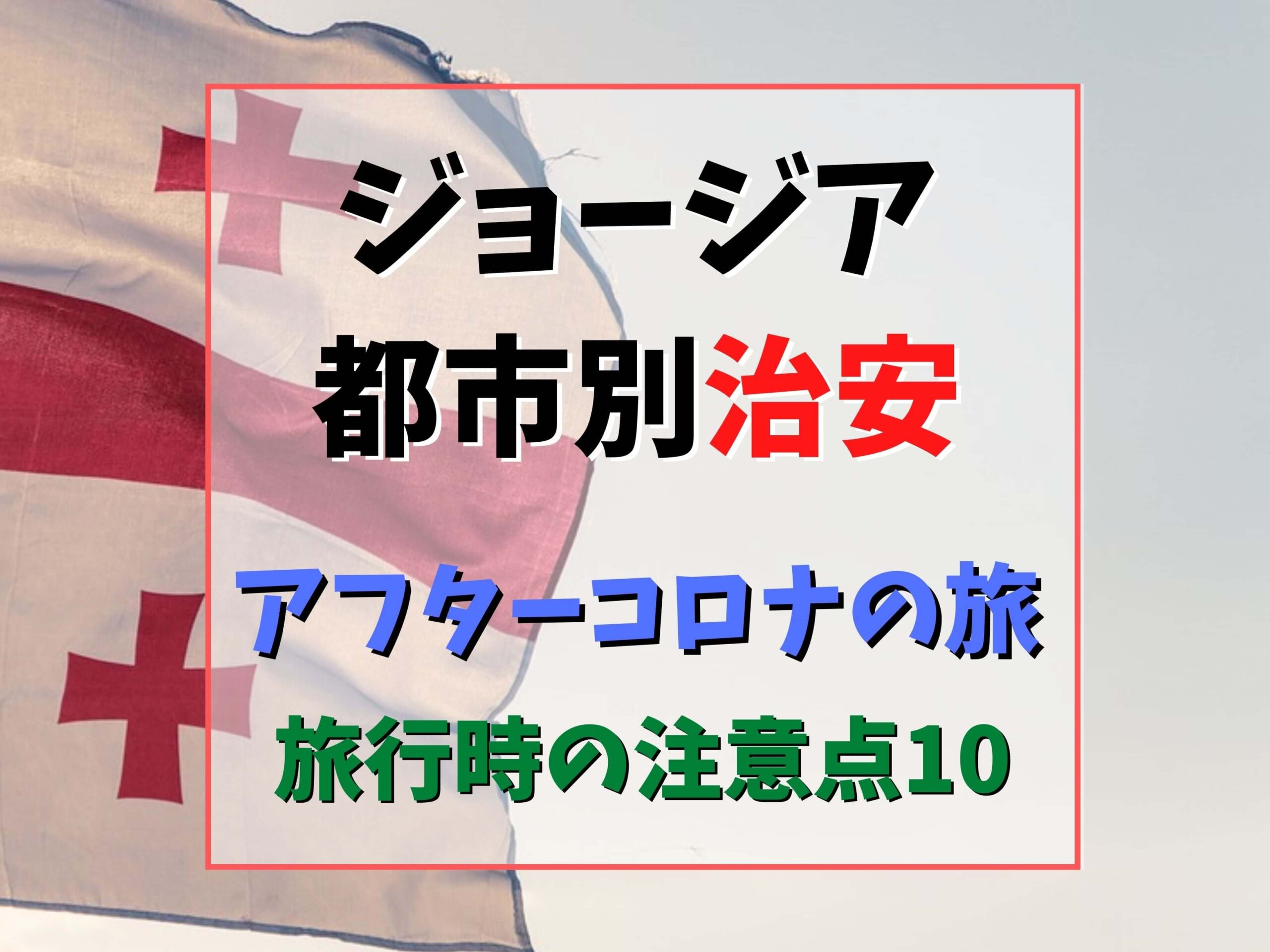








コメント