モルドバの首都・キシナウの喧騒に満ちあふれたバスステーションを出発し、もはやモルドバ名物と言っても過言ではないボッコボコ(「ボコボコ」ではなく「ボッコボコ」)の道を走ること1時間ほど。
乗客の乗り心地など知ったこっちゃないとばかりに爆走していた満員の16人乗りマルシュルートカが、すうっと減速しはじめて、ついに完全に停車した。
「国境」に差し掛かったのだ。
地元民はバス内での身分証提示だけで「国境」を簡単に越えられるようだが、外国人はもちろんそうはいかない。
自分ともう一人(パスポートを見るにルーマニア人だった)だけがバスから降ろされ、数十メートル先にある「国境審査場」の建物、というか小屋へと歩かされる。
小屋の中は田舎の公民館によくある会議室のような、こじんまりとした空間。
何の装飾もされておらず殺風景で、色褪せた白い壁が寂しい雰囲気を演出している。
対応してくれた審査官は、自分と歳もさほど変わらないであろう若い女性だった。

ロシア語訛りが強い英語で、「入国」用の書類に記載する事柄をひとつひとつ指示してくる。(とは言っても””Name!”とか”Birthday!”とか単語単語で)
書類への記載が終わると、「パスポートをコピーしてくるわ」と言い、にっこりと微笑んで席を立つ審査官。
数年前にモルドバから沿ドニエストルに渡航したという人が「賄賂を請求された」なんて言っていたものだから、はじめは若い女性とスマイルで油断させておいて、後から強面の上司でも連れて来られて財布の中身をすっからかんにされるんじゃないか…?なんて身構えていた。
30秒ほどの待ち時間の後に再度、同じ女性が姿を現す。強面の上司は…連れて来ていないようだ。
パスポートに一枚のペラペラな紙を挟んだ状態のものをやおら手渡しながら、彼女は、語尾に「!」を3つくらい付けたような調子でこう言った。
「ウェルカム!!!」
それも、とびっきりの笑顔で。

沿ドニエストル共和国。
その名の通り、モルドバの国土の東部を流れるドニエストル川に沿って広がる細長い地域は、国際的にはモルドバの一部とされているが、住民の大半はロシア語話者だ。
この小さな地域は、ソ連崩壊後のいざこざや戦争によって、モルドバから事実上独立したような立ち位置にある。
モルドバ領内にありながらモルドバ語は通じず、独自の「政府」を有し、独自通貨である「沿ドニエストル・ルーブル」が使用される。
それだけではなく、「ソ連の正当な後継者」を自称し、ロシアを後ろ盾としてヨーロッパ寄りの政策を目指すモルドバ本国からの独立を勝手に掲げている。
ひとつの国として事実上機能している状態であるのに、国際的には国として認められていない。
国際的にはあくまでもモルドバの一部という扱いなので、地図には載っていない。
沿ドニエストルのように複雑な事情が根付く地域は、一般的に「未承認国家」と呼ばれる。
…なんとも怪しい香りがするではないか。

こういった地域に足を踏み入れるのは人生で初めてだったこともあって、普段の国境越えに比べてとても緊張していた。
だからこそ、総じて不愛想なことが多い国境審査官による「ウェルカム!!!」には驚いた。
ソ連の正当な後継者を名乗る「国」の人のイメージとは180°異なっていたからだ。

沿ドニエストル側に無事入り、最初に到着したのがベンデルの町だった。
良い意味で予想を裏切られた「ウェルカム!!!」とは異なり、その町並みに対する第一印象は、何となく頭の中でイメージしていた沿ドニエストルそのままだった。
ひとことで言うと、数十年前から時が止まっているかのような、死にかけている町のような、そんな雰囲気に思えた。


まずは、両替をしなければならない。
先述の通り、沿ドニエストル共和国内ではモルドバの通貨であるモルドバ・レイは使用できず、独自通貨である沿ドニエストル・ルーブルが流通している。
国際的には独立国家だと認められていない地域の通貨であるため、沿ドニエストル内でしか両替ができず、ATMで引き出すこともできない。
この小さな「国」をいちど出てしまえば、沿ドニエストル・ルーブルをどれだけ持っていようが、ただの紙切れと化してしまうのだ。
何の下調べも事前知識もないままに訪れたので、両替所がどこにあるのか見当もつかない。
廃墟と化したバスステーション内にはもちろん、周りにも店の一軒もなく人影もない。ここには両替できる場所など絶対にないだろう。
途方に暮れていると、一人の男性が近寄って来て何やらロシア語で話しかけてくる。
とにかくお金を両替したいことを伝えると、「ついて来い」というアクションをする。
一瞬、警戒心が先行したが、そもそも現金がなければどうにもならないので、ついて行くことにした。
いっさい活気のない共同住宅に挟まれたボコボコの歩道を歩くこと3分ほど。
電器屋のようなたたずまいの小さな店に案内された。

「この店の客引きか?」と男を訝しむも、明らかな外国人が沿ドニエストルの電器屋で電化製品を買うわけなどないことは自明であろう。
男に連れられて店の奥に入っていくと、小さな両替コーナーがあった。
ようやく目的の両替所にたどり着いて安堵の表情をした外国人を見届けた男は、特に何を言うでもなく満足そうな笑顔を見せて去って行った。お礼を言う暇さえないほどに、颯爽と。

10ユーロ分だけ両替を済ませ、退廃的な雰囲気に満ち溢れたベンデルの町を散策したり、町の最大の見どころである要塞を見学したりした。
次は、沿ドニエストルの「首都」ティラスポリへと向かうときだ。
ベンデル~ティラスポリには路線バスが走っているという話は聞いていたのだが、どこからどのバスに乗れば良いのか見当もつかない。
「バスステーションに行けばティラスポリ行きが簡単に見つかるだろう」と高をくくっていたが、どうやらベンデルのバスステーションからはティラスポリ行きのバスはないらしい。
数人に尋ねて教えてもらった場所は、バスステーションから1km近く離れたベンデルの中心街だった。
そこには、キリル文字で「ティラスポリ」と書かれたミニバスが停車していた。

車内に外国人はもちろん自分一人だけ。怪訝な顔をされると思っていたら、やたらと笑顔の運転手に迎え入れられ、他の乗客も交えてのお決まりの質問攻めタイム(どこから来たのか、なんで来たのか、ベンデルは美しいだろう、etc)となる。
車窓からの眺めを楽しむ余裕すらないほどの質問攻め&謎の爆笑タイムが数十分続き、ようやくティラスポリに到着した。
バスステーションに到着するのかと思いきや、ボロボロの集合住宅が建ち並ぶ住宅街のような場所で停車し、「ここで降りて観光案内所に行け」と笑顔で言ってくる運転手。(と、「そうだそうだ!ここで降りなさい!」と一斉唱和する乗客たち)
何かの聞き間違いかと思ったが、確かに「観光案内所」と言っている。

沿ドニエストルほど、観光案内所のイメージとかけ離れた場所が他にあるだろうか。
そもそも観光客の数が限られているモルドバという国の中にあり、モルドバ本国よりもさらに訪れる人が少ない未承認国家なのだから。
しかし、運転手の放った言葉は間違いでもなんでもなかった。
ちゃんと観光案内所が存在していたのだ。

中に居たのは若い女性が一人だけ。
これまでのロシア語オンリーな環境が嘘のように、流暢な英語ととびきりの笑顔で出迎えてくれる。
以前は「国家機密」として発行が許されていなかったらしい沿ドニエストルの地図を手渡され、英語で書かれたティラスポリの市内観光マップに色々と印をつけながら見どころを教えてくれる。

第一声の”Hello!!!”から最後の”Have a great day!!!”まで、驚くほどに感じの良い笑顔と元気で対応してくれたお姉さん。この国には語尾に「!」を3つつけて挨拶するルールでもあるのだろうか。
外まで見送ってくれたお姉さんに別れを告げ、マップ上に印をつけてもらった通りにティラスポリの町を歩きはじめる。


さすがは「ソ連の正当な後継者」を自称しているだけあって、レーニン像やボロボロの共同住宅、鎌とハンマーをかたどった国旗や紋章が至る所に見られる。
ひとことで言うなら、異空間だ。

町のメインストリートには人影はまばらで、走っている車やバスもソ連時代の古いものが目立つ。
自分が生まれる前に存在していたソ連という国では当たり前だったであろう光景が、30年経った現在でもそのまま、目の前に広がっているのだ。

無機質で寂しい雰囲気に支配された街を散策していると、徐々に空腹を感じる。
外食をする文化に乏しいのだろうか。ローカルの人が行くような雰囲気のレストランを探しはじめたのだが、一向に見つからない。(観光案内所で尋ねておくべきだった…)
メインストリートを行ったり来たりし、裏道に迷ったりしながらようやく見つけた一軒の食堂は、明かりがついていなかったが、営業はしているようだ。
中に入ると、調理係のおばちゃんたちがお喋りしていた。

「メニューはありますか?」と尋ねると、首を横に振りながら「何が食べたいの?」と言うおばちゃん(満面の笑顔でなんだか楽しそう)。
沿ドニエストルにどんな料理があるのか全く知識がなかったので、知っているロシア語の食材名を思いつくままに適当に伝えた。(肉、じゃがいも、スープとかそんな感じだったと思う)
しばらくして運ばれてきたのは、おばちゃん曰く「ボルシチ」だというスープと、肉じゃがのような煮込み料理だった(料理名を尋ねたが聞き取れなかった)。


「ボルシチ」は、ロシアやウクライナで食べたような真っ赤な色のものではなく、澄んだ色のブイヨンに野菜とハーブがたっぷり入ったもの。
「肉じゃが」は、豚肉とじゃがいもをメインにハーブをふんだんに使った、見た目にも美しいものだった。
ひと口食べてみて、衝撃が走った。
信じられないほどに、素材の味が濃い。
ボルシチも肉じゃがも、あっさりしていながらも旨味がじわりと口の中に広がる。とにかく絶品だった。
モルドバの料理はどれも、一から手作りされてじっくりと調理されるスローフードが基本だ。
この食堂の料理も、時間をかけて調理されたのが味覚で感じられるほどに、手間暇かけて作られたものに違いなかった。
しかし、モルドバの食文化そのままというわけではない。
ハーブの使い方や味付けなどに、目と鼻の先にあるウクライナの食文化のエッセンスも感じられる。
二つの国に挟まれた沿ドニエストルという地域独自の食文化が、この器の中に詰まっていた。
さっきまで楽しそうにお喋りしていたおばちゃんたちは、ふらりとやってきた外国人がどんな反応をするのか興味津々のよう。
「オーチン・フクースナ(とても美味しい)!」と言うと、皆ぱあっと笑顔になり、お決まりの質問攻めタイムのはじまりはじまり。
ベンデルからティラスポリに移動した際のミニバス車内とほぼ同じ内容の質問だったが(というか、自分のロシア語レベル的にちゃんと聞き取れる&答えられる質問が限られていたからかもしれない)、この食堂ではやたらと「クラシーヴィー(恰好良い)」とベタ褒めされたことが印象的だった。
…もしかしたら沿ドニエストル受けする顔面なのかもしれない。

美味しい料理に大満足し(しかも恐ろしいほどに安かった)、終始笑顔だったおばちゃんたちにお礼を言って、ティラスポリの街を再び歩く。
お腹が満たされたからなのか、これまでにたくさんの笑顔に触れたからなのか、それとも西日が良い感じに街を照らしていたからなのか、理由はもう覚えていない。
先ほどまで無機質にしか見えていなかった町並みが、なんだか生き生きと輝いているように感じられた。

沿ドニエストルの名前の由来ともなっているドニエストル川沿いには、釣りを楽しむおじさん軍団とお喋りに興じる若者たちの姿がちらほらと見える。
みんな、楽しそうだ。
川のすぐそばにどんと構える戦車のモニュメントが何かのフェイクに思えるほどに、ただただ平和な光景だった。

最終バスを逃さないように、ティラスポリからモルドバ本国に戻るミニバス発着ポイントの鉄道駅へと向かう。
乗車ポイントを教えてくれた鉄道駅のお姉さんも、親切すぎるくらいに丁寧だった。もちろん、この人の笑顔もまぶしい。

国際的に国として認められていようがいまいが、ソ連の継承者を名乗っていようが、きな臭いイメージを持たれていようが、そんなことは外から見た人間のいち視点に基づく判断に過ぎないのかもしれない。
「地図に載っていない国」にも人々の生活はちゃんと存在しており、どうにかこうにか社会が回っていて、みんなそれなりに楽しく暮らしているのだ。
この地で出会った人々の笑顔が、それを象徴しているように思えてならない。

見知らぬ土地でここまで多くの人々の笑顔に触れた日は、それ以前もそれ以降もあの一日以外にはない。
あの食堂で偶然食べた「沿ドニエストル風肉じゃが」は、あれから3年の時が経とうとも「これまで食べた中で最も美味しかった料理」の地位を簡単に譲る気配はなさそうだ。
人間の記憶とは不思議なもので、笑顔が印象的だった人々の風貌や良くしてもらった思い出、楽しかった会話の内容なんかは、時が経とうとも鮮明に思い出すことができる。特に一緒に写真を撮ったわけでもないのに。
そういう意味では、地図にすら載っていない沿ドニエストルのイメージは、ソ連でも戦車でもボロボロの共同住宅でもない。そこにあったのは、人々の笑顔だった。
政治的な目論みがどうだとか、国際的にはどこの領土でどうだとか、そんなの知ったこっちゃない。
あの日、あの町で出会った人たちの素敵な笑顔が絶やされてしまう事態にならないよう、ただ平和な時間がこれからも流れていてほしい。
それこそ、あの日の夕暮れ時に見たドニエストル川沿いの風景のように。




















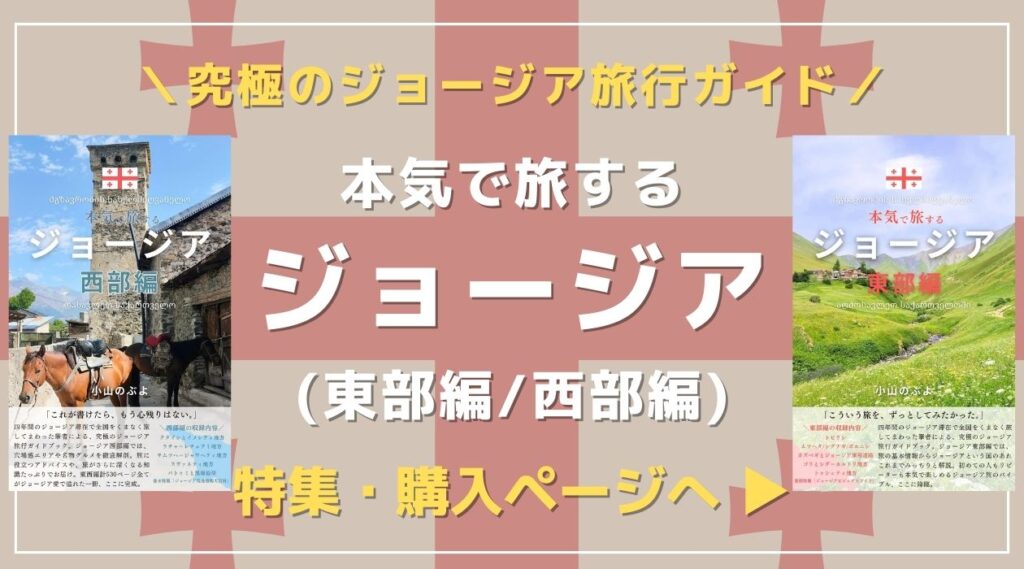






コメント