バトゥミの朝は、遅い。
見慣れたストリートは静まり返り、時々車が通るだけ。まるで町全体が昨晩の二日酔いを引きずっているかのように、気だるい雰囲気が湿った空気とともに辺りを覆う。

十時を過ぎてしばらく経つ頃、ようやくこの町は動き出す。
町工場が連なる昔ながらのストリートには、コーヒーを飲みながら談笑する人々や物売りが現れ出し、パン屋からはグヴェゼリ(具入り揚げパン)やハチャプリ(チーズ入りパン)を焼く香ばしいにおいが漂う。そんなローカル感を絵に描いたような風景の中、ビーチへと向かう様子の外国人旅行者の姿がちらほら。
なんだかちぐはぐに感じられるけれど、これが八月のバトゥミの毎朝の光景だ。

八月のバトゥミは暑い。じめりと肌に纏わりつくような湿度と、それを応援するかのように降り注ぐ太陽光は、どこか日本の夏に似ている。
こうも朝から晩まで蒸し暑いと、自分で食材を買って何かを調理して…という一連の行為がひどく面倒に思えてしまう。しかし、腹は減る。
そういうわけで、夏の虫が灯りに誘われるように、ふらふらと宿の近くの気に入りの食堂に吸い込まれる。
商売っ気はまったくないこの店。愛想の良い女店主はいつも、外の椅子でぐだあ〜っと溶けている。
しかし、味は良い。もちろんビールだってキンキンに冷えている。

自転車に乗る練習をする小さな子供たち。ものすごい手速さでバックギャモン遊びに勤しむおじさんたち。大声で子どもを叱りつけるおばさん…
いつもと何一つ変わらぬ音や光景を、感じる。
この食堂でよく注文するオジャフリ(豚肉とポテトのグリル)も、相変わらず完璧な味だった。
いつもと何も変わらない、八月のバトゥミの朝。

今年の八月。そのほとんどを、ここバトゥミで過ごしてきた。
旅行というよりも「滞在」という言葉がしっくりくるような日々で、気に入りの食堂でオジャフリを食べ、そのまま海まで散歩し、天気が良かったらそのままビーチに居残って、日が傾いたらビールをプシュッと…
なんの生産性もない、そんな八月。
どこか新しい場所へ行きたいという気持ちはあれど、このある意味「日常」のような日々が過去のものとなってしまうことを厭ってもいる。
「そろそろ次の町に移動しなきゃなあ。」なんて頭の片隅で考えながらも、両足は「日常」に忠実に従おうと動く。

町工場エリアの雑踏を抜け、バトゥミのメインストリートを越えると、旧市街に入る。
町工場エリアの喧騒や古ぼけた雰囲気は、少しずつエキゾチックでレトロな町並みへと変わっていく。
ここがトルコ人街。市内に唯一残る、モスクを中心とした地区だ。

低い木の椅子に座ってお喋りをするおじさんち。シーシャ(水タバコ)が置かれたテーブルがずらりと並ぶストリート。聞こえてくる言語は、ジョージア語でもロシア語でもなく、トルコ語だ。
エキゾチックな空気に包まれ、何やら(トルコ語で)話しかけてくる笑顔のおじさんたちをうまくかわしながら歩を進めていくと、重厚な石造りの建物がぽつりぽつりと現れはじめる。

19世紀後半の瀟洒な石造りの建物が残り、「バトゥミのはじまりの地」らしい威厳が感じられる。何度歩いても絵になる風景の連続だ。

アジアのような、ヨーロッパのような…なんとも言えない雰囲気の中に、ソ連時代そのままの住宅街があり、青い空を背景に色とりどりの洗濯物がはためく。
ちぐはぐで不思議なミクスチャーに満ちた旧市街を抜けると、街路樹がわりの椰子の木の向こうに、いよいよ青い輝きが見えてくる。
黒海だ。

つい2週間前まではギラギラと、それこそ煮えたぎるように照りつけていた太陽。八月も終わりに近づくと、どこか日差しが柔らかくなっていることを感じる。
先週までビーチを埋め尽くしていた観光客の数は少なくなり、爆音で音楽を流していたビーチバーも、今日はどこか慎ましげに見える。
季節は、着実に変わりつつあるのだ。

存分に海を楽しんだ後は、喉が渇く。湿気は朝よりもその存在感を増し、冷たくスッキリした味わいの「何か」を喉にグイッと流し込みたい衝動に駆られる。
海沿いのお洒落な店ではそれなりに値が張るものの、少し歩くだけで安く飲める酒場が見つかるのがバトゥミという町の良いところ。
馴染みの酒場も良いが、新しい店を発掘するのも楽しい。
ビールの値段だけ最初に確認し、地元プライス(2GEL〜2.5GEL)を提示されれば、そこは安く飲み食いできる店だという法則がバトゥミにはある。今日もその法則に間違いはなかった。

少しほろ酔い加減で酒場を出ると、空はもう黄金色からピンク色へと表情を変えつつある。
今日は雲がほとんどない。午後になるとどこからともなく真っ白な雲が現れるバトゥミの八月には、こんな夕暮れ空にはなかなか出会えない。
ビーチに足をのばしてみると、案の定、素晴らしい光景が広がっていた。

黒海に沈む夕日は、とても美しい。
観光客も、地元の家族連れも、釣りをするおじさんも、橙色に染まる世界に顔を上げ、みるみると小さくなっていく太陽の旅を見守る。
その場にいる皆の気持ちが一つになっているような気がして、この時間がとてつもなく好きだ。

太陽が完全に顔を隠し、夜の帳が完全に下りるまでの三十分ほどの短い時間。このときを待っていたとばかりに、バトゥミの海沿いのプロムナードは一気に賑わいはじめる。
海沿いの移動遊園地の軽妙なネオンの光。屋台のアイスクリームをねだる子ども。
どこからともなく続々と、人が集まってくる。
皆、終わりを迎えつつある夏の夕べのひとときを、それぞれのやり方で楽しんでいる。時折やわらかに吹く、かすかな涼しさを帯びた風が、「楽しむなら今のうちだ」と告げているように感じる。

宿に戻れば、お決まりの顔ぶれの宿泊客に、犬と猫がお出迎え。(迷い込んできたのがそのまま飼われることになったのだとか)
日が暮れたあと、街灯の少ないストリートは仄暗い闇に包まれていた。
ビーチパーティーにでも向かうのだろうか。大音量でイケてる風の音楽を流すボロボロの車を運転する若者や、酔っ払った風の観光客が、時折、薄い暗闇を割きながら通り過ぎては、またもとの暗闇がやって来る。
毎晩が熱帯夜そのものの八月のバトゥミは、かなり寝苦しい。子どものとき、エアコンなどなかった実家の寝苦しい夜を思い出す。
「明日は何をしようか。少し早起きして遠出でもしてみようか…」そんなことを考えているうちに、いつの間に眠りに落ちる。
一ヶ月以上なにも変わらない、八月も終わりの一日。

八月が永遠に続けば。
こんな怠惰で、でもどこか居心地の良い、ふわふわとした日々が続いていくのかもしれない。
しかし現実には、九月は容赦なくやってくる。一日ごとに秋の匂いをぷんぷんと漂わせながら。
もしも、昨今の気候変動や天変地異や何らかの魔法や、とにかくそうした要因でたとえこの八月が永遠に続くことがあったとしても、その流れに身を任し続けるわけにはいかない。
なぜなら、旅をしているからだ。
八月の思い出は心に仕舞い込み、いったん別れを告げ、新しい冒険へと踏み出す。
それを九月も十月も十一月も繰り返していくことが旅であり、その永遠にも見えるルーティーンのような生き方を続けているからこそ、後で振り返ったときに、この八月がさらに愛おしく思えるはずだ。
そんなことを思いながら、一ヶ月間ベッドの下に置いたままのバックパックをようやく引っぱり出すことにした。
普段は旅行情報や海外情報を主に発信している当ブログですが、これまでの旅を通して感じたことをフォトエッセイ形式でお届けする新企画が「世界半周エッセイ」。
各国で体験した出来事や、出会った人たちとの思い出がテーマとなっています。




















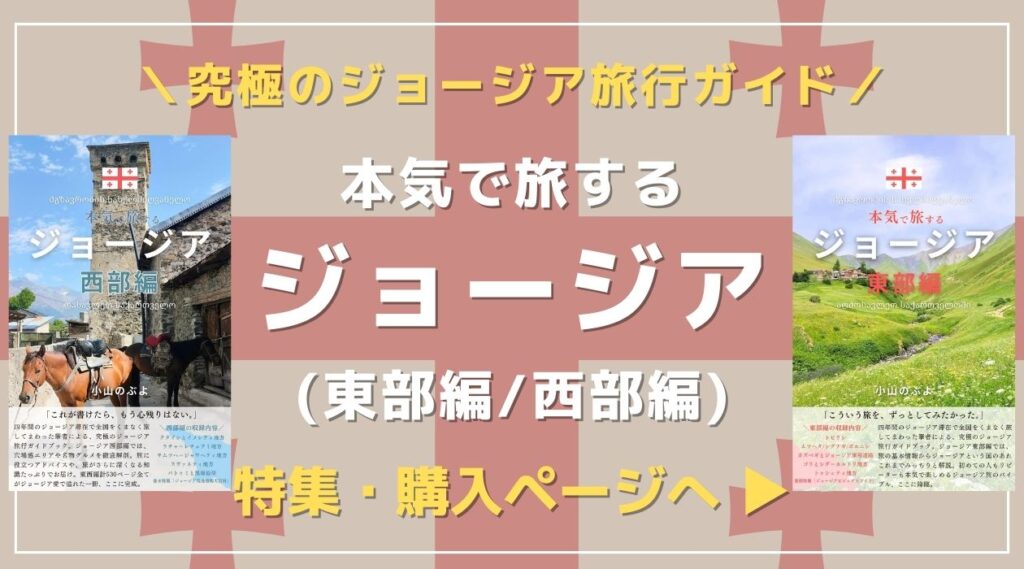


コメント