ウシュグリ村には、結局六日間も滞在することになった。
天気がいまいちパッとしなかった、というのが一番の理由のつもりだった。
でも実際は、時が止まったかのようなこのコーカサスの奥地の村から離れたくない気持ちが、日に日に強まっていったから。それが本音だと思う。

鶏や牛の鳴き声で目覚め、ひょっとしたら数百年前から変わっていない風景をぼうっと眺め、牛糞だらけの小道を歩き、気に入りの食堂やパン屋に立ち寄り、宿に戻る。
たった一日で、秋の気配が色濃く、冬の匂いが少しずつ強まっていくこの村の、風景の中に自分が存在している。それが好きでたまらなかった。
気に入りの場所ができると、どうしても長居してしまいたくなる性だ。予定も期限もない旅をしているからこその、特権かもしれない。
でも、そろそろ行かなきゃな。
再びコーカサスの山へと出発する日のウシュグリの朝は、雲ひとつない青空で、なんだか決心がついたような気がした。

今日歩くのは、ザガリ峠を越える山道だ。
標高2900mほどの場所に位置するザガリ峠。
ウシュグリ村があるゼモ・スヴァネティ地方とクヴェモ・スヴァネティ地方を隔てる場所だ。
いずれもスヴァネティ文化圏に属する地域ではあるが、「ゼモ」は高い、「クヴェモ」は低いの意味だ。その名の通り、二つの地域の標高差は600mから1000mも異なる。
一般的に「スヴァネティ地方」というのは、メスティアやウシュグリなどが位置するゼモ・スヴァネティ地方を指すことが多く、ほぼすべての旅行者はこの地域だけを旅して去る。
いっぽうのクヴェモ・スヴァネティ地方は完全に忘れられた存在と言えるほどにマイナーで、インターネット上にも渡航した人の記録はほぼない。
商店があるのか、宿があるのか、どんな地域なのか…何一つ情報がなく、未知のベールに包まれている。
なんとも、ワクワクするではないか。

荷造りを済ませ、朝の柔らかな日の光を浴びながら、これから歩いていく方角を眺め、胸が高鳴るのを感じる。
情報がないなら、自分の足で歩いて、自分の目で確かめて、自分の心で感じれば良い。旅することなんて、案外とてもシンプルだ。
もう二度と、目にすることがないであろう美しい風景。小さく別れを告げ、歩きだす。
最後に見えたラマリア教会に、心の中で旅の無事を祈った。

ウシュグリ村からは、東へ続く一本道をひたすら歩いていくだけだ。
最高地点のザガリ峠までは7kmほど。高低差500mほどなので、そこまで険しい道のりではない。

緩やかな上り坂が続く砂利道。単調な道のりなのかと思っていたが、周囲の光景に圧倒される。
ここではもう、秋真っ盛りなのだ。

燃えるような紅色。透き通るような黄色。季節の移ろいに必死に抵抗するかのような薄緑色。
それらが混ざり合い、グラデーションのように山肌を覆う。

紅葉のピークとは、まさにこんな風景のことを言うのだろう。
あと数日ずれていたら、ここまでの彩りは見られなかったかもしれない。

それにしても、想像していた以上に歩きやすい道だ。
車両通行可能な道であることは知っていたが、相当な悪路だと聞いていたのに。
少し拍子抜けしたような気持ちになるが、周囲の風景の美しさは道のりの退屈さを感じさせない。
ウシュグリを出発してちょうど二時間。
緩やかな上り坂が平坦になり、目の前に雪をかぶった山が姿を現す。

ここがザガリ峠。二つのスヴァネティ地域を隔てる境界だ。
それまでの秋真っ盛りの風景はいつの間にか、すぐそばに迫る冬を待つ大地の風景へと変貌していた。
命を失った草の侘しげな茶色と、物音一つ聞こえない静寂。それだけが峠一帯を支配する。
この世界に、たった独りぼっちになってしまった。そう感じた。

ザガリ峠を越え、クヴェモ・スヴァネティ地方に人生で初めて足を踏み入れる。
何か標識のようなものがあるのかと思っていたが、期待は外れた。(そもそもこの道を通る人や車は恐ろしいほどに少ないので当然かもしれない)
峠を越えてすぐの場所。小高い丘の上に教会がぽつりと建っていると聞いていた。
予想以上にスムーズに上りの区間をこなせたので、足をのばしてみることにする。
丘を登ること10分足らず。目の前に現れた光景が現実のものであると、にわかには信じられなかった。

雪をかぶったコーカサスの峰々に対峙するかのように、石造りの教会が堂々とたたずんでいた。
見た感じ、さほど古いものではないように思える。
歴史的価値は薄いのかもしれないが、それを軽く凌駕する絶景が広がっていた。
そして、再びの静寂。


誰が、いつ、何故、ここに教会を立てたのかは見当もつかない。しかし、この場所を選んだ理由がなんとなく解る気がした。

教会からは、ザガリ峠の先へと下っていく道も一望できる。
いま立っている場所の寂しげな色の風景とは対象的に、赤や黄色の木々に彩られている。
峠から最初の人が住む村までは、12kmほどの距離で900mもの高低差をひたすらに下る道のりだ。
クヴェモ(低い)・スヴァネティの名の通り、下界へと少しずつ近づいていくのだ。
それを自分の足で、一瞬一瞬を感じながら歩けることに、改めて興奮と喜びを抱く。
さあ、下りていこうじゃないか。下界へ。

ザガリ峠の真っ茶色の風景が、徐々に色彩を取り戻してゆく。だんだんと黄色や赤が濃くなっていき、はじめはぽつりぽつりとしか見えなかった緑色が、いつの間にか増えていく。

この紅葉を眺めながら、ずっと何かに似ていると思っていた。
それが何なのかようやく分かった。マーブルチョコレート。
子供のとき、あの色とりどりの楕円形のチョコレートをこぼしたことをふと思い出す。
赤、茶色、黄色、緑…あの毒々しいくらいの原色の粒たち。
コーカサスの紅葉がマーブルチョコレートに見える自分の感性の幼稚さに、思わず笑いがこぼれる。
少なくとも、今目の前に広がる色彩は、マーブルチョコレートのように人工的に色づけられたものではない。

自然の色が変化していくのを目で感じると同時に、気温が少しずつ上がっていくのを肌で感じる。
冬を目前に控えた寒々しさから、秋真っ只中のひんやりとした空気、夏の名残の汗ばむ暑さへと、ほんの少しずつ。
まるで一歩進むごとに、季節の流れに逆らっているみたいに。

周囲の風景の美しさに夢中になっていたら、後ろからクラクションを鳴らされた。
このボコボコの道を延々と走るには心許ない風情の乗用車。
運転席のおじさんが窓を開け、「乗っていけ」と手で合図する。
少し迷う。ここで車に乗せてもらうことができれば、目的地のさらに先にある大きな町まで今日中にたどり着けるかもしれない。なにより、体力的にかなり楽なのは言うまでもない。
しかし、この美しい風景を、季節に逆行している不思議な感覚を、車窓越しに眺め去ってしまうのは、なんだかすごくもったいない気がした。
なにより、最後まで自分の足で歩ききりたい。そんな小さなプライドやこだわりのようなものが頭をよぎる。

せっかくの提案を丁寧に断ると、おじさんは後部座席からおもむろに柘榴を取り出し、差し出した。
真っ赤ででっぷりとした秋の味覚。おじさんがどこから来たのかはわからないが、もう秋はそこら中で始まっているのだ。
ガタゴトと音を立てつつ、でこぼこ道を遠ざかっていく乗用車を眺めながら、ふたたび下界へと一歩ずつ下っていく。


ザカリ峠を出発してニ時間ほど。
九十九折りのような山道を下りきった先にあるコルルダシという集落に到着した。

コルルダシは、かつてソ連時代に砒素を生産する工場が建てられ、多くの雇用を生んだ場所だった。
工場で働く従業員やその家族が数組居住し、かつてはクヴェモ・スヴァネティ地方最奥の村として成り立っていたのだそうだ。
しかし、ソ連崩壊とともに工場は閉鎖。村人は全員出て行ってしまい、工場も集落も全て放置されることとなった。大量の砒素を残したままに。

砒素とは、言わずもしれた劇薬の一つだ。
かつてカレーに砒素を混入させて多くの人を死に至らしめた事件があったことは、多くの日本人の記憶に残るものだろう。
コルルダシに残るかつての砒素工場周辺の土壌は、現在でも致死量の砒素に汚染されているという。そこを流れる水も同様だ。

人間の作り出したもののせいで、人間が住めない土地となる。なんとも皮肉なことだ。
そんな人間の愚行などお構いなしとばかりに、コルルダシの廃村を取り囲む大自然は、非現実的な美しさを見せてくれる。


まさに人間の住むことのできない「死の楽園」。
朽ちていくかつての工場と、燦然と命を輝かせる木々の姿があまりに対照的で、どこか不気味な雰囲気さえ感じさせる。
いっぽうで、この絶妙なアンバランスさが、どうにも心をとらえて仕方がなかった。

コルルダシから今日の目的地であるツァナという村までは、4kmほどの道のりだ。
「死の楽園」を後にして歩きはじめたころには、谷間はすでに山影にすっぽりと覆われて薄暗い。
相変わらず人の気配はまったくないし、人間の生活の営みを感じさせる風景すら、いっさい見えない。

大自然の中に身を置いているのに、人間の生活の香りが無性に恋しくなるのはなぜだろう。
「死の楽園」で感じた不気味なまでの孤独感を、まだ引きずっているからだろうか。
たった4kmの道のりが、永遠に続くように感じる。
林道を歩き続けてどれくらいが経っただろうか。ようやく、クヴェモ・スヴァネティ地方で人が住む最奥部にあたるツァナの村が視界に入る。

思ったよりも大きな村だ。十数軒の民家がぽつりぽつりと建ち並び、それまではなかった電線が張り巡らされているのが遠目にもわかる。
あそこまで行けば、人がいる。
これほどの安堵感に包まれる瞬間も、なかなかに珍しいのかもしれない。
しかし、ツァナ村に到着してみると、その安堵感は幻想であったことに気づかされることになる。
人がまったくいないのだ。

遠目では人が住んでいそうに見えた家々には、人影はない。
窓ガラスは割れ、木製テラスは朽ち、庭には雑草が生え放題。
なにより、人が生活する場に必ずこびりついている「匂い」のようなものが、ここにはいっさい感じられない。


唯一、村の高台にある教会らしきものの辺りで、何やら木を切っているような音が聞こえるだけだ。
まだ日没までは一時間ほどあるはずなのに、太陽はもう深い山々の向こうに呑み込まれ、薄暗闇が辺りを支配する。
不気味なほどに静まり返った道を、教会を目指して、ただ歩いた。

教会の目の前。ツァナ村を一望する高台には一軒の家が立っていた。
軒先に積まれた薪、煙突から流れ出る煙。庭を走りまわる鶏たち。
ようやく人の営みが感じられる場所に来た。


扉をノックすると、老夫婦とその息子の三人家族が出迎えてくれた。
いちおうゲストハウスとして宿泊客を迎え入れているのだという。願ってもないことだ。
料金を尋ね、部屋に案内してもらう。
まるでソ連時代にタイムスリップしたかのような空間。暖房やインターネットなどはもちろん無いが、電気が通っているだけましだ。食事も用意してくれるという。
ここに泊まらないという選択肢は、ない。

ツァナ村に定住しているのは、この三人家族たった一組だけなのだという。
かつては、4km先のコルルダシの工場で働く人々や、他の村人も住んでいたそうだが、1986年の豪雪によってインフラの大部分が破壊されてしまった。
それをきっかけに、村人のほとんどは最寄りの大都市であるクタイシに居を移してしまい、このゲストハウスを営む家族だけが残されたそうだ。
十一月から三月までは、ツァナ村に至る道は雪で寸断されてしまう。
しかし、たった一家族のためだけに除雪をするほど、ジョージアという国は裕福ではない。
商店も飲食店も存在せず、インターネットも通じず、携帯の電波さえ届かないこの僻地で冬を越すのは難しいそうで、この家族も初雪の頃にはクタイシの別宅へと山を下りるのだそうだ。
まさに「死にゆく村」ではないか。
この家族が村での生活に終止符を打つと決めたその瞬間から、もう村としての命は尽きてしまうのだから。

家族の息子が、シャワー用のお湯を沸かしてくれている。
屋外に設置されたボイラーを、薪を燃やして温めるのだという。
この場所にはガスなど通っていないから、考えてみれば当たり前なのだけれど、なんだかとても新鮮な光景に映る。

シャワーから出て(熱すぎるぐらいの良い湯だった)母屋に入ると、ふさふさの毛がついたままの立派な雄鶏が、息絶えた状態で薪ストーブの脇に鎮座していた。ストーブの上にはグラグラと煮立ったお湯。
たったの数分前まで雄鶏だった物体を、熱湯に数十秒浸けて取り出し、素手で羽を剥いでいく。
つるりと薄黄色の肌を現したそれは、市場でよく売られている丸鶏と同じだ。

生き物が、食べ物になっていく。
当たり前のことながらも、食品加工技術や運輸ネットワークが発展した現代では、実際に目にしてみないとなかなか実感が湧かないことでもある。
その点、山での暮らしには人間の原点がある。すべては、生きるためなのだ。
夕食は質素ながらも、家庭的な味わいの温かみがあるものだった。
お隣のラチャ地方でわざわざ買ってきたワイン(この地域では寒すぎてブドウが育たないためワインは作れないそう)をわざわざ開けてくれ、村での生活について話が弾む。

「冬のクタイシの生活と、村での生活と、どちらが好き?」なんて尋ねると、全員一致で「村に決まっている。」と即答される。「ここは世界で最も美しい場所。”楽園”だ。」と。
そう答える家族の表情は、どこか誇らしげで、一見すると不便でしかないこの地での生活を心から愛していることが伝わってきた。
そうか。ここは死にゆく村ではなく、「死にゆく楽園」なのかもしれないな。
でも、その寿命はまだしばらくは尽きることはなさそうだ。だって、この人たちがまだここに居るのだから。
なんの縁もゆかりもない、村に到着してたったの数時間しか過ごしていない旅行者ながらも、不思議と安心感を覚えた。
この儚さに満ちた美しい風景が、どうかずっと残っていてほしい。家族に笑顔で相槌をうちながら、そう願った。
・山男日記(序章)「スヴァネティの山に呼ばれて。」
・山男日記①「スヴァネティの真髄に酔う一日。」(メスティア~チュヴァビアニ)
・山男日記②「中世の村を目指して。」(チュヴァビアニ~アディシ)
・山男日記③「最高の一日に、最高の絶景を。」(アディシ~イプラリ)
・山男日記④「山の神に捧ぐ歌」(イプラリ~ウシュグリ)
・山男日記⑤「光ではなく、影が観たくなる村。」(ウシュグリ)
・山男日記⑥「死の楽園と死にゆく楽園。」(ウシュグリ~ツァナ)
・山男日記⑦「ジョージアで一番閉鎖的な村の、オアシス。」(ツァナ~メレ)
・山男日記⑧「良い旅のつくり方。」(メレ~パナガ)
・山男日記⑨「世界一美味しい、クブダリ。」(パナガ~レンテヒ)
・山男日記⑩「あの山の向こうを、確かに歩いていた。」(レンテヒ~ツァゲリ)
・山男日記(終章)「結局、私たちは何者にもなれない。」
このエリアを実際に旅する人向け。お役立ち情報
この区間のトレッキング情報
ウシュグリ~ツァナ間コース詳細
・所要時間:片道5時間~6時間
・距離:片道22km
・高低差:▲484m ▼909m
・難易度:★★☆☆☆
この区間を歩く際の注意点
コルルダシ以降の水は飲まない
記事内でも触れたとおり、コルルダシにあるかつての砒素工場周辺は、放置されたままの砒素が流出していると言われています。
土壌はもちろん、工場周辺にある湧き水は絶対に口にしないようにしましょう。
また、コルルダシから下流へと流れるコルルダシ川にも微量ながら工場由来の砒素が含有されているそうなので、こちらも飲用は厳禁。
ツァナ村にはコルルダシ川とは水源を別にする湧き水があり、そちらは安全だそうです。
明るいうちに到着する&野宿は厳禁
ザカリ峠から少し標高が低い地域の山林には、熊が多く生息していると言われています。
昼間は姿を現すことはなく危険はないそうですが、暗くなってからの山歩きは危険。
また、ウシュグリ~ツァナ(~その先のメレ)の区間は極端に人口が少ないエリアなので、野生動物の王国であると言えます。
キャンプ等、屋外で夜を明かす行為は絶対にやめましょう。
現金は十分に用意しておく
この区間のみならず、ゼモ・スヴァネティ地方(メスティアやウシュグリがあるエリア)~クヴェモ・スヴァネティ地方に共通する注意点なのですが、ATMの数にものすごく限りがある点に要注意。
それぞれの地方で最寄りのATMがある町は以下の通り。
・ゼモ・スヴァネティ地方:メスティア(TBC Bank / Bank of Georgia / Liberty Bank / Credo Bank etc…)
・クヴェモ・スヴァネティ地方:レンテヒ(Liberty bank)
この二つの町以外には、銀行はおろかATMは一台もありません。
また、クレジットカードの通用度はほぼ絶望的なので、現金がなければ詰みます。
スヴァネティ地方を観光する場合は、必要な現金をあらかじめ計算し、余裕を持って下ろしておくのが絶対です。
インターネットはない
ウシュグリを出て10分ほどで携帯電話の電波は圏外となり、それ以降の区間もいっさい電波が入らなくなります。(人がほぼ住んでいないので当然といえば当然ですが)
ツァナ村に入っても携帯の電波は圏外のまま。
インターネットケーブルすら敷かれていない村なので、当然Wi-Fiも存在しません。(電気は通っています)
次に携帯の電波が入るのは、ツァナ村から18km先のメレ(Mele)という村の手前あたり。
それまでネットの接続は絶望的なので、調べもの等は事前に済ませておきましょう。
徒歩以外のアクセス情報
記事内では、実際に徒歩で歩いたようすをレポートしていますが、この区間は他の移動手段を利用することも可能です。
ウシュグリ〜ザガリ峠
ウシュグリ村~ザカリ峠までの上り坂をスキップして、峠から下り坂のトレッキングをしたい場合は、馬か4WD車をチャーターすることも可能です。
・馬チャーター:一頭200GEL~300GEL(=¥10000~¥15000)
・4WD車チャーター:一台200GEL~300GEL(=¥10000~¥15000)
とはいえ、正直ここの登りの区間はたいした傾斜はなく、緩やかな坂道がずっと続くだけのもの。
個人的には、わざわざ別の交通手段を利用して峠まで行くなら、頑張って歩けば良いと思います。
ウシュグリ〜ザガリ峠〜ツァナ
今回の記事の道のり全てを、徒歩ではなく車に乗って移動したい場合は、4WDのチャーターのみ可能です。(馬のレンタルは距離が長すぎるため、拒否されるでしょう)
・4WD車チャーター:一台400GEL~500GEL(=¥20000~¥25000)
このオプションが利用可能なのは、本記事と同じウシュグリ→ツァナへ抜ける場合のみ。
ツァナ村には4WD車どころか人口がほとんどないため、ツァナ→ウシュグリ方面の場合は徒歩での移動に限られます。
クタイシ/レンテヒ〜ツァナ
ウシュグリからではなく、ツァナ村へジョージア他都市から直接アクセスしたい場合は、クタイシかレンテヒ(Lentekhi)のいずれかの町が拠点となります。
クタイシの中央バスステーションから1日1本、レンテヒ経由メレ(Mele)行きのミニバスが出ています。(クタイシ発15:00 / 20GEL)
メレ~ツァナ間を結ぶ公共交通手段は存在せず、18kmほどの道のりを歩くか、ヒッチハイクするかになります。(メレにはタクシー等はありません)
ツァナ村の宿情報
【Tsana Guesthouse】

・料金:50GEL ※夕・朝食付
・部屋タイプ:ドミトリー
・注意点:オーナー家族は毎年3月後半~11月に初雪が降る期間しか村にいないそうなので注意。
・山男日記(序章)「スヴァネティの山に呼ばれて。」
・山男日記①「スヴァネティの真髄に酔う一日。」(メスティア~チュヴァビアニ)
・山男日記②「中世の村を目指して。」(チュヴァビアニ~アディシ)
・山男日記③「最高の一日に、最高の絶景を。」(アディシ~イプラリ)
・山男日記④「山の神に捧ぐ歌」(イプラリ~ウシュグリ)
・山男日記⑤「光ではなく、影が観たくなる村。」(ウシュグリ)
・山男日記⑥「死の楽園と死にゆく楽園。」(ウシュグリ~ツァナ)
・山男日記⑦「ジョージアで一番閉鎖的な村の、オアシス。」(ツァナ~メレ)
・山男日記⑧「良い旅のつくり方。」(メレ~パナガ)
・山男日記⑨「世界一美味しい、クブダリ。」(パナガ~レンテヒ)
・山男日記⑩「あの山の向こうを、確かに歩いていた。」(レンテヒ~ツァゲリ)
・山男日記(終章)「結局、私たちは何者にもなれない。」


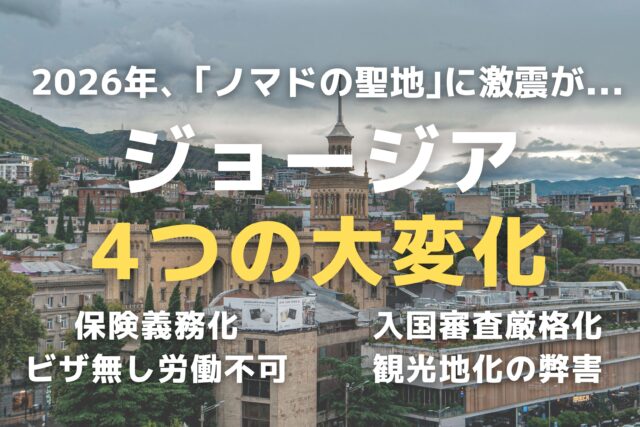






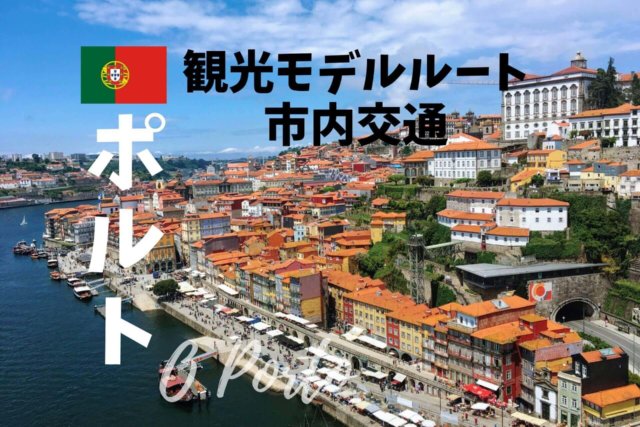






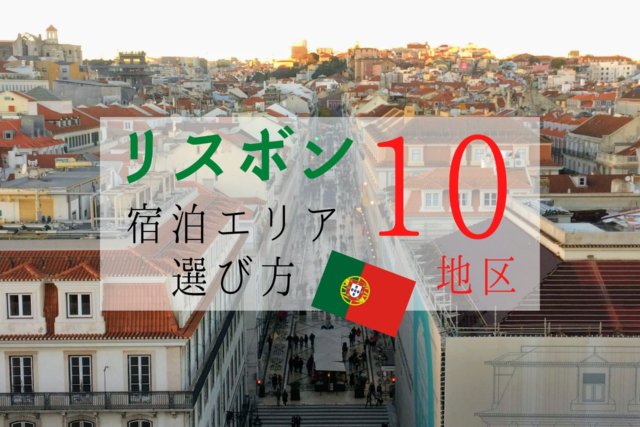



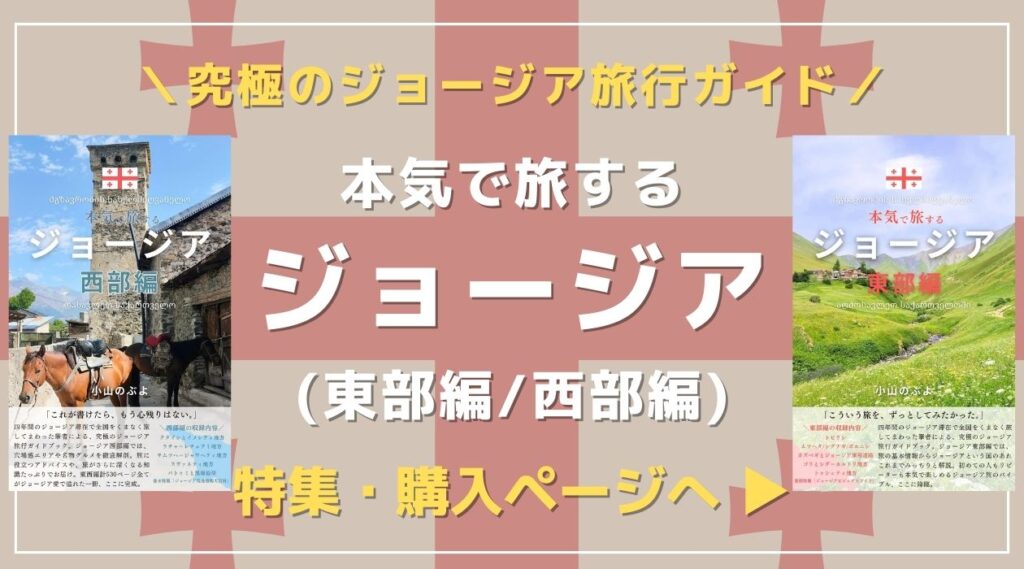

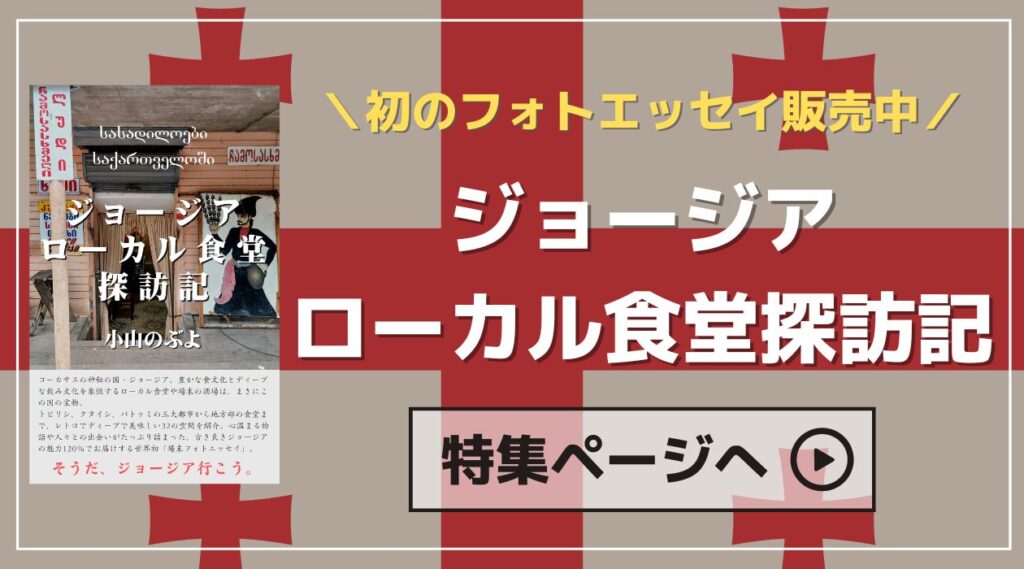


コメント