出発の朝は、早い。…なんてことはなかった。
いつもと同じような時間に起き、もう10日以上は居座っているメスティアの宿の庭で、温かいコーヒーを飲みながら煙草を数本。
ここ数日間の朝とあまりにも変わらない時間を過ごしたからか、自分が本当にこれからコーカサスの山に対峙しに行くのか分からなくなる。
とはいえ、出発のときは訪れる。
居心地が良すぎてもはや自分の家のように感じていた場所を、ここで過ごした日々を、出会った人々との時間を…そうしたものを振り切るように、ギリギリで荷造りしたバックパックを勢いよく背負って、旅立つ。

目をつむったままでも歩けそうなほどにくまなく散策したメスティアの町。
「もうきっと戻ることはないだろう。」
そう思うと、やけに後ろ髪引かれるような思いにとらわれる。
名残惜しく感じる気持ちを抑えながら、見慣れた街並みをあえて早足で歩いた。
山歩きの一日目は、距離17km/高低差500mほどの道のり。コース前半にあるビューポイントに向かって、緩やかな登り坂が延々と続く。

ふと後ろを振り返ると、メスティアの町のパノラマが見える。
合計10日以上も滞在していた町であるはずなのに、その風景はなんだかいつもよりもキラキラと輝いている。まるで知らない町のようにさえ思える。
もう戻る予定も理由もないのに、「またいつか来たいな」なんて思っている自分に驚きながら、歩を進める。

ビューポイントまでの道のりは、それまでの緩やかな上り坂からだんだんと急坂へと変化していく。
まだスタートして間もないので体力的にはまったく余裕だが、荷物の重さが想像以上に肩や足腰にかかっているのを感じる。
息を切らしながらようやく登りきった急坂。
そこで待ち受けていたのは、二年前に見たのとまったく変わらないスヴァネティ・バレーの大パノラマだった。

正面に見えるのはテトヌルディ山。二等辺三角形の美しいフォルムが特徴的で、数日前に天候が荒れた期間で、山頂は真っ白に雪化粧している。
テトヌルディ山に抱かれるように散在する村々には、スヴァネティ地方独特の「復讐の塔」がにょきにょきと生えているのが見える。
目の前に広がる谷間の桃源郷さながらの風景に、どうしようもない感動を覚える。
初めて見る風景ではないのに。
…これから、あの谷間を歩いていくんだ。

後ろを振り返ってみると、こちらも雪化粧したウシュバ山が顔をのぞかせる。
ここ数日の雨が溜まってできた小さな池に、山頂が映りこんでいることに気がついて、はっとする。
雨の後にしかここに池はできないので、まさにかりそめの絶景。
これが見られただけでも、悪天候のメスティアで数日間じっと出発を待ち続けた価値があったのかもしれない。
もうハイキングシーズンも終わりに近いからなのか、一日目のハイライトであるはずのこのビューポイントに、人の姿はほとんどない。
唯一、休憩をしていたイスラエル人の若いカップルに話しかけられ、コーヒーをご馳走になる。
ガスバーナーでコーヒーの粉を入れた水を沸かすトルコ式。
イスラエルから持参したと言うコーヒーの味は、ほのかにスパイスが効いた香り深いものだった。
初めてのジョージア旅行で、スヴァネティ地方のトレッキングも初めてだというイスラエル人たち。(そもそもこんな僻地で同じコースを歩くリピーターなど余程の物好きなのかもしれない)
目の前の絶景を眺めながらこれまでの旅やこの先の予定について話す彼らの目は、眩しいほどに輝いていたけれど、きっと自分の目だって負けないほどに輝いていたに違いない。
それほどに、自分たち三人を取り巻く風景と、エスニックな風味のコーヒーがもたらす効果には特別なものがあった。

もう少しのんびりしていくというイスラエル人たちを残し、再び歩きはじめる。
ここからはもう上りはほとんどなく、谷の最奥部までゆるやかな下り坂を10kmほど歩いていくだけだ。
急坂を登っているときとは異なり、体力的にも精神的にも余裕が出てくるから、ときどき足を止めては周囲の風景を眺める。
いや、余裕があったから何度も立ち止まったわけではない。
足を止めずにはいられないほどの美しい風景が続々と目の前に現れてくるのだから、素通りすることなんてできなかった。

スヴァネティ・バレーには十ほどの集落が点在しており、どれも人口数人から数十人ほどだという。
谷の最奥部に位置するジャベシとチュヴァビアニの二つの村は、ハイカーたちの定番の宿泊ポイントとなっているため、ゲストハウスなどが点在しており、人口もまだ多い。
いっぽうで、最奥部の二つの村に至るまでの道沿いにある村々は、これといった産業もなくハイカーも素通りしてしまうため、人口がどんどん流出した結果、限界集落さながらの状態となっている。

朽ち果てた民家。崩れ落ちた塔。道に散乱する瓦礫…
そんな「死にゆく集落」の中にも、数組の家族が生活しており、観光地化とは無縁の昔ながらの生活の営みを感じることができる。
車が入れないほどの狭い道しかないため、村人たちの主な移動手段は現在でも馬だ。

崩れかけた石壁の路地を曲がった途端、馬に乗った村人と鉢合わせて驚いた。
向こうは手慣れたもので、笑顔を見せながらこちらをうまくよけ、瓦礫が散らばる道を颯爽と去っていく。
こんな光景がこれらの村々での日常で、その日常はきっとこれからも続いていくのだろう。
いや、むしろ。「この昔ながらの生活がいつまでも続いていてほしい」なんて思うのは、他所者が地方部に期待する「ピュアな田舎幻想」にすぎないのだろうか。


限界集落でのんびりしすぎたせいか、メインのコースに戻るのが遅くなってしまった。
最後の2kmほどには、新しく舗装道路が敷かれていて驚いた。
二年前は確か、動物の糞だらけのべちょべちょの道に悪態をつきながら歩いたはずだ。
少しずつではあるが、この場所にも現代文明の波が押し寄せてきているのかもしれない。もしくは、観光客が多く訪れるようになっているのかもしれない。
先ほどまで居た限界集落たちとのインフラの差に驚くとともに、きっと他所者の淡い期待に反して、いつか昔ながらの生活は消滅してしまう運命にあることを心のどこかで悟った。

ようやく、今日の宿泊地であるチュヴァビアニ村が見えてきた。
西日に照らされて橙色がかった小さな村…まるで旅行者の到着を歓迎してくれているようではないか。
今日の宿は予約こそしていなかったものの、見当はつけてあった。
メスティアの宿で出会ったフランス人旅行者(すでにこの区間を歩き終えていた)がおすすめしてくれていたのだ。

予約なしだというのに、温かく迎えてくれた宿の家族。
部屋こそ質素だが、お湯は問題なく出るし、暖房も効いている。
広々とした庭で鶏と子どもたちが追いかけっこをしている、そんなジョージア地方部の典型的な家族経営ゲストハウスといった宿だった。
夕食をお願いすると、さっそく準備に取りかかってくれる。温かなシャワーを満喫して食堂に向かうと、驚くほどの量の食事が食卓に鎮座していた。

ロビオ(豆の煮込み)、アジャプサンダリ(ナスのシチュー)などジョージア料理の定番の品揃えだが、どれもスヴァネティ・ソルトが効いていてひと味違う。美味しい。
もちろん完食できるはずはなく、残りは翌日の朝昼用に取っておいてもらうことにした。
夕食後は一階の家族が住む空間に招かれ、オーナーとワインを飲みながら色々と語り合う。
なんとこの家、950年前に地下住居として建設された空間の真上に建っているそうで、現在でもその空間が残っていると言う。
リビングの片隅にある古い扉を開け、石造りの通路を下った先に現れる二枚目の扉を開けた先に、その空間が姿を現す。

四方を石壁に囲まれた10mほどの地下空間。
天井近くに小さな窓が一つだけ設置されており、地上と隔絶されていることが肌で感じられるほどの、ひんやりとした地下特有の空気に満ちている。
スヴァネティ伝統の地下住居にざっくばらんに置かれているのは、950年前の家財道具や調理器具。
以前トビリシの民俗博物館でスヴァネティ地方の民家の再現を見たことがあるが、比べ物にならないほどの充実度で、すべてが本物だった。

かつてはこの空間に25人ほどが生活していたのだという。
そうとは信じられないほどにこの場所は狭く、閉塞感があり、薄暗かった。
山羊や馬をモチーフにした囲炉裏や調理器具に、手の込んだ装飾が施された家財道具が目を引く。
スヴァネティ地方の人々が古くから大切に守り続けてきた文化や歴史の全てが、この小さな空間に息づいていた。

予期せぬ驚きに興奮は収まらないが、夜はだんだんと深まっていく。
気を良くしたオーナーによるチャチャ(ジョージアの蒸留酒)の誘いをありがたく断り、自室に戻る。
そうして今、ふかふかのベッドの上でこの文章を書きながら、ただひたすらに今日という一日を噛み締めている。
これ以上完璧な旅のスタートなんて、きっと他にないだろう。
今朝、メスティアの街を出発したときの名残惜しい気持ちなど、もう微塵もないと断言できる。
それほどに、明日から待ち受けているさらなる旅の楽しさにだけ、この心が向いているように感じてならない。
・山男日記(序章)「スヴァネティの山に呼ばれて。」
・山男日記①「スヴァネティの真髄に酔う一日。」(メスティア~チュヴァビアニ)
・山男日記②「中世の村を目指して。」(チュヴァビアニ~アディシ)
・山男日記③「最高の一日に、最高の絶景を。」(アディシ~イプラリ)
・山男日記④「山の神に捧ぐ歌」(イプラリ~ウシュグリ)
・山男日記⑤「光ではなく、影が観たくなる村。」(ウシュグリ)
・山男日記⑥「死の楽園と死にゆく楽園。」(ウシュグリ~ツァナ)
・山男日記⑦「ジョージアで一番閉鎖的な村の、オアシス。」(ツァナ~メレ)
・山男日記⑧「良い旅のつくり方。」(メレ~パナガ)
・山男日記⑨「世界一美味しい、クブダリ。」(パナガ~レンテヒ)
・山男日記⑩「あの山の向こうを、確かに歩いていた。」(レンテヒ~ツァゲリ)
・山男日記(終章)「結局、私たちは何者にもなれない。」



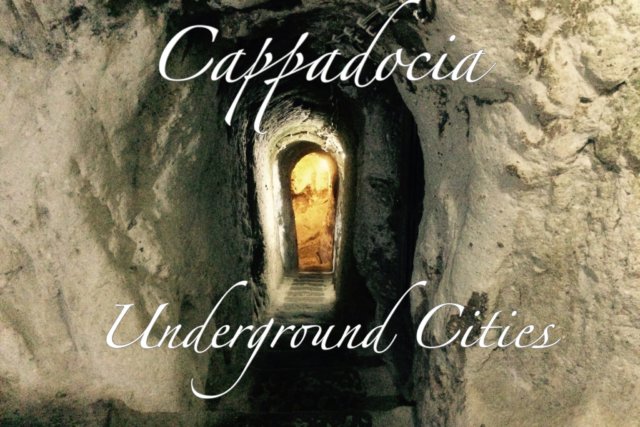





















コメント