窓から差し込む朝の光で目を覚ます。
前日の長く険しい峠越えの疲れのせいか、快適なベッドのおかげか、なんだかとてもよく眠れた気がする。
朝の甘美なまどろみの途中。ふと窓の外に目をやり、途端に気分が高揚する。
文句なしの快晴だ。

外に出てみると、朝の光に照らされたイプラリ村が目の前に広がる。
昨日の夕方に到着したときには気が付かなかったが、すでにこの辺りの山も紅葉がぽつりぽつりと始まっている。
それを背景とした小さな集落。なんだかとても絵になる。
早く歩きたい。そう思った。

はやる気持ちに従うように荷造りを済ませ、宿の家族に挨拶をし、村を後にする。
今日はメスティアからの四日間トレッキングの最終日。
スヴァネティ地方の最奥部に位置するウシュグリ村を目指して歩く日だ。
これまで歩いてきた三日間のコースに比べると、今日の道のりは山歩きとしての魅力はやや少ない。
ウシュグリ村までは車両も通行できる未舗装の道路が敷かれており、それに沿って歩いていくだけだからだ。
とはいえ、スヴァネティ地方観光におけるハイライトとして名高いウシュグリ村が目的地となるのだ。
それも自分の足で到達するのだから、到着の瞬間の感動は計り知れないものがあるだろう。

山の中腹に位置するイプラリ村からは、急な坂道を下って、谷底に位置するラルホリという村に向けて歩いて行く。
ラルホリ村からウシュグリ村までは、未舗装道路を9kmほど延々と歩いていくだけだ。


かなり急な下り坂をしばらく歩くと、朝の柔らかな光に包まれたラルホリ村が見えてくる。
谷底にひろがるラルホリ村は、十数軒の民家が建ち並ぶだけの小さな集落といった雰囲気。
メスティアとウシュグリを結ぶ唯一の道路沿いに位置しており、たまに旅行者を乗せた満員のミニバンが走り過ぎていく。ウシュグリへ日帰り観光に向かうのだろう。
旅のスタイルや移動手段に優劣などない。好きなように旅すれば良い。
そんなことは分かっていながらも、高いお金を払って車でさっと移動してしまう「ツーリスト」(あえてそう呼ぼう)たちには到底見られない風景を、到底味わえない経験や感動を、自分は現在進行形で味わえていることを、なんだかちょっと嬉しく感じた。

ラルホリ村のすぐ先にはダヴベリという美しい村がある。
ダヴベリから先、ウシュグリまでの7kmほどの区間には村は存在せず、人は住んでいない。
緩やかな傾斜をともなった未舗装の悪路が延々と続いているだけだ。

未舗装道路は渓谷に沿って敷かれており、自然の美しさは存分に感じられる。
しかし正直なところ、これまでの三日間で感じてきた「山歩きの楽しさ」のような魅力には乏しい。
車は十分に一台通るかどうかという交通量。イヤホンを取り出し、音楽でも聴きながら歩くことにする。
こんなときのために予め作っておいた、お気に入りのジョージア伝統音楽プレイリスト。
ギターのような木製の伝統楽器・パンドゥリのエキゾチックな音色にのった力強い歌声が、コーカサスの山の中を歩く気分を盛り上げてくれる。


車も通れる未舗装道路ということもあり、これまでの山道とは比べ物にならないほど歩きやすい。
とはいえ、ウシュグリ村までは高低差が400mほどある。
緩やかとはいえ、上り坂が休みなしに続いていくのは、意外と体力を消耗する。
三十分に一回ほど休憩を挟みながら、のんびりと歩く。
時間はまだ午後一時過ぎ。余裕だ。

緩やかな上り坂がほぼ平坦になり、放牧された牛たちの姿が目に入るようになる。
家畜がいるということは、人が住む場所、つまりウシュグリ村が近いということだ。
イプラリ村から歩きはじめて四時間弱。とうとう待ち焦がれていた瞬間が訪れた。

ウシュグリ村の境界にあたる場所に立てられた標識。
ここから先は、スヴァネティ地方最奥の村の敷地となる。
標識に貼られたカラフルなステッカーたちが、旅の情緒を演出しているように思える。
自分と同じようにここまで歩いてきた人たちだろうか。サイクリストだろうか。きっとみんな、この場所に到達したときには、言葉では言い表せないほどの感動や興奮を抱いたのだろう。
今まさに、この心が達成感に包まれているのと同じように。
標識から少し先。小高い丘の上に、何かが建っているのが見える。
あれは、村の防衛拠点としての役割を担ってきた要塞。
村の入口にあたる場所に建っており、そのすぐ先にウシュグリ村が広がる。
標識から丘の上の要塞を正面に歩を進めると、とうとうウシュグリ村がその姿を現した。

二年前。はじめてこの場所を訪れたときも、まったく同じ道のりを四日間かけて歩いた。
ようやくウシュグリに到着し、まさにこの景色を眺め、心を打たれた。
二年後の今、あの瞬間の気持ちを追体験しているような、深い感動に駆られる。
いや、もしかしたら、二年前よりも感動が深まっているような気がする。
初めて見る風景ではないのに。初めて味わう瞬間ではないのに。なぜだろう。
旅は、ほんとうに不思議だ。

ウシュグリは、実は単体の村ではない。
それぞれ数百メートルほど離れた場所に位置する、四つの集落の総称。それが「ウシュグリ」だ。
村の入口にあたるムルクメリ地区。古い石塔や石造りの民家がひしめき合うチャジャシ地区。中心部にあたるチュヴビアニ地区。最も高い場所に広がるジビアニ地区。
村の背後に堂々とそびえるシュハラ山の氷河から解け出たエングリ川の流れに沿って、四つの集落が細長く広がっている。


それにしても、何と美しい村だろうか。
千年以上前に建てられた石塔や石造りの民家が、形一つ変えずに残り、旅行者を出迎える。
早く、この美しい風景の中に身を置きたい衝動に駆られる。
しかし重たいバックパックを持ったまま散策するのは得策ではない。
はやる気持ちをどうにか抑えながら、中心部のチュヴビアニ地区にあるゲストハウスへと一直線に向かう。
ウシュグリで宿泊するゲストハウスには、目星をつけてあった。
二年前の訪問時に滞在し、とても素敵な思い出となった宿だ。
いつものように予約なしで飛び込みで泊まろうとしたのだが、到着すると驚きの答えが返ってきた。
なんと今年は改装中でゲストハウスとしての営業をしていないというのだ。
記憶と寸分違わないゲストハウスの建物の半分にはカバーがかけられ、確かに工事の真っ最中。
少なくとも宿泊できるような状態ではない。
申し訳なさそうにするおばさんは、すぐ隣のゲストハウスの家族に声をかけてくれ、そちらに泊まることになった。

完全なる普通の民家のたたずまいではあるが、二階部分は宿泊客向けに改装されている。
居心地も悪くないし、ウシュグリの中心部に位置するため何かと便利だ。
一階部分は家族が暮らすスペースだが、宿泊客も自由に出入りして良いという。
絵に描いたような「おじいちゃんおばあちゃんの家」そのままの雰囲気で、ゲストハウスというよりも「民家」だ。


調理用と暖房用を兼ねた薪ストーブ。食卓に放置されたままの朝食の残り。収納しきれずにその辺に置かれた衣類や靴。
こうした飾らない雰囲気が嫌いではない。というか、好みだ。
その場所で暮らす人の日常の一部にお邪魔しているような感覚になれる宿は、貴重だと思っている。

案内された部屋でバックパックを下ろした瞬間、文字通り「肩の荷が下りた」気がした。
少なくとも今日から数日間は、重い荷物を背負って山歩きをすることはないのだ。
宿探しをする必要はない。翌日歩く道のりを逆算して起きる時間を決めなくてもよい。食べ物にも困らない。インターネットもちゃんとある。
山歩きは好きで好きでたまらないのだけれど、英気を養う期間だって必要だ。
十月とは思えないような暖かい日差しに照らされた木製ベンチでコーヒーを一杯飲んでから、宿の目と鼻の先にあるタマル女王の塔へと向かうことにした。

タマル女王とは、およそ八百年前に中世ジョージア王国を治めた、最初で最後の女性国王のことだ。
彼女の治世中の王国は黄金時代を謳歌しており、長らく支配が及んでいなかったスヴァネティ地方にもある程度の影響力を及ぼしたのだという。
タマル女王は、まさにこのウシュグリ村を訪れた。その記念に建てられたのがこの古い石塔なのだという。

小高い丘の上にたたずむ石塔は、ウシュグリきっての絶景ポイントとしても知られる。
西側には、屈強な石造りの民家と塔がひしめき合うチャジャシ地区と、遠くにムルクメリ地区を望む。
ウシュグリにやって来たことを実感する、とても美しい風景だ。
しかし、楽しみにしていたのはタマル女王の塔の東側に広がる風景だった。
二年前にこの地を訪れたとき、一番の感動を覚えたあの風景。
今はどう見えるのだろうか。二年前と変わっていないだろうか。
塔の反対側へとまわりながら、視界の向こうにすでに広がっているその眺めから、あえて目線を逸らしながら歩く。
なんだか、楽しみは最後にとっておきたくて仕方がない子供みたいだ。客観的に見たらさぞ滑稽な姿だろうな。
目線を足元に向けたまま、深く息を吸い込み、吐き出し、また吸い込み…を数回繰り返し、とうとう目線を正面に向ける。

そこにあったのは、二年前に見たものと同じ、ウシュグリの風景だった。
変わっているものといえば、山肌が少しばかり茶色みを増していること。正面のシュハラ山を覆う雪が少なめであること。それくらいだ。
肩を寄せ合うようにひしめき合う民家。民家からにょきにょきと生えた石塔たち。午後の太陽の光を受けて黄金色に輝く山々。それらすべてを抱くように白く泰然と聳えるシュハラ山。
この景色をもう一度、ずっと見たかったんだ。

タマル女王の塔に寄りかかりながら、ぼうっと目の前の風景を眺めた。
気が付けいたときには、もう小一時間ほどが経っていた。
このまま村の散策を続けても良かったのだが、宿に戻ることにした。
あまりの感動の後に別の美しい風景を見ても、どうしても見劣りしてしまう。そんな気がして。

宿に戻り、手短にシャワーを済ませて食堂に入ると、すでに薪ストーブが焚かれていた。
パチパチと木がはじける音に呼応するように、暖かな空気がじわりじわりと空間を満たしていく。
家族の一員だという男性数人が食堂にやって来て、挨拶をする。
しばらくすると、その友人らしき人たちが数人。あっという間に小さな食堂は人でいっぱいになった。
男の一人が、台所の奥から硝子瓶を引っさげて食卓に就き、「飲むか?」と不敵な笑みとともに問いかけてくる。
チャチャ。アルコール度数40%とも60%とも言われる、ジョージア伝統の葡萄の蒸留酒だ。

酒には強い方だ。誘われた酒は断らないというのもポリシーだ。
蒸留酒は好みではないが、せっかくなのでいただくことにする。
チャチャを囲んでの飲み会には、一種のパターンのようなものがある。
乾杯の音頭(「~に感謝!~にも感謝!」をひたすら長々と述べる)からはじまり、全員クイっと一気に飲み干しては新たに注がれ、また別の何かに感謝を述べる乾杯の音頭がとられ…
こんな感じなので、三十分もすれば場の雰囲気が完全にできあがる。
言葉がわからなかろうが、関係ない。こうした場にただよう楽しさは、世界中どこへ行こうとも変わらないのではないかと思う。
薪ストーブで温まった部屋。そこで飲むチャチャ。
体の外側からも内側からも温まっていくのを感じる。
きっとこの地の人々は、昔からずっと、長く厳しい冬をこうして乗り越えてきたのだろう。

煙草を吸いに外へ出た男たちが、なにやら歌っているのが聞こえる。
ポリフォニー(混声合唱)だ。
しかも、聞き慣れたジョージア語ではない。スヴァネティ地方独自の言語である、スヴァン語の。
その節はとても神々しくて、のびやかで、酒飲みの男たちの発する声色とは思えないほどに澄みきっていて。いつの間にか夜の帳が下りつつあるコーカサスの山々に、染み渡るかのように消えていく。
まるで山の神に捧げられた歌みたいだ。
その音色の神聖さが、男たちの真剣さが、目の前の山の屹然さが。
この瞬間を構成するすべての要素があまりに圧倒的で、他所者が邪魔するのはひどく悪いように思えた。
だから、男たちから少し離れた場所で煙草を吸うことにした。
どうやら、先ほどとは別の歌が始まったようだ。
男たちが奏でる音色が、徐々に繊細さを帯びながら、小さく響いている。
煙草をすうっとふかし、藍色の山影を眺めながら、それを遠くに聴いている。
・山男日記(序章)「スヴァネティの山に呼ばれて。」
・山男日記①「スヴァネティの真髄に酔う一日。」(メスティア~チュヴァビアニ)
・山男日記②「中世の村を目指して。」(チュヴァビアニ~アディシ)
・山男日記③「最高の一日に、最高の絶景を。」(アディシ~イプラリ)
・山男日記④「山の神に捧ぐ歌」(イプラリ~ウシュグリ)
・山男日記⑤「光ではなく、影が観たくなる村。」(ウシュグリ)
・山男日記⑥「死の楽園と死にゆく楽園。」(ウシュグリ~ツァナ)
・山男日記⑦「ジョージアで一番閉鎖的な村の、オアシス。」(ツァナ~メレ)
・山男日記⑧「良い旅のつくり方。」(メレ~パナガ)
・山男日記⑨「世界一美味しい、クブダリ。」(パナガ~レンテヒ)
・山男日記⑩「あの山の向こうを、確かに歩いていた。」(レンテヒ~ツァゲリ)
・山男日記(終章)「結局、私たちは何者にもなれない。」




















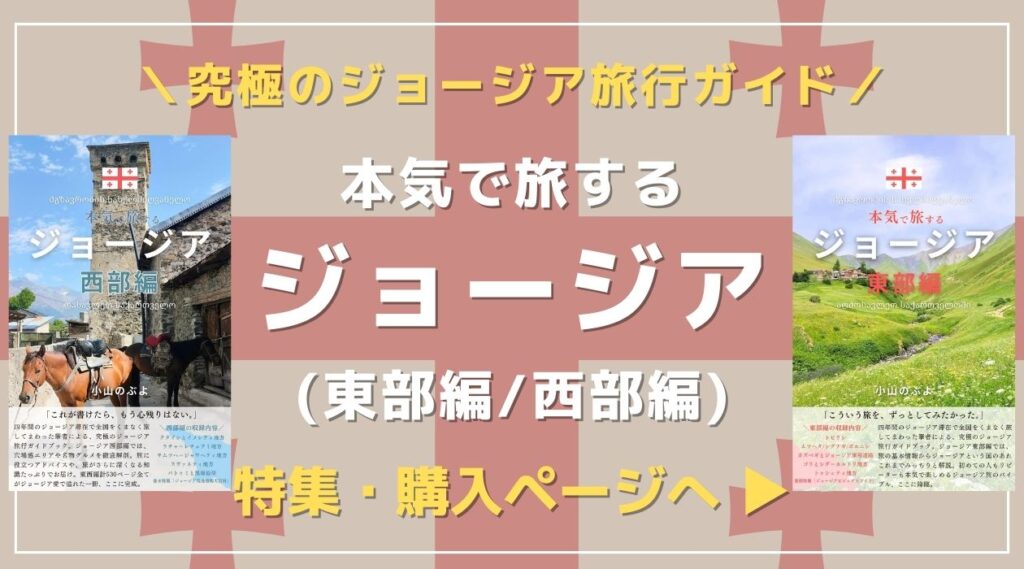




コメント