朝のアディシ村には、どうしようもなくコーヒーが合う。

鼻腔を刺激するひんやりとした空気。だんだんと谷間を照らしていく朝日。いつもと変わらずにそびえる石塔。しんと寝静まった村に響く鳥たちのさえずり。
「スヴァネティ地方で地理的に最も隔絶された村」を五感で感じながら、温かなコーヒーをずずっと啜る。
これ以上に山の朝を感じられる瞬間など、きっと他にない。
さあ、そろそろ出発。
今日のコースは、メスティアからウシュグリまでの四日間の山歩きの中で最もハードなコースだ。
17kmの道のりは、四日間のトレッキングの中でも最長。600mほどの高さを登って峠を越えねばならない場面もある。
心の準備を整えながら、朝のアディシ村を散策する。
どんよりとした曇り空だった昨日とは打って変わり、すがすがしい青空が広がる。


朝の光に照らされた中世の村は、曇り空の下とは異なる表情を見せる。
昨日、村全体を包み込んでいた陰鬱さや不気味な雰囲気はどこかへ立ち消え、村全体がつかの間の暖かな陽気を楽しもうと生き生きしているように感じられる。
もう少しこの美しき中世の村でのんびりと時間を過ごしたい…そんな気持ちがふつふつと湧いてくる。
でも、もう行かなくちゃ。

朝日にキラキラと輝くアディシ村を背にして、名残り惜しむようにちらちらと振り返りながら、歩く。
何度見ても、どの角度から見ても、まるでこの世のものではない美しさ。
でも、きっともう、訪れることはないだろう。
振り返るたびに少しずつ小さくなっていく桃源郷に、心の中で「さようなら」と呟いた。

アディシ村から5kmほどの区間は、アディシチャラ川に沿って歩いていくだけの簡単なコースだ。
高低差もほとんどなく、秋の色を深めつつある渓谷をひたすら歩いていく。

雲ひとつない青空が気持ち良い。川の流れる音が心地良い。
自分は今、コーカサスの大自然の中に確かに存在している。
山を歩くことの醍醐味を噛みしめながら歩いていくと、正面に真っ白な山肌が目に入ってくる。
あれがアディシ氷河だ。

氷河から流れ出た水は川となり、轟々とした水音をたてながら流れ、やがて人々の命の水となっていく。
ダイナミックな風景に心を奪われていたのもつかの間。今日の山歩きにおいて最大の難関が訪れる。
このアディシチャラ川を渡らねばならない。

トレッキングコースは川の向こうに続いているのだが、幅3〜4メートルほどの川には橋などは設置されていない。自分の足で渡る必要がある。
もしくは、「これぞ商売どころ」とばかりに目をつけ、馬とともに川辺で待機するアディシの村人にお金を払い、馬に乗って川渡りするかだ。
たった十秒の乗馬の川渡りに25ラリ(¥1250)なんて足元を見てくる魂胆が大嫌いなので、馬に乗るなんて選択肢はない。
この持って生まれた肉体をして、川の流れに対峙してやろうではないか。
威勢良く靴と靴下を脱ぎ、携帯をバックパックにしまい、試しに川の水に足をちょこんとつけてみる。
…恐ろしいほどに冷たい。
しかしもう行くしかないのだ。

できるだけ流れが緩やかそうなポイントを見定め、意を決して足を踏み入れる。
アドレナリンが出ていたのか、冷たさに体が慣れたのか、川を渡っている数十秒の間は冷たさをあまり感じない。というか、必死すぎてあまり覚えていない。
川の流れというものは目で見るより急で危険なものなのだ。
ようやく渡りきって、川の水から足を出した瞬間、冷たさかじんじんと足の指先から、爪の間から入ってくるような感覚にとらわれる。

バックパックを放り出し、草むらに横たわる。煙草をふかしながら、両足が乾くのを待つ。
最大の難所を越えたことによる達成感のせいか、周囲の風景はより色彩を増してキラキラと輝いて見える気がする。
山歩きにおいては絶景を眺めることも好きだが、なんでもない場所で休憩するこうした時間も、すこぶる好きだ。

足も乾いたことだし、再び歩きはじめる。
ここから2kmほどはずっと急な坂が続いていく。
秋の始まりの風景の先に鎮座する氷河を目指して歩いていくと、少し開けた広場のようなポイントがある。
ここから眺めるアディシ氷河は、メスティア〜ウシュグリ間の四日間トレッキング全体で最も素晴らしいもののひとつだ。

まるで月のクレーターのような灰色の巨大な窪み。その上に立ちはだかるような氷の壁。地球上の風景ではないかのような、圧倒的な大自然。
ときおり、腹の底に響き渡るような「どどどどぉっ」という音とともに、氷河が崩れていく。それを除けば、この場所は果てしなく無音だ。

まるで世界に独りぼっちになってしまったかのような、圧倒的な孤独感に身を包まれる。そうだ、大自然とはこういうものだった。
これほどまでに、自分という存在の小ささを突きつけられる瞬間など、普通に生きていてあまり訪れるものではないのかもしれない。
そう思わせるほどに、目の前の風景と周囲にただよう雰囲気は、ただひたすらに強烈だった。

大自然の造形に心から圧倒されたあとは、いよいよ峠へと向かって登る。
たったの2kmほどの距離で500mほどの高低差があるのだから、なかなかの急坂が続いていく。
急坂を登るのはしんどいものだ。体力的にも、肉体的にも。
しかし、今はそこまで苦に感じない。
なぜなら、登りながら眺める景色があまりに美しすぎるからだ。


登れば登るほどに、秋の色彩を濃くしていく木々たちと、徐々にひんやりとした肌触りになっていく空気。
アディシ氷河を背景に、今朝歩いてきたアディシ村からの渓流沿いの道を横目に、言葉にならないほどの美しい風景が広がる。
山登りとは不思議なものだ。
どう考えてもしんどいはずの道のりでも、それを凌駕する感動の波に呑まれながら歩いていると、苦労を苦労と感じなくなる。
本日最も標高が高い地点にあたる峠に到着するまで、さほど時間はかからなかった。

峠からは、今日歩いてきた道のすべてを見渡すことができる。
先ほどまで登ってきた急坂。雄大なアディシ氷河。意を決して越えた川。深く刻まれた渓谷。遠くに見える中世の村。
先ほどまで自分の足で歩いてきた道を、今こうして遥か高い位置から俯瞰している現実に、心が高鳴る。
「達成感」とは、こんな感覚のことを言うのだろう。


景色も素晴らしいことだし、この峠で昼食にすることにした。
山歩き一日目の宿でお弁当に持たせてくれた野菜と、二日目の宿でくれたハチャプリ(チーズ入りのパン)。

粗末だろうが、温かい食事じゃなかろうが、山を登りきったあとに口にするものは総じて極上でしかない。
弾けるほどに瑞々しいトマトときゅうり。塩気が体に染み渡るようなハチャプリ。
ありふれた食べ物が、山ではごちそうになる。
この瞬間だけは、「自分が今、世界で一番幸せな経験をしている人間だ」と胸を張って断言できる。
最高の昼食だった。

峠で十分に休息をとったあとは、反対側へと斜面を下っていき、目的地のイプラリ村まで渓流沿いを歩いていくだけ。
距離にして10km弱とやや長いが、体力的には楽勝だ。
峠を越えた先はコースが簡単なことに加え、風景だって登っているときに負けじと美しい。
コーカサスの山々の多種多様な表情に見とれているうちに、あっという間に歩ききってしまうだろう。

黄金色に輝く斜面の向こうに、紅葉が徐々に進みつつある山肌。そして雪をかぶった山頂。
まるでCGで作られたかのようにも見える風景の中を、順調に下っていく。

高低差500mほどの坂を下りきった先には、木造の小さな小屋がいくつか散らばっている不思議な光景があった。

この小屋は、かつて牛飼いたちが夏の間の放牧の拠点にしていたものらしい。
彼らはこの場所から4kmほど離れたハルデという村の住人だったそうだが、その多くは村を後にしてしまったため、小屋だけが残されたのだという。


コーカサスの厳しい四季にさらされながら朽ちていくのを待つだけの牛飼い小屋。
昔話の舞台になってもおかしくないような風景は、迫りくる秋の気配もあいまってか、どこか寂しげで哀愁に満ちた雰囲気を醸し出していた。

かつての牛飼いの小屋からは、渓流沿いに平坦な道がずっと続いていく。
秋の足音が渓谷沿いで小さく木霊しているかのように、この辺りでもぽつぽつと紅葉が始まっている。
牛飼い小屋からちょうど一時間ほどで、ハルデ村に到着した。

現在のハルデ村に年間を通じて定住しているのは、たったの一家族だけ。
もともとのハルデ村は、伝統的な石造りの民家群に数十組の家族が暮らす、典型的なスヴァネティ地方の山村だった。
およそ百五十年前のこと。当時のロシア帝国による支配に反旗を翻した村人が一致団結し、村に十一基あった石塔に立て篭もってロシア軍の砲撃を耐えようとした。
しかし、大国が送った軍隊に山奥の村人が敵うはずもなく、五日間に及ぶ戦いによって村は廃墟と化す。
生き残った村人たちは全てシベリアに送還され、後の時代になってハルデ村に戻って来られたのはたったの二人だけだったという。

ハルデ村の人々の勇敢さもむなしく、ロシア帝国の支配下となったスヴァネティ地方。
しかしながら、大国に果敢にも立ち向かおうとした人々の故郷であるハルデ村は、スヴァネティ地方の人々の誇りそのもの。
村は「スヴァネティの白き頂」と称されるようになり、現在でも語り継がれているのだそうだ。

現在のハルデ村はほぼ廃墟と化してはいるものの、当時シベリアから生還してこの地に戻った村人の子孫にあたる家族が、小さなゲストハウスを経営している。
ここに泊まっても良かったが、翌日のことを考えるともう少し距離を稼いでおいた方が良い。
まだ日が暮れるまで二時間ほどはあるし、そもそもハルデ村にはこのゲストハウス以外は何もないのだ。
歴史が詰まったハルデ村の風景に後ろ髪を引かれつつも、再び緩やかな砂利道を歩きはじめる。
四十分ほどで、今日の目的地であるイプラリ村に到着した。

日没まではまだ時間が残っているが、いまにも山影に隠れようとしている太陽。
民家が十軒ほどあるだけの小さな村を黄金色に染め、一日の山歩きのフィナーレにふさわしい光景を見せてくれた。
イプラリ村では宿の予約はしていなかったものの、そもそも二、三軒のゲストハウスがあるだけの小さな村だ。
どこに泊まっても良かったのだが、たまたま最初に声をかけられた村人が所有するというゲストハウスに宿泊することにした。

何一つ期待していなかっただけに、驚いた。
ここまでの山歩きで宿泊したゲストハウスの中でも、群を抜いて綺麗でモダンだったからだ。


景色も良く、部屋もベッドも快適で、料金も夕食付きで60ラリとお手頃な部類。
全く期待していなかったシャワーのお湯や水圧も完璧で、長い一日の疲れを十分に癒すことができた。
シャワーの後は、食堂に呼ばれて夕食をいただく。
人口十数人の小さな村とは思えないほどに快適な宿自体も素晴らしいのだが、食事でさえもなんだか洗練されている気がする。

見た目にも彩り豊かで、生野菜たっぷりで栄養バランスも良さそう。
味も申し分ないほどの美味しさで、気分は極上のひとことだった。
もはやゲストハウスというか、ミニホテルのような感じの宿。
とても快適で居心地の良さを感じるとともに、昨日まで宿泊してきた「普通の民家」そのものなゲストハウスへの恋しさも少しばかり感じる。
人間とは、どこまでも贅沢なものなのだ。

比較的早い時間に食事を済ませることができ、まだ夕闇に包まれる前のイプラリ村が宿のテラスから見える。
この風景を眺めながらビールでもクイっといきたいところだが、あいにくこの村には商店は見当たらないし、あったとしても山プライスに違いない。
ここは我慢するときだ。早めに寝よう。
ベッドにもぐりこむと、最大の難所を越えた達成感に胸が躍り、明日への期待に胸が膨らむのを感じる。
そう。明日はいよいよ、スヴァネティ地方最奥部に位置するウシュグリ村まで歩く日だ。
天気はどうだろうか。紅葉は進んでいるだろうか。二年前に初めて訪問したときの感動を再び味わうことできるだろうか。
そんなことを考えながら、ふかふかのベッドに包み込まれるように眠りに就いた。
・山男日記(序章)「スヴァネティの山に呼ばれて。」
・山男日記①「スヴァネティの真髄に酔う一日。」(メスティア~チュヴァビアニ)
・山男日記②「中世の村を目指して。」(チュヴァビアニ~アディシ)
・山男日記③「最高の一日に、最高の絶景を。」(アディシ~イプラリ)
・山男日記④「山の神に捧ぐ歌」(イプラリ~ウシュグリ)
・山男日記⑤「光ではなく、影が観たくなる村。」(ウシュグリ)
・山男日記⑥「死の楽園と死にゆく楽園。」(ウシュグリ~ツァナ)
・山男日記⑦「ジョージアで一番閉鎖的な村の、オアシス。」(ツァナ~メレ)
・山男日記⑧「良い旅のつくり方。」(メレ~パナガ)
・山男日記⑨「世界一美味しい、クブダリ。」(パナガ~レンテヒ)
・山男日記⑩「あの山の向こうを、確かに歩いていた。」(レンテヒ~ツァゲリ)
・山男日記(終章)「結局、私たちは何者にもなれない。」




















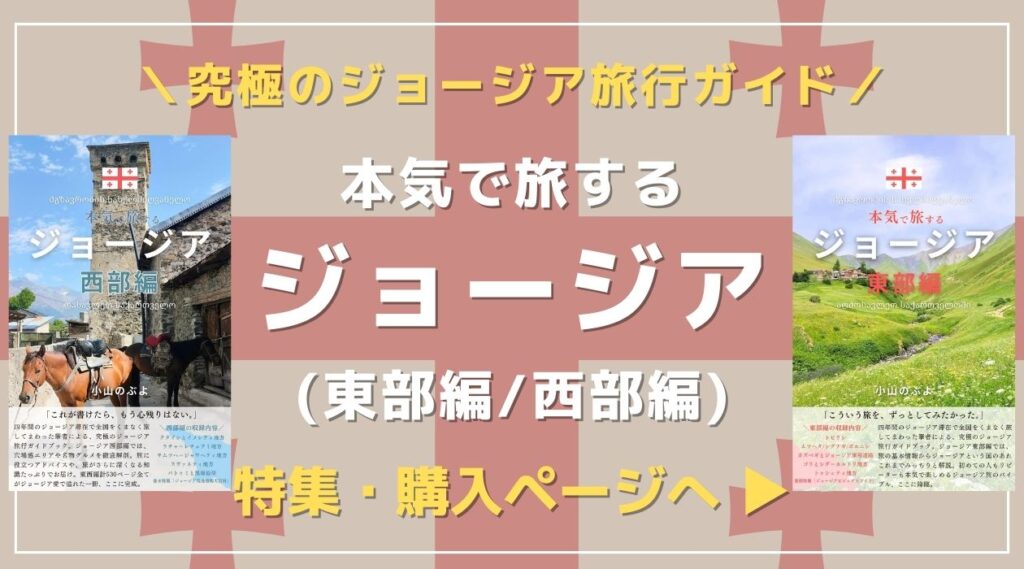




コメント