いつの日か。ふと、あの頃を思い出して、まるで何かにとり憑かれたかのように一心不乱に、夜通し手を動かし続けずにはいられない衝動に駆られるのだろう。
物置の奥底に何年も仕舞ったままの埃を被ったバックパック。時代遅れのデザインに吹き出しそうになるのを堪えながらそれを引っぱり出し、シワシワに折り目がついたパンフレットやら、どうして買ったのか思い出せないほどに微妙なセンスの雑貨やら、着すぎて色褪せたTシャツやら、あの日々を構成していた一つ一つの物たちを、濃く刻まれつつある目尻の皺などお構いなしとばかりに両目を細めて眺めながら、一つ一つ壁に飾る。
ついぞ腰を落ち着けた、ようやく自分のものだと呼べる部屋の、壁一面に。

人間というものは、長期で旅をすることに向いていない生き物なのかもしれない。
明日の予定もわからぬままに、自分の趣味からは程遠い謎センスのデコレーションが施された安宿の壁に囲まれ、どこの誰とも知らぬ他人の鼾に苛立ちつつ、自分のものではないベッドシーツの知らない洗剤の匂いに辟易しながらもくるまって、眠りに落ちようとするその瞬間。ふとそう思うことがある。
せっかくできた旅の友人たちもどこかへ旅立ち、そのうちまた新しく旅の友人となる人がどこかからやって来る。食材や調味料をえっちらおっちら持って移動するなんて御免だから、使い慣れていない粗末なキッチンで簡単な(手抜き)料理を作り胃を満足させる。言葉も勝手もわからない異国の街にようやく慣れて来た頃には、次の街へ移動するときが訪れる。それでも先へ進み続けなければならない。
数週間や数ヶ月の間であれば、その溢れんばかりの非日常感に陶酔し続けていられるかもしれない。むしろ、この「仮住まい感」が旅の醍醐味だと言う人もいるだろう。
だが、それが年単位で続くとなると、その非日常はいつの間に日常に溶け込み、境界線が見えにくくなる。
だから、同じ場所に腰を据えて滞在し、馴染みの店に通ったり、その土地で生きる友人を作ったり、食材や調味料が揃ったキッチンで凝った料理を創作したり…とにかくそうした「生活のようなもの」が恋しくなる。
「人間というものは」なんて主語が大きすぎるかもしれないが、少なくとも自分という人間にとってはそうだ。

この半年間、旅することから遠ざかっていた。心のどこかで欲していた「生活のようなもの」を手に入れ、その快適さに溺れた。明日の予定もわからぬままに彷徨い、知らない洗剤の香りがふんわり漂うベッドシーツにくるまって眠りに落ちるような、あの日々とはとんと疎遠になっていた。
昔の友人との関係がちょっと会わないうちに大きく変化していたり、久しぶりに実家に帰ったら両親が年老いていることに気がつかされたり。
ひとたび疎遠になった人や物と再び関係を築くのは並大抵のことではないし、もしかしたら再び同じ関係性を築くことなんて不可能なのかもしれない。
旅することにおいても、それは同じではないか。
同じ場所に同じ季節に再訪すれば、はじめこそ懐かしさを覚えたり、見知った顔が出迎えてくれることに安心するかもしれない。
しかし、旅を感受する器やアンテナのような存在であり、壮大な物語の主人公でもある自分自身は、時の流れとともに変化している。
たった半年前だろうが、数ヶ月前だろうが、一週間前だろうが、あのとき感じたことを全く同じように追体験することはできない。
だからこそ、旅は面白いのだ。
一つ一つの瞬間も、風景も、出会う人も、空気感さえも、すべてが一期一会で、それらに出会えるか出会えないかを左右するのは、紛れもなく主人公である自分の決断だけなのだから。
つまりは旅は究極の「運ゲー」。しかし運だけに100%左右されてしまうような、理不尽なプログラミングのもとに成り立つ糞ゲーではない。
自分の決断次第なのだ。宿選びだって、予定の立て方だって、食事する場所だって、今日はビールを一杯飲むか否かだって…こうした小さな決断の一つ一つが出会う人や出会う風景、思い出までも大きく変化させるし、それをもう身にしみて経験している。
そうした意味では、旅は人生の縮図のようなものかもしれない。どうせ黙っていても人生は続いていくんだから、飽きるまで運ゲーを楽しむのも良い。
だから、また旅に出ることにした。
以前と同じ気持ちや感動に浸ることはもうできなくなっていたとしても、それを凌駕する新たな感動や、発見や、出会いが必ず待っているから。
いや、「待っている」のではなく探しに行くのだ。自分の足と五感と感性をフルパワーで発揮させ、小さな決断を重ねながら。

いつの日か。「ああ、あの頃あてもなく旅していた自分があったから、どれほど今が幸せなことか。」と独りごつのかもしれない。
ようやく腰を落ち着けた、自分のものだと呼べる部屋。その壁いっぱいに飾られた旅の証をぐるりと見渡し、自分の呼吸の音だけを聞きながら、嗅ぎなれたいつもの洗剤の匂いがふんわりと漂うべッドシーツにくるまって、眠りに落ちようとする、その瞬間に。




















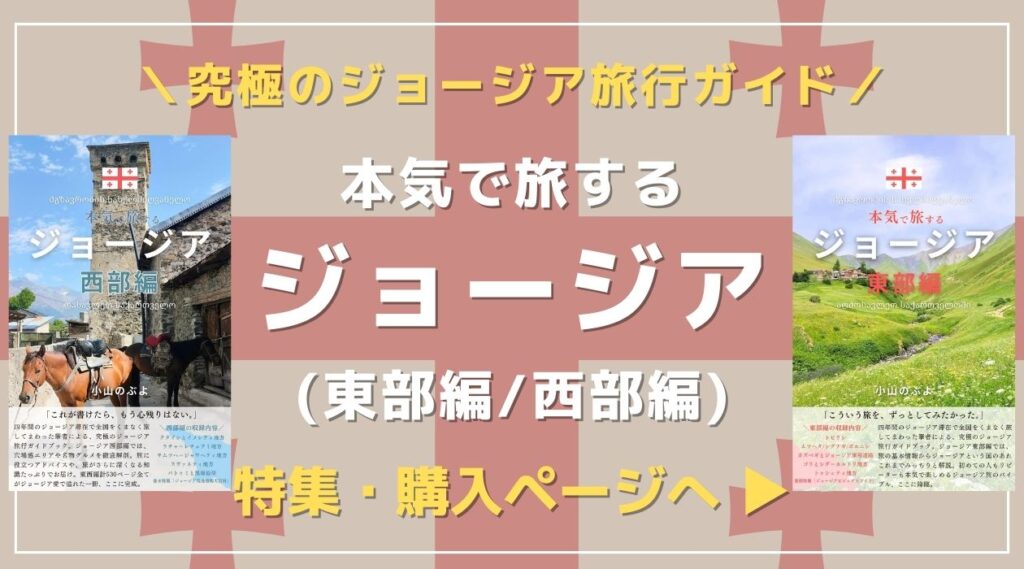
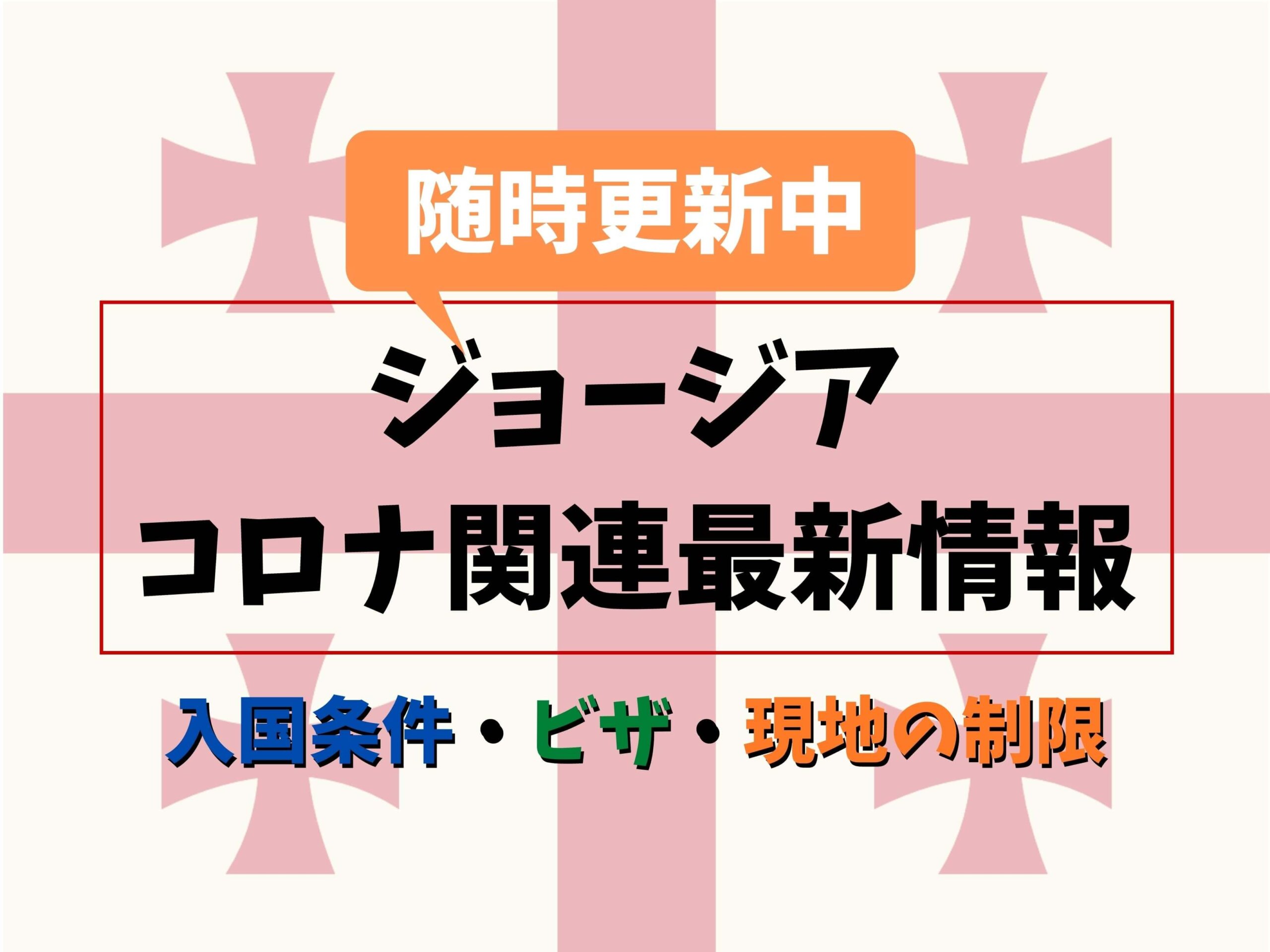

コメント