「俺、戦争で5人殺したんだ。」
まるで「今日は早起きしてランニングして朝ごはんを食べて仕事に行った。」と、何てことない一日をつまらない箇条書きで語るように。
もしくは「去年の夏のバカンスは海辺で過ごしたんだ。」と、色褪せつつある一枚の写真を懐かしく眺めるかのように。
静かな口調で淡々と、しかし何らかの確かな感情を込めつつ、彼はそう云った。

アルメニアの首都・エレバン。
同国最大の都市であり、人口百万人余りを数える大都会。その片隅にある安宿には、外国人だけでなく地方部出身のアルメニア人も多く集まる。
その中の一人が、ジャンという青年だった。
ナゴルノ=カラバフ自治州(アルメニア語では「アルツァフ」)出身の彼の体には、アルメニア人の血が流れていながらも、厳密には「アルメニア共和国の人間」ではない。
ナゴルノ=カラバフは、国際的にはアゼルバイジャンの一部とみなされている。しかし住民の大多数はアルメニア人。
ソ連崩壊前後のゴタゴタによってアゼルバイジャンの一部となった後は、宗教や民族の違いに領土問題が絡み、三十年ほどの間ずっと諍いが絶えない。そんな地域だ。
ナゴルノ=カラバフ出身者に実際に出会ったのは、はじめてのことだった。
昨年、この地域で起こった戦争は記憶に新しく、彼もまた戦火を逃れてエレバンにやってきたのだと推察した。
アルメニアでは、長年の敵国であるアゼルバイジャンに関する話や、ナゴルノ=カラバフに関する話はなかなか出しにくい雰囲気が漂う。
昨年の戦争に負け、それまで実効支配していたナゴルノ=カラバフの一部地域をアゼルバイジャンに取られてしまったのだから。
人々のアゼルバイジャンに対する心情は複雑である(というか「憎悪」に近いものが確かに存在する)ことは間違いない。
いずれにせよ、この国にたった数ヶ月いるだけのいち旅行者風情が、軽々しく話題にするようなテーマではない。
そう思って、こちらからは戦争に関する話をあえてしないようにしていた。

連日40℃越えの灼熱の日が続く真夏のエレバン。
暑さがようやくおさまるのは、太陽が顔を隠す午後8時を過ぎてからだ。
安宿にもかかわらず妙に小奇麗に保たれた中庭は、夕涼みをかねて毎晩宿泊客が集うスペースとなっている。
ジャンがこの「夕涼みスペース」に顔を出すことはあまりなかったのだが、なぜかこの日は長い時間寛いでいた。妙に饒舌だったのは(英語はそこまで話せないため、ロシア語で)、夕涼みのお供のビールのせいだったのかもしれない。
アルメニア人らしい細身の体格と、くっきりとした顔立ち。柔らかな物腰に素朴な笑顔。
26歳になったばかりだという彼は、生物学的にも社会的にも「人生のピーク」にあたる黄金時代を生きていて然るべき人間だと思う。
しかし、彼の「人生のピーク」を待ち受けていたのは、恋愛でも仕事でも旅でもない、戦争だった。
誰に促されたわけでもなく、彼は昨年のナゴルノ=カラバフ戦争での経験を語り始めた。
ナゴルノ=カラバフの男子には2年間の兵役義務があり、2017年から2019年にかけてがジャンの兵役期間だった。彼が兵役を終えた1年後の2020年9月に、戦争が再燃した。
つまり、最前線で戦う義務を負うことは免れたわけだ。
しかし彼は、そんな安寧の地に自分の身を置くことを許さなかった。
ナゴルノ=カラバフはもちろん、アルメニア本国でも、兵役に就いていないにもかかわらず戦地に赴いて戦おうとする義勇兵が多く見られた。
ジャンはすでに兵役を終えていたにもかかわらず、義勇兵として自ら志願し、戦地へと向かったのだ。
「去年の戦争は本当にひどかった。何度も死にそうになった。」
淡々とそう語る彼の口調はどこか達観しているように感じられた。きっと、いち他人が計り知れないほど、本当に悍ましいものだったのだろう。
アゼルバイジャン軍によるクラスター弾が直撃して破壊された町や、ドローンを利用した最新の無人兵器による攻撃…
「アルメニア側はもはやなす術もなし」
当時ニュースを見ていただけでも、そんな印象を持った。
実際に、自らの命を危険にさらしながら祖国のために戦地へと赴き、敵国との圧倒的な力の差を目の当たりにさせられた若者の気持ちとは、いったいどんなものなのだろう。
死への恐怖だろうか。それとも絶望だろうか。
「俺、あの戦争で敵を5人殺したんだ。でも、結果として自分の国を守りきることはできなかった。」
相変わらず淡々と、しかし確かに熱情のようなニュアンスを舌先に留め、彼はそう語る。
鳶色の瞳をいくら熟視したところで、彼がどんな思いでこの話をいち旅行者風情の人間にしているのかを察することはできなかった。
両親や兄弟、友人など、大切な人を守るため。
もっと大きく言うなら、大切な人が暮らす自分の国を守るため。
時に人は、自分の命を危険にさらそうとも、戦う道を選ぶ。
「もしあなたが戦争で死んだら、残された人たちはどうなるの?」
「敵にだって守りたい人がいるのでは?」
「国のために命を捨てるなんて馬鹿げてる!」
そうした言葉で命の大切さを説きたくなるのは、私たちが安寧の地から戦争を鑑賞しているだけの傍観者だからだ。
「守るべきもの」と自分の命とを天秤にかけ、生まれた決意の揺るがなさは、実際に経験した当事者たちにしか分からないのではないか。

幸いにもジャンの家族は誰一人戦争の犠牲となることはなく、ナゴルノ=カラバフの首都・ステパナケルトでいちおうの平穏を取り戻した生活を送っているそうだ。
戦争は憎しみしか生まないが、彼が敵国を(言葉にして)悪く言うことは最後までなかった。
しかし、20代半ばの青年の心に刻まれた憎しみの炎は、きっとまだ消えてはいないだろう。
真っ赤で仰々しい炎を噴かなくなった木炭が、チロチロと静かにくすぶり続けているように。
そしてひとたび風を吹かせれば、チロチロと燃えていただけの炎が、一気に温度を上げて燃え上がるように。
憎しみは心の奥底でくすぶり続け、ふたたび劫火となる機会を耽々と待っているのではないか。

「これが俺の弟。今ステパナケルトの大学で生物学を勉強していて、研究職に就きたいみたい。」
戦争の話で沈み切った場。その空気を入れかえるかのように、ジャンが誇らしげに見せてきた写真。
兄に比べてがっしりとした体格の青年がいた。5歳ほど年下だろうか。
笑顔ではにかむ彼の弟は、戦争の経験こそあれど、自身が戦場に出向いたことはまだないのだろう。
数年後には2年間の兵役が彼を待ち受けている。その期間にふたたび戦争が勃発しない保証などどこにもない。
「どうかジャンの弟の夢が、新たな憎しみの炎に焼き尽くされることなく、叶いますように。」
口には出さず、ひそやかにそう願った。
おそらくそれは、ジャンの心の奥底にくすぶる憎しみの炎のすぐ隣に存在する希望と、同じ類の「願い」だったはずだ。
普段は旅行情報や海外情報を主に発信している当ブログですが、これまでの旅を通して感じたことをフォトエッセイ形式でお届けする新企画が「世界半周エッセイ」。
各国で体験した出来事や、出会った人たちとの思い出がテーマとなっています。




















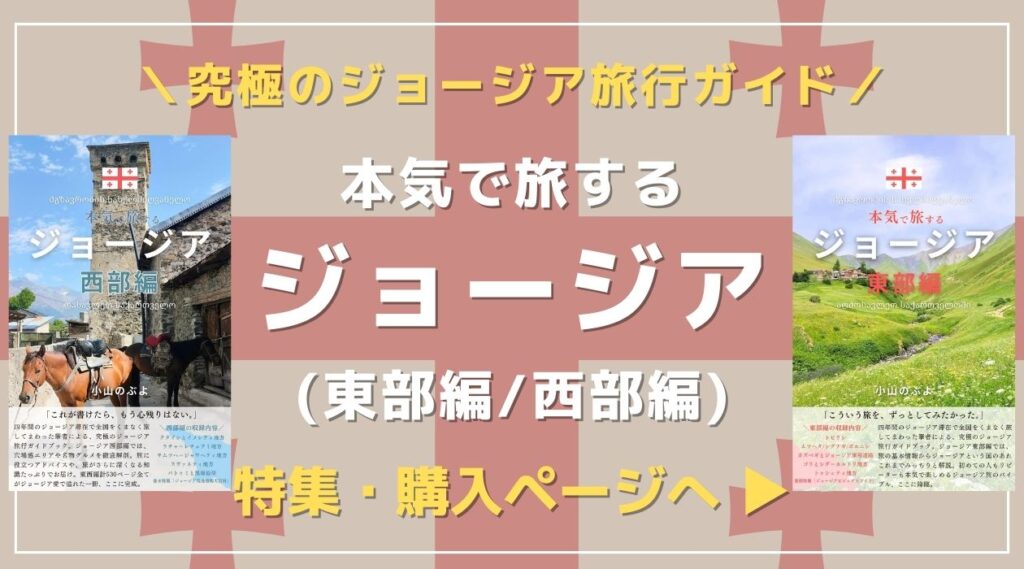


コメント